- HOME
- 連載長編小説『4 LOVE NOTES』
- 第2話 『有紗の事情』
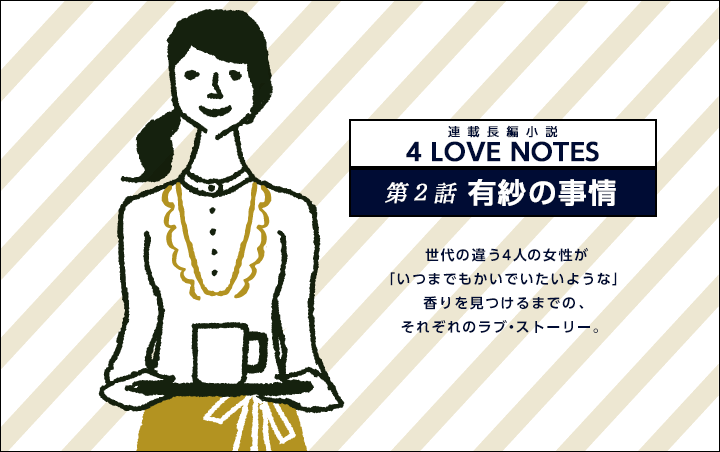
【ここまでのあらすじ】
暗闇でご飯を食べるイベントで偶然知り合った女性誌編集長の鍵崎多美子(50代)、フラワーアーティストの内畠麻貴(40代)、カフェでパティシエをする野添有紗(30代)、旅行代理店勤務の殿村未知(20代)。
世代が違いながらもなぜか通じ合うところを感じた4人は、有紗がパートナーの勝瀬とともに経営する池尻のビストロで女子会をすることになった。
《1》
246号線から細い道を1本入り、うねうねと住宅街に入ったところに、ビストロ・ドゥ・ミニオンの黄色に茶色の文字の看板がある。
休業日のはずの月曜の店内には、そろそろオーブンを開けたくなるシューの焼ける匂いが立ち込めていた。
野添有紗は膨らんだシューの形を確かめる。自然に笑みがこぼれる。5年近く使っている銀色のミトンをさっとはめると、オーブンの扉を開けた。
白い細面の顔を、熱気がもわっと覆う。
切れ長の目を見開いて、重めの鉄のトレーをよいしょと引っ張り出した。
クリームは既に作ってある。ほのかにミントを効かせたカスタードクリームにコンポートにしたグレープフルーツを挟み込むのだが、それは皆がメインを食べているときにやるつもりだ。
前菜からメインまでは、オーナーシェフでパートナーでもある勝瀬洋三が夜中に概ね仕込んでおいてくれた。今頃は家でジャージのまま、ネットニュースでも見ていることだろう。
「ええと、鰹のカルパッチョは、林檎のソースで、サラダにはこのエディブルフラワーを散らして、と…」
独り言を言いながら、段取りを確かめる。18時40分。19時にはあの3人がやってくるはずだ。
窓辺の4席だけに、お皿とカトラリーを並べてある。他にお客さんがいない日に一人で料理を出すのは、なんだかホームパーティーのようで、有紗はちょっとわくわくしていた。
それにしても、暑い。冷房はちゃんときいてるのかと、リモコンを手にしたとき、白いエプロンのなかのスマホが振動した。
勝瀬からだ。有紗は彼と話すときだけは故郷の言葉になる。
「一人で大丈夫か」
「うん。今ね、シューも焼けたとこ。いろいろありがとうね」
「ずっと忙しいのに、休みの日に店開けたいて、よっぽど大事な友達やねんな」
「まあ、最近会うたばかりやねんけどね。感じのええ人らやねん」
「そうか。俺、ほんとに行かんでもええんか」
「ええよ、美人もおるから」
「ほんならいつでも呼んでくれや。… ああ、着替えんのめんどくさいけどな」
「そやろ。大丈夫大丈夫。それより腰、どう?」
「横になってたらマシや。すまんな、じいさんで」
「何言うとお。予約取れたらマッサージ行ってきたほうがええよ」
「はいはい… ほなね」
「はーい」
有紗は切れたスマホをまたエプロンのポケットにそっと入れた。
- <<前のページ
- 1/4
- 次のページ>>






