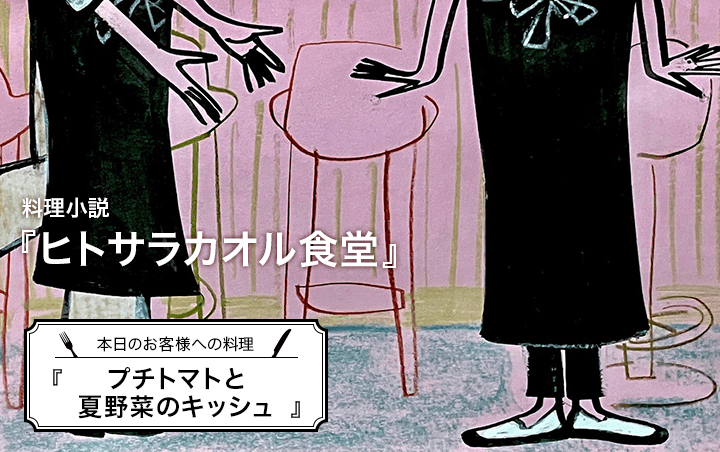
幸の人生は、半分以上おせっかいでできている。
確かに、土日にブランチを出せば観光客も来るかな、とは考えたことはあった。
しかし自分だけではちょっと手が足りない。ひとりくらいアルバイトを雇って、などとも思っていた。
驚くべきことに、凛花が大城のことを好きらしいからなんとかしてあげたい、というおせっかいは、妙な着地を見てしまった。
凛花をバイトに雇う、ということだ。
大城の帰り際、咄嗟に「週末ブランチをやる」「凛花ちゃんが手伝いに来てくれる」と言ってしまった。
けれども幸は、凛花の手伝いを、さほどあてにはしていなかった。
大城が来そうな日になんとなく彼女を呼んで、サービスを手伝ってもらおうくらいの腹づもりだったのだ。
だが凛花は本気を見せた。
「幸さん。私に調理も教えてもらえませんか」
「お料理はやったことはあるの」
「いいえ」
凛花の返事は、あまりにもきっぱりしていた。
🥂Glass 1
日中の最高気温は35度、というような月曜日。
日陰のない代官坂は人影もまばらだ。
ヒトサラカオル食堂の「定休日」という看板の向こうで、長い髪をきつくポニーテールにした凛花と、いつものギャルソンエプロンをした幸が向かい合っていた。
二人のテンションはまたかなり熱かった。
「これ、つけて」
幸は、買っておいた自分と同じエプロンを凛花に付けさせた。
「うん。なかなかいいんじゃない」
見た目から入るのも大事だ。
「わあ、ありがとうございます。嬉しいなあ。なんだか、自分が料理ができる人のような気がしてきました」
「大事大事。気がするのは、大事よ」
ブランチは、キッシュからと決めていた。これならホールでいくつか焼いておけば、その場で切って温めて、スープとサラダをつけて出せばよい。
そしてとりあえず、今日は試作でいい、と幸は思っていた。
「試作のキッシュを作ります」
「はい」
「冷凍のパイを伸ばして、型に入れて、フォークで穴を開けます」
「あ、これは楽勝」
凛花は力一杯フォークを突き刺している。
「いやいや、そんなに力入れたら型が傷ついちゃうよ。適当にね」
「あ、はい」
「でね、玉ねぎとベーコンとマッシュルームは、塩胡椒で火を通しておきます。こんな感じ」
「なるほど… あ、今何入れたんですか」
「少しだけナツメグね」
「どうなるんですか」
「ちょっと甘い香りがつくの」
凛花はフライパンに鼻を寄せた。
「ほんとだ。私、この香り好きです」
「ハンバーグの玉ねぎを炒めるときにもちょっと入れるといいのよ」
「ナツメグ、ナツメグ、メモメモ」
凛花は真面目にスマホにメモして、氷の入ったグラスの水をごくりと飲んだ。
- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






