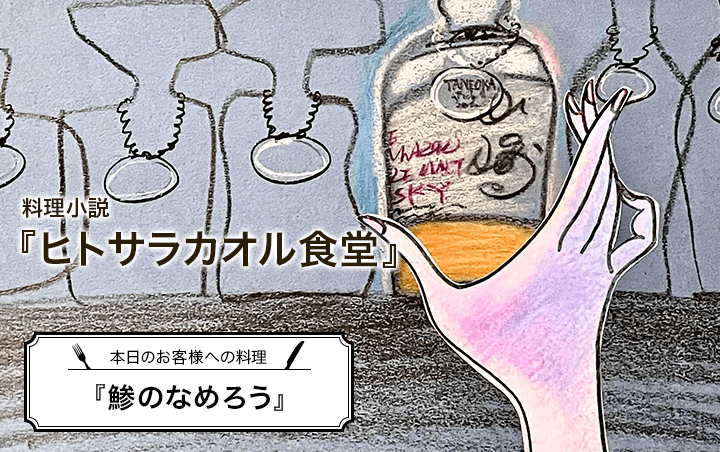
日本の夏がどんど暑くなる。体温くらいの気温が当たり前になってゆく。
朝のワイドショーでどこかの学者が言っていた。「これはもう異常気象ではありません。ニューノーマルなんです」。なんでもかんでも横文字の名前をつけて「ていうことなので、よろしく」という風潮である。
幸はテレビを消した。
一体どうしてこんなことになってしまったのか。世界のニュースを見ていると、気候変動が激しすぎてあちこちで天災が起こっている。山火事。大雨、洪水。地球は大丈夫か。
幸は鏡を見た。すっぴんの顔はだいぶ老けて見えた。
いやいや「ヒトサラカオル食堂」は大丈夫かが先だ、と、幸は思った。人間は、とりあえず自分の顔の周りの空気を吸って生きている。
この暑さでは、なかなかお客さんが家を出ない。この店までたどり着けない。
きんきんに冷やしたクラフトビールは、出番を待っているのだけれど。
狭い店は、誰もいなければ冷房が寒いほどなんだけれど。
確かに、お盆休みもはじまったようだけれど。
22時を過ぎた。もはや一人で飲むしかない。
幸は思い切って看板を下げた。
冷蔵庫を開け、今日中に食べなければならないものを見極める。これは冷凍できる。これはまだ大丈夫。… 問題は生魚だ。仕入れた刺身用の鯵は、なめろうにすることにした。
ねぎ、大葉、茗荷をみじん切りにする。生姜をすりおろす。自家製の味噌をひと匙すくい、一番小さい硝子のボールに入れた。
さて、鯵を叩こう。
2本の小さな包丁を使って、薬味と味噌、塩を混ぜ込むように叩いていく。生姜を混ぜ、最後に少し、山椒香油をたらして叩く。
包丁についたところを人差し指でなぞって味見すると、なかなか美味しくできていた。
「誰かに食べてほしいなあ」
思わず独り言が出た。こればっかりは出来立てでなければ出せない。あきらめて皿に盛り、小さな冷酒の菊水の瓶を捻った。
「いただきまーす」
こういう時のなめろうは皮肉なくらい、完成度が高い。
ちまちまと箸ですくい、冷酒を飲みながら、ふと、大阪時代のある夏の夜のことを思い出した。
🥂Glass 1
あれは幸が北新地に戻り、若くして店を任されてしまった頃のことだった。
世の中はバブル景気の真っ盛り。毎夜毎夜、店はお祭り騒ぎだった。こちらのテーブルとこちらのテーブルが合体して盛り上がったり、次の客のために席を移動してもらったり。誰が誰を連れてきたのか、把握しきれない日もあった。
4人ほどいたひと組のメーカーの客を外まで見送り、店に戻ってくると、奥のソファの片隅に、静かに座っている男を見つけた。
「あれ、ヒトミちゃん、あれ、誰やったかな」
「えー。誰ですかあ。… ああ、O組の人ちゃいますか。でも顔がようわからん」
皆忙しく、一人で静かに飲んでいる客のことはそっとしておいてあげようという気持ちと、盛り上がっているところをさらに盛り上げて、ドンペリをバンバン開けてもらおうという気持ちが半々だった。
幸はママとして、一応、全ての客を把握していた。
その男のことが気になり、近くへ寄っていった。俯いている顔を覗き込んだ。青ざめて無表情だった。が、彼がゼネコンO組の社員だと気づいた。
一度来た客の名前は憶えるのが幸の仕事だ。
「碓井さん、ですよね」
男は黙っていた。幸は以前、彼を連れてきたのが、O組の種岡という男だと、脳の中のあみだのような組織図から思い出した。
「種岡さんのボトル、出しましょか」
「… たねおか」
男は呟いた。絞り出すような声だった。
幸はボトルを探しに棚へ戻った。種岡のボトルは山崎で、あと3分の1ほどあった。
「これこれ」
名札を確かめ、碓井のいた席に戻ると、彼はいなかった。
「あれ… 碓井さん… 帰らはった?」
幸はもう一度、別の放送局のグループで盛り上がっていたヒトミの耳元へ尋ねた。
「ここに座ってはった人、帰らはった?」
「誰かいましたっけ」
ヒトミは目を細めて、その席のあたりを一瞬見て「あ、岸本さん、もうブランデー空ですよお」と、つや消しの緑色の瓶を持ち上げて、最後の10ccほどを彼のグラスに注いだ。
「いらっしゃいませー」
大笑興業のお偉いさんがたがやってきて、そのまま、幸はその流れに入ってしまった。

- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






