- HOME
- 連載長編小説『4 LOVE NOTES』
- 第22話 『多美子のパーティー』
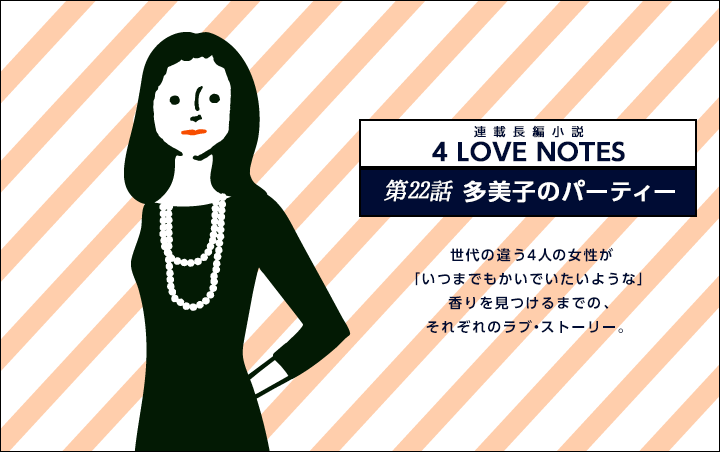
【ここまでのあらすじ】
鍵崎多美子は大手出版社の女性誌の編集長だったが、IT制作会社社長の岸場鷲士と出会い、彼が不祥事から退社することになって一緒に会社を立ち上げた。自ら立ち上げた雑誌「Luck me」のWEB版を作ることになったが、切り詰められた制作費のなかで苦労する。一方の鷲士は何をしているのか、なかなか姿を見せなかった。
《1》
1月末の北西角部屋は寒かった。株式会社ミッション・グレイスのオフィスには開かないガラス窓が両面にあったが、西側にはビルがあって、鎧戸になったロールカーテンを開けることも憚られた。日当たりはそうよくはない。
大きな白木のテーブルが二つ、鉤型に並んでいた。鍵崎多美子は西側のテーブルで、今朝もコーヒーを飲みながらPCに向かっていた。
コロン、と音がして、メールが着信した。
「おはようございます、岸場です。」
きた、と多美子は思い、ひとりごちた。
「どこでなにしてんのよー」
PCの画面はそれに答えるような文面をあらわにした。
「ようやく、サポートしてくれる人や、新規事業の目処もついてきました。
ついては今週金曜の夜に、ミッション・グレイスのローンチ・パーティーをやろうと思います。
うちのレジデンスのパーティールームを借りたので、そこで。
酒関係は知り合いの店に頼んだんですが、どこかケータリングしてくれる人はいませんか。いなかったら適当な店に頼みます。
鍵崎さんのほうで呼びたい人にもぜひ声をかけてください。」
「はあーっ」
多美子は画面に思いきり突っ込んだ。
「まず、人数を教えろってば」
その言葉が聞こえたかのように、コロン、と次のメールがやってきた。
「僕のほうは30~40人かな。鍵崎さんのほうと合わせての数で、一人3000〜4000 円くらいの予算でなるべくゴージャスだとうれしいです。」
「そりゃ、うれしいだろうよ…」
多美子は一瞬、恨めしげにつぶやいて画面を見つめたが、スマホの画面を素早くスクロールすると、知り合いの料理研究家に電話していた。
「三上先生。ご無沙汰しています、集学社にいた鍵崎です。今、お話ししても大丈夫ですか」
「あら〜、鍵崎さん。お元気ですかあ。はい、今パンの発酵中なので大丈夫ですよ」
「先生、お忙しいですかね。あの、今週の金曜日に、ケータリング50人分なんて…」
「えーっ。今日、火曜日よね」
「はい… 申し訳ありません」
三上知恵子は『ワインのとまらないおつまみ』シリーズで大人気の料理研究家だった。多美子はなんとしても、ここは名のある人の料理でなければならないと考えたのだった。
なんとか了承をとりつけると、すぐ鷲士にこう返信した。
- <<前のページ
- 1/4
- 次のページ>>






