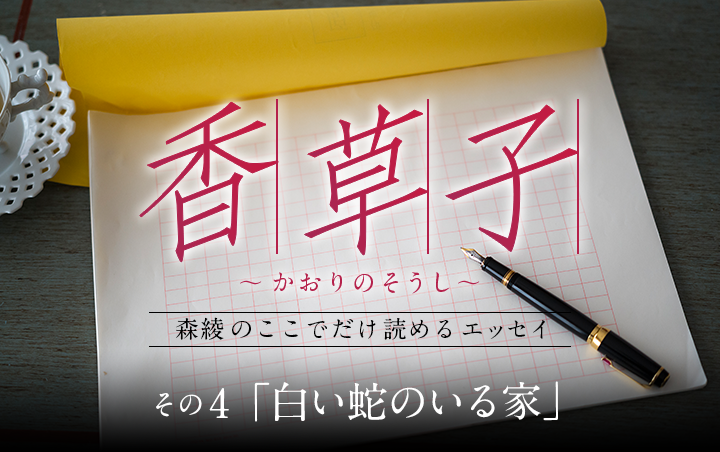
●白い蛇と、白い蛙
毎日通う母方の祖父母の家は、明るかった。工場には何人も人がいたし、“店”と呼ばれる玄関には、いろんな人がやってきたから。
しかし明治に建てられたその家は、建物自体が、どこか謎をはらんでいた。
平屋建てで、玄関を入るとまずデスクがふたつと応接セットのある“店”があり、一段上がったところに大きな居間があり、そのまま祖父母の寝室でもある仏間へとつながっていた。居間の奥にまた一段下がった台所とダイニングがあって、その隣に小さな押入れのある小部屋があった。その先がお風呂だった。
時折、居間の上の天井で、ざあ、ざあ、ざあという、砂をこするような音がした。
「なんの音かな」
その日のざあざあは、お昼時にみんながご飯を食べてお茶を飲んでいるときに起こった。
私は天井を見上げた。音は端っこのほうから、部屋の真ん中の上へと移動していく。
祖母は事もなげに言う。
「みいさんや」
「みいさん、って」
「蛇や」
「えっ」
私は怖くなって祖母の膝ににじり寄った。しかし、祖父ももう慣れていて「みいさんや、みいさんがいてはんねん」と、歌うように言って工場へ行ってしまった。
私だけがいつまでも天井を見つめていた。
祖母が言った。
「今まで何回か、落ちてきたはったこともあるで。白い蛇や。そやから、あそこの神棚で、お祀りしてるんや」
確かに一角に大きな神棚が吊り下げてあった。ひと月に一度「みいさんの神さん」と呼ばれる巫女らしきおばさんがやってきて、祝詞をあげるのである。
「商売の家にみいさんがいてるというのは、素晴らしく縁起のいいことなのです。この家は商売繁盛でしょう。ありがたいことです」
そのみいさんの神さんは、怖がる顔をしている私にそう言った。
蛇は何度か、工場の近くでも発見された。白い蛇だった。私は蛇の姿は憶えていないのだが、縁側の近くで白い蛙を見たことは憶えている。
「おばあちゃん、白い蛙がおった」
「蛇とちごてか」
「うん。白い蛙」
叔父も白い蛙を見たようだった。
「白い蛇は商売繁盛やったら、白い蛙はなんやろう」
母が言うと、祖父はにやにや笑って言った。
「白い蛙も神さんや。うちは守られとるんや。よかったよかった」
一時が万事、そういう明るい結論が出る。もちろん、いいかげんな話ではある。でも、受け入れて、憂えない。それは、生きていく上でどれだけ大事なことか、小さい私にはまだわからなかった。ただ私は、この家がとても安心できたのだった。
- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






