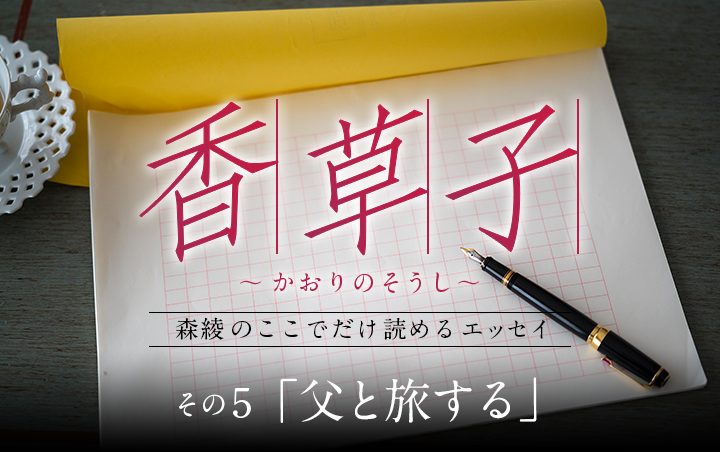
●「ふるさと」はどこにある
2歳になる直前に、私は突然喋り始めたらしい。母曰く「赤ちゃん言葉でなく、まったく普通に喋り始めたので、最初、あれ、誰がいるんだろうとキョロキョロしてしまった」という。
そういうことはわりと珍しくないようだ。後年、夙川プリスクールの渡辺洋一園長の御著書を手伝ったとき、こんな話を聴いた。
「子どもがいつ喋るか。それは、コップに水が溜まるように言葉が溜まって、それがあふれ出すときなのです」
私が母のおなかにいるときから、父はいろんなものを読み聞かせていた。胎教には少し的外れで、森鷗外の『雁』だったりした。父曰く「日本で一番美しい口語体の小説だから」だったそうだ。
母方の祖父母の家で大人たちの会話を日がな聴いていたり、近所に少し年上の子どもたちが何人かいたことも、私のコップの水を早く溜めたのだろう。
夏前になると、子どもたちのなかでは「夏休みに田舎に帰る」話になっていた。
「うちの田舎は山があるねん。かぶと虫とか、とんぼがおるねん」
「うちの田舎は海で泳げるねん。海の水はしょっぱいねんで」
私は母に尋ねた。「うちの田舎はどこ」と。
母方も父方も、祖父母の家は大阪市内である。
「大阪やんか。豊崎のおじいちゃんとこが、田舎や」
それは意味が違う、と思った。そんな街中は「田舎」ではない。小さい私はひどく落胆した。
「ちゃう。そんなん、田舎とちゃう」
欲しいものを与えられ続けている初孫の私にとって、それは初めて絶望的に手に入らないものだったのだろう。
当時、母親は弟をみごもっていて、私はひょっとしたら「母を弟にとられている」ような寂しさも芽生えていたのだろうか。
ある夜、父と母は話し合っていた。
「みんなが海や山や、言うてるのが羨ましいみたい」
「そうか。なんかここがふるさとや、っていう記憶をもっておくのは大事かもしれんな。おばあの里へでも連れていくか」
「和歌山?」
「うん」
「遠いやん。あの子、車に酔うのに、大丈夫かいな」
「汽車で行ったらええ」
「だいぶかかるやろ」
「5時間ぐらいかな。トイレもついてるから。大丈夫や。海も近い」
紀伊日置という駅だった。白浜からまだ3つ先で、鈍行しかなかった。
「おおい、綾、田舎いくぞ。お父さんと和歌山行こう」
「うん!」
そうか。うちの田舎は海なのか、と嬉しさがこみあげた。海はしょっぱい味がするらしい、と思い出した。「めばえ」や絵本に出てくる浮き輪をもった海水浴の絵をめいっぱい頭のなかに広げた。
「水着がいるな」
と、母が言った。
「泳げるかな」と父は不安げに言った。父は泳げないと母が言っていたことがあった。
「パパ、浮き輪があったら泳げるで」
と、私は言った。父は苦笑いしていた。
- <<前のページ
- 1/4
- 次のページ>>






