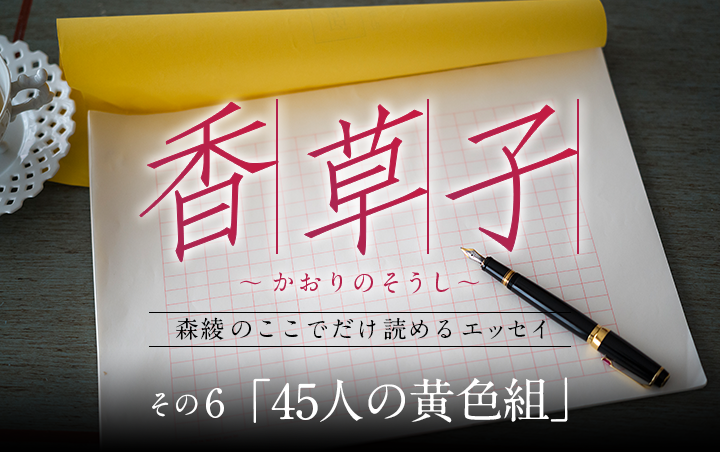
●トリイ先生のダメなサンドイッチ
大阪市旭区北清水。昭和40年代、私が住んでいた街は、大阪市と守口市の境目ぐらいにあった。
その地域には、子どもはあふれんばかりにいたのに私立の幼稚園しかなかった。
2年保育が当たり前だった。少し離れた、女子校の付属幼稚園には、3年保育もあったが、3歳の子どもをバスに乗せてそこへ通わせる家はほとんどなかったと思う。幼稚園も心得ていて、おそらくそんなにすごい保育料もとっていなかった。
いくつか選択肢はあった。
そのなかで、私はしごく普通な、真ん中の幼稚園に入れられた。
帝国学園大学付属幼稚園、といういかめしい名前がついていたが、特に思想はなく、普通に誰もが通う幼稚園だった。
1クラスは45名で4クラス。いくつか幼稚園があるにもかかわらず、その生徒数には「子どもが多かった」時代が彷彿とされる。
年少のときのクラスは黄色組。担任はトリイ先生という、25~6歳のしっかりした先生で、副担任が一人ついていた。しかし、私には副担任の記憶はない。
5歳になる歳の4歳の子どもたち45人を背負うのは、どんな心境だったのだろう。今の保育体制ではちょっと考えられない。
しかしトリイ先生はしっかりしていると評判だった。全員の名前や特徴をすぐに把握していたようだった。
お弁当は月曜と木曜がおにぎり、火曜と金曜がサンドイッチ、と決められていた。私は唾液の出が悪かったのか、サンドイッチでよく喉をつまらせていた。母は最初、パンにキャベツをいためたものと、ハムをはさんだ。すると、なぜか時間の経ったキャベツがひどく臭いように感じられた。パンに水分が移り、べちゃっとするのも嫌だった。そこを食べると、うっと吐き気がした。そこで私は、キャベツを剥ぎ取って、弁当箱の縁に寄せていた。
トリイ先生はそれに気づいた。そこまで目を配っていたのかと今思うと恐ろしい。
「どうしてそんなことするの。お野菜も食べないと」
私は「臭いから」と言った。トリイ先生は母に手紙を書いた。お弁当の中身を変えてほしいという内容だったのだろう。それから母は、パンをトーストし、お砂糖とはさんだものと、チーズをはさんだものを作ってくれた。
生徒たちは順繰りに、先生の近くのテーブルで食べる。ある日、私もトリイ先生と同じテーブルで食べた。その日はサンドイッチの日だった。そこにいる誰もが、トリイ先生のサンドイッチが気になった。
先生のサンドイッチは、見たことのない形状だった。
コッペパンの間にオレンジ色のジャムがはさまったものを薄く切ってあったのだった。
それは明らかに、買ってきた菓子パンを一口大に切ったものだった。
トリイ先生はそれをおちょぼ口でゆっくり食べた。
「トリイ先生のサンドイッチ、美味しそう」
誰かが言った。私もそう思った。
先生は赤くなった。自分のサンドイッチの「ずる」がばれてならないと慌てた。
「これはね、違うのよ、これはダメなサンドイッチなの」
先生は左手で軽くそれらを隠した。
「えーっ、なんでなんで」
「ダメなの。みんながお母さんに作ってもらっているサンドイッチのほうがずっと本物で美味しいのよ」
私は家に帰って、先生のサンドイッチが美味しそうだというのを説明した。 母は「先生は忙しいから買うてきてはるんやな」と笑った。
- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






