- HOME
- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』
- 第1回『祖母のおしろい』
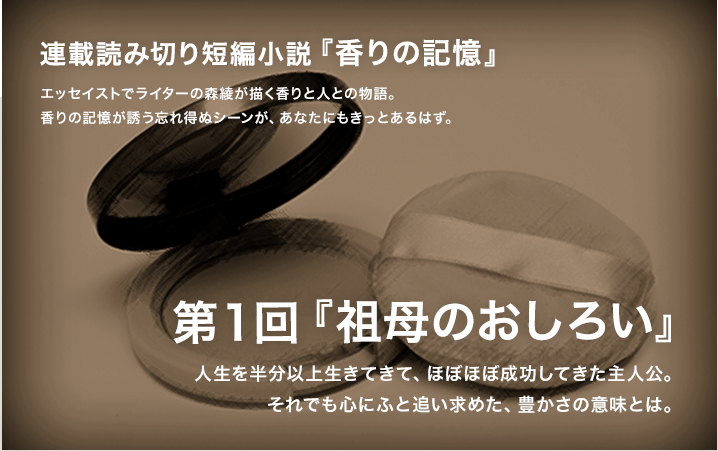
《1》

道頓堀の上にゆらゆらとネオンが落ちる。
それは赤と青と白で、混じり合うことなく川面に流れていく。
大阪・ミナミの夜はどことない喧騒が響き合う。
少し、泥臭い川の匂いに、うっすら焼けたソースの匂いもするような。
毛穴を満たすような街だな、と信三は思う。
武田信三は元々は東京生まれの東京育ちだ。それが何の因果か、今はこの大阪で、もう20年以上も放送局の営業部長をしている。しかも最近、取締役に昇進したばかりだった。
それでも彼は、北新地の名門クラブのような気の張る場所よりも、このミナミの一角の、カビ臭いバーを好んでいた。
ゆるゆると階段を登ると、足跡に合わせてぎいぎいと板がきしむ。
疲れた腕がもたれるようにドアを押す。
「まいど」
その大阪商人の言葉が、20年以上前は大嫌いだった。
が、今の信三は自虐的にそれを使う。
八の字の髭をたくわえた顔色の悪いマスターの細面がこちらを向く。
「ぃらっしゃい」
そして、奥にふた席残した3番目の席に、信三のためのコースターを置く。
「いつもの?」
「だね」
目の前にやってきたのは、丸い大きな氷に注がれたバーボンと、氷水だった。
「今日は、そろそろかな」
「ですねえ」
いそいそと恋人のように待つ。信三だけでなく、マスターもその相手が来るのを待っているようだった。
1杯飲み、2杯飲んだ。
「遅いですね」
「おねえちゃんとこいっちゃったかな」
「それでも最後はここですから」
マスターはグラスを拭きながら、時計を見て、自信ありげに言った。
0時近くなって待ち人は現れた。
「やあ」
静かに右手をあげたのは、歌舞伎役者の通称・梅さんだった。
「今日はひとりなの」
「うん」
梅さんは信三の隣に座った。
「信ちゃん、久し振りだね」
「ああ。久し振り」
「なんか偉くなったんだって」
「偉くなんかねえよ」
誰が言ったんだ、とばかりに信三はマスターを見た。マスターは知らん顔をした。
- <<前のページ
- 1/4
- 次のページ>>






