- HOME
- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』
- 第2回『LOTUS PLACE』

《1》
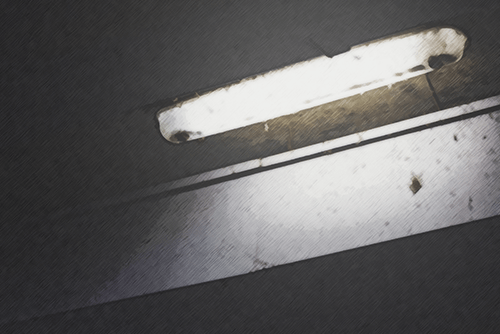
蛍光灯が煌々と照らしていることが、かえってその場所を暗くしている。
22時過ぎのデリー空港は、野犬がのろのろとうろつき、見えない人間が影のように幾人もいるような気がした。
うっすらと、マサラと獣の匂いが漂う。
「はあ、、、もう、やられたなあ」
フォトグラファーのエリカが、ショートカットの頭を振って、やりきれないというふうに黒いカメラバッグのジッパーを勢いよく閉じた。
ライターの友里江は悔しそうにまだ書類を握りしめている。
今しがた、エリカが税関で引っかかった。ライフルを肩に下げ、ベレー帽をかぶった税関の男に「カメラを2台持ち込むなら300ドルよこせ」と言われたのだった。迎えに来ていたコーディネーターのガウリと友里江が必死に交渉し、180ドルにまでは下がったのだが。ガウリは日本に7年留学したことのある29歳。編集者の紹介で、インドにいくなら彼女に任せればよいと言われていた。
彼女はニコニコと黒い瞳で笑った。きゅんとくびれた腰、浅黒い肌と漆黒の髪はどう見てもインド人だが、実に流暢な日本語をしゃべった。
「彼らは理由はなんでもよいのです。まあ、自分のボーナス稼ぎね」
「だって公務員でしょう?軍人?…ひどすぎる言いがかりですよね」
エリカはまだ納得できないという顔だ。
友里江はキャリーバッグのポケットにさっき払ったお金の領収書をねじ込むと、気持ちを切り替えようと、まだぐずぐずしているエリカの肩をぽんと叩いた。
「大丈夫。もしこんなことがあったら請求して、って編集部に言われてるから。郷に入れば郷に従え。しょうがないわよ」
ガウリはニコニコしながら、自分の車に二人を乗せた。
空港の外にも野犬がいた。
車が走りだすと、真っ暗な道路の脇に、裸足で歩く人が見えた。一人で荷物をもつ人。子どもを抱きながら歩く人。ヘッドライトの光が時折、その黒い顔のなかにはっと発光するような目を照らし出す。
「みんなどうして歩いているんですか。こんな遅くに」
友里江がその姿を見送りながら言うと、ガウリは静かに答えた。
「家に帰るんですよ。あの丘を見てください。いくつも家があるでしょう」
彼女が目で指した右手の丘の上には、テントのような、掘建小屋のようなものが並んでいるようだった。
「あんなところに…」
「交通機関はないですから。2時間、3時間、歩いて仕事場に行って、帰るのです」
灯りもなく、ただ息をひそめるようなあの場所に。
友里江はつぶやいた。
「そうまでして帰りたいと思える家があるなんて… 幸せかもしれない」
ガウリはやっぱり答えなかった。
興奮して疲れたのだろう。スースーと、エリカの寝息が聞こえてきた。
- <<前のページ
- 1/4
- 次のページ>>






