- HOME
- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』
- 第6回『横顔だけのクリスマス』
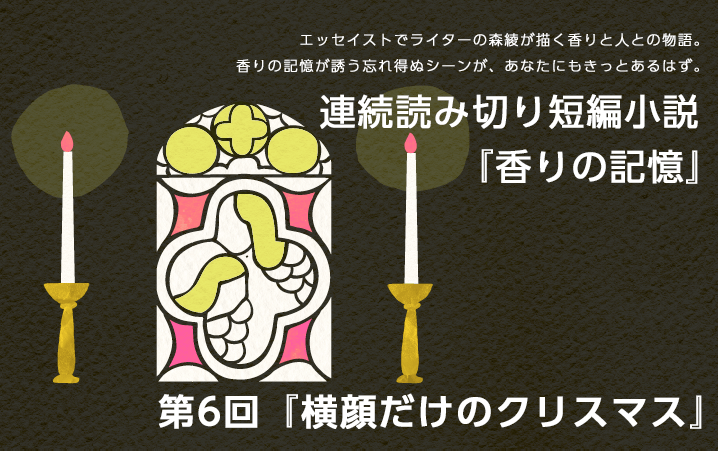
《1》
遮光カーテンの隙間から入る白い光が、テーブルの上に散乱した図面の真ん中に線を引く。
朝の連続テレビ小説が終わった途端に、固定電話が鳴った。
昨夜も4時まで作業していた希子は、ソファの上でうつらうつらしながらそれを見ていた。いや、テレビをつけっぱなしたまま寝てしまっていたというのが正しい。
固定電話にかかってくる用事は、ろくなものがない。
ええと税金は払ったっけ…、保険の引き落としができなかったのかな…と呪文のように頭のなかで繰ってみながら、左の髪をかきあげ、鳴り止まないその子機を肩にはさんで黙らせた。
「もしもし」
「さつき会、36回生のムネハラと申します。サカモトノリコさんですね」
「は…はい」
サカモトは6年間、結婚していたときの苗字だ。希子は2年前に離婚して旧姓のクマダノリコ、に戻ってしまった。しかしさつき会といえば、卒業した中高の同窓会の名前だ。その学校の先輩は99%が良妻賢母のまま一生を終える人たちだ。そんなことが、まるで手品師が小さな箱から旗を引っ張り出すように思い出された。だから説明を省いた。
ムネハラさんは低い声で淡々と話した。
「あの、来週9日の同窓会東京支部のお知らせ、ご存知ですよね。今回、出席が少なくて、ぜひ若い皆さまにもご出席していただこうと思いまして」
「はあ」
「今回は京都からシスター織原と、松田先生と、谷沢神父がお見えになりますの」
「えっ、ヤザワが!… 」
受話器の向こうで、コホ、と咳払いが聞こえたので、希子は「すみません」と小さく付け加えた。
谷沢神父はリーゼントで大きなバイクに乗っている、当時はまだ30そこそこの神父だった。ロック好きの異色の神父を女子生徒たちは「ヤザワ」と呼んで、何かと話題にしたのだった。
希子は思わず口にしていた。
「… 出席します。あの、どこへ行けば」
ムネハラさんは静かに言った。
「会報誌に詳細が載っていたかと思いますが…。もうお手元にはございませんの… 」
どうして卒業しても、先輩は怖いのだろう。
そういう人たちがずらっといるのだろう。けれども卒業以来会っていない谷沢神父を思い出すと、希子はその銀座の老舗のレストランで行われるそのランチ会が、ちょっと楽しみになった。
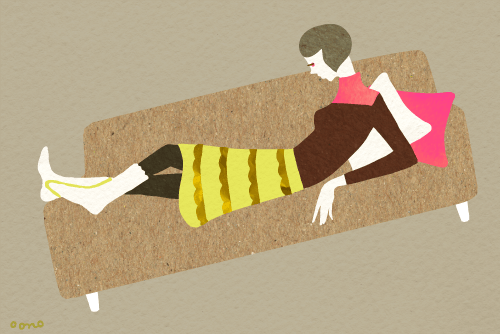
- <<前のページ
- 1/4
- 次のページ>>






