- HOME
- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』
- 第8回『砂糖菓子のリボン』
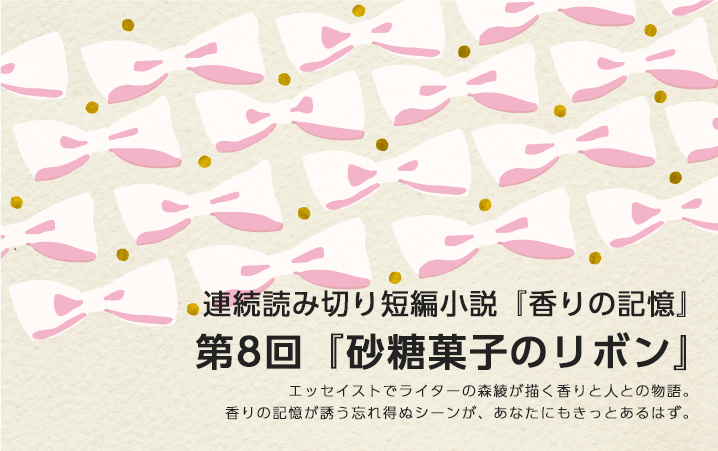
《1》
直行便でも、パリまで13時間もかかる。
婚約者に会いにいくというのに、香苗はさほどウキウキしていなかった。
大学を卒業するまで3年間付き合っていた彼氏と別れ、卒業して商社に就職して2年と数ヶ月。見合いをしたのはつい半年ほど前のことだった。医者と結婚してほしいという親の勧めで見つかった相手は、ひと回りも年が離れた脳外科医だった。
彼はほどなくフランスの病院に就職が決まっていて、見合いのときから「そちらに住むこと」が条件だった。仏文科だった香苗の友達はこぞって羨ましがった。
「いいなあ。いきなりパリで新婚生活なんて。アパルトマン、ってところに住むの?16区?いやだ、高級住宅地だよ。当然かあ、外科医の嫁だもんね」
でも一番仲のよかった尚代だけは、香苗の気持ちをどこかでわかっているようだった。結婚することになったと告げたとき、一度だけ、本当に一度だけ、という感じで、こう聞いた。
「だいじょぶ? 本当にもういいの、川邊くんのこと」
「… うん。海外に住むって聞いて、だったら吹っ切れるかなと思って」
香苗はつとめて明るく言った。尚代はそれ以上何も言わなかった。が、電話の向こうで心配げに苦笑する様子が、香苗にはわかった。
3月終わりの飛行機は空いているのではないかと思われたが、それなりに乗客がいた。
2人掛けの席の窓際で香苗が座席の下に茶色い大きなエルベシャプリエをねじ込もうとしたとき、長身の頭に小さなサングラスを乗せた20代の男性が隣の席にやってきた。自分の荷物をひょいと棚にあげ、香苗の足元の荷物を見るとごく自然に声をかけた。
「それ、上にあげます?」
「あ、はい」
その自然さにつられて香苗は返事をしてしまった。男性は香苗のバッグをやっぱり軽々と棚にあげ、からし色のフード付きのコートを脱ぐと、それも棚にあげて、席に座った。180センチ以上は優にあるだろう、と香苗は思った。身体を折りたたむように座ったエコノミーの席は、彼には狭すぎた。卵色のセーターの広い肩は、どうしようもなく香苗のミルク色のセーターと重なった。
しばらくすると、CAが飲み物を配りだし、やがて菓子パンを運んできた。
「クリームパンはありますか」
「申し訳ございません。あいにくジャムパンしかございません」
「あ…じゃ、結構です」
香苗は子どもの頃からジャムパンのジャムが嫌いだった。そんなことを思い出しながら、少しうとうと眠ってしまった。

- <<前のページ
- 1/4
- 次のページ>>






