- HOME
- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』
- 第10回『雨音演奏会』
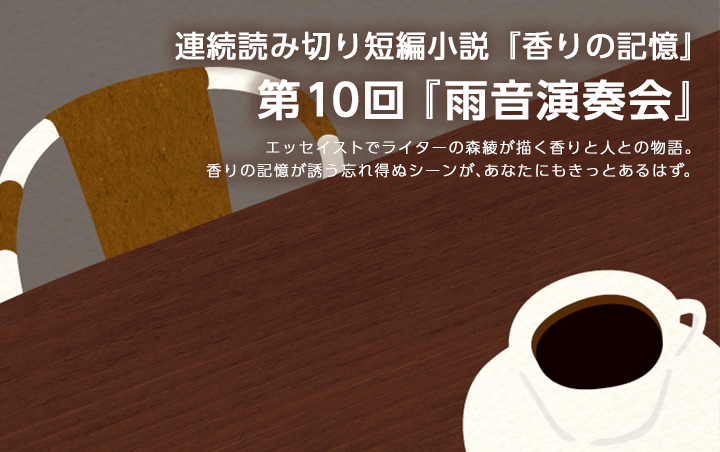
《1》
小さな店には珈琲を焙る匂いが立ち込めていた。
窓際の細いカウンターの上に、4台の古めかしい焙煎機が並んでいる。
それは、丸い穴が無数に空いた鉄製の円筒で、カセットコンロの火の上20センチくらいのところに横たわり、くるくると回る仕組みになっている。
そのうちの1台のなかの珈琲豆は、頃合いよく焙られ、はぜ出してパチパチと音を立て始めた。そのかすかな音を聞きつけると、大柄な店主は猟師が獲物を落としたときのように素早くそばへ行き、豆の粒ひとつひとつの様子を確かめるように凝視して、円筒を外して四角いざるにざーっと豆をあけた。
そして、彼は今度はざるを両手でもち、鍋のように振っている。
店にたったひとつある丸いテーブル席で、さっきからそれをじっと見入っていた木崎則雄は、店中に漂う珈琲豆の香りを深く吸い込みながら聞いた。
「それは冷ましているんですか」
「それもありますけど、見えますか、この細かい天使の髪の毛のような銀の殻…これが雑味になるので、なるべく取りたいんですよ」
「ほう」
木崎が目を凝らしてみると、小さな短い糸状のものがふわふわ、きらきらと宙を舞っていた。
「繊細なものなんですねえ」
「はい」
珈琲豆の焙煎を待つ間、珈琲が一杯サービスされる。その20〜30分ほどの時間は、休日の木崎にとって至福の時間だった。
ひと口飲んで、ガラスドアの外のほうを見る。いつもと変わらないアスファルトの道路にぽつぽつ、ぽつぽつと水玉模様が出来始めた。
「降ってきたみたいですね」
「傘、ありますよ。でも通り雨かもしれないですから、ゆっくりしていってください」
「ありがとうございます」
高輪の住宅街の坂道の上に、その店はあった。日曜日でもそんなに人通りはなく、近所に住む人たちが大きなイヌを散歩させているくらいだ。
木崎は、今日は家にいたくなかったのだった。
先週、勤めているレコード会社で辞令が出て、彼のいる宣伝第二部は宣伝第一部と統合されることになった。来週からは、52歳の彼は部長職をはずされ、35歳の部長のもとで働かなければならなかった。給料は8割になる。そのことをまだ、妻には言えずにいた。
いや、わかってくれない女ではない。でも、なかなか言えずにいた。娘の音絵はまだ高校生。これから、進学だ。
木崎は思う。バブル時代は金も使えたが体も酷使して働いてきた。あの頃の仲間たちはもうこの業界を離れたり、故郷へ帰ったりした。CDも売れなくなったこの時代に、自分はまだ、二つ目のレコード会社に残っているだけでもラッキーだ。
それに今更、いったい他になんの仕事ができるだろうか。
給料が8割になるなんてまだマシなのだ。
…しかしそのことを、家族はどのくらい理解してくれるだろうか。彼にはうまく話す自信がなかった。
ふと目を店の壁の片隅に向けると、そこに「蓄音機の会 第3日曜20時」という貼り紙があった。
「ご主人、蓄音機の会ってなんですか」
「ああ、ここでやってるんですよ。私の唯一の趣味でね。今夜なんです。よかったらいらっしゃいませんか」
「へえ。SP盤かな」
「ええ。本当にそこで演奏しているような音がするんですよ」
店主は豆を静かに袋に注ぎ込みながら言った。
木崎は、自分がレコード会社に勤めているということは言えなかった。もはや絶滅しそうなアナログ音源と、今の自分はどこか似ているのではないかと、ドキリとしたのだ。
レコード、CD、今やデータ音源。音楽が手に触れる形ではなくなってしまったように、自分の役目も変わろうとしている。だからこそ、今、無性にその最初の形を見てみたい、聴いてみたい気持ちが湧いてきた。
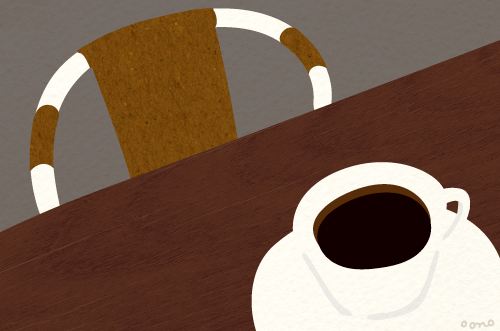
- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






