- HOME
- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』
- 第11回『笑い屋・かす子』

《1》
新社屋になってから、この放送局全体に煙草や汗の匂いが消えた。
朝、局員は通用口から出勤する。
ピッ。
局員カードを当てると、電車の改札のように羽が開いた。
おはようございます、と、髪をかきあげて橘麻子が言うと、警備員は敬礼した。のろのろと、エレベーターで10階へ上がる。いつもより、肩にかけたバッグも重く、エレベーターも遅く感じる。
ピッ。
入室するにも、その儀式が必要だ。いつものように入っていくが、テレビ制作部の午前中のデスクには社員は少ない。週末の深夜番組班だった麻子には無縁の時間帯だ。
「おはようございます」
東田制作部長はすでにガラスのパーテーションで仕切られた自分のミーティングルームにいた。そして彼女を見つけるなり、その顔を見ずに右手を挙げて手招きした。
「おはよう。まあ、もう短刀直入に話そう。わかってはいるとは思うんやけどな。下谷くんの話や」
麻子はどさりと肩からヴィトンのトートを隣の椅子に落として、座った。そして東田のでっぷりしたおなかの前ではじけそうなワイシャツのボタンを見ていた。
とても彼の目を見ることなどできなかったのだ。
「君と下谷くんが個人的に付き合いがあったのは有名や。そやけど、まさかもう、つきおうとらへんのやろ。… 制作費持ち逃げしてドロン、やもんな。… どこ行きよったんや、ほんまに」
「…」
麻子は瞬きをするのも忘れていた。本当になんということだろう。なんちゅうやっちゃ、あのアホは。… 麻子は心のなかでそう叫んでいた。いや、ここ数日、何度叫んだかわからなかった。
下谷一夫は小さな制作会社の社長だった。週末の夜中のローカル番組を作っていた。そこにマスコット・ガールとして出ている20歳そこそこの女のコの一人と恋仲になり、制作費を持ち逃げして行方をくらましたのである。
しかもその番組の担当ディレクターだった麻子は、下谷と結婚を前提につい最近まで付き合っていた…はずだった。しかも3年も。
「本当にすみません」
麻子はそれだけ言うのがやっとで、また鉛のように固まった表情になった。
東田は右手の親指と人差し指であご髭をさすりながら、気の毒そうに言った。
「いや人間やからな。いろいろある。君かて20年も、仕事メインで頑張ってきたんや…」
「18年です」
「あ、そやったな。失礼。そやけど、アナウンサーから制作へ移っても、君ほど戦力になった女性はおらんわな。それはみんなわかってる。そやけどな、まあ、今回ばかりはちょっとなあ。僕も庇いきれんところがある。同じ待遇、ちゅうわけにもいかん。そやけど、君はディレクターとして優秀や。制作になんとか残ってほしい。… そこでや。お笑い班で一から勉強してみいひんか」
「お笑い、ですか」
麻子は意外な提案に心の底で30%だけ喜んだ。絶対に営業か、子会社出向あたりだろうと読んでいたからだった。40歳を前にして、まったくやったことのない仕事を一から覚えるのは大変なことだ。
まだ制作に残れるなら御の字だ。
しかしこじゃれた深夜の情報番組を続けてきた彼女にとっては、ベタなお笑い番組は未知の世界であることも事実だった。
「ありがとうございます。勉強させてもらいます」
そう言って、小さく頭を下げた。
東田は黒縁のメガネをはずし、はげたグレーのハンカチで拭きながら、言った。
「とりあえず『爆笑とまらん寄席』のフロアからやってみて」
フロア! 麻子は心の中で突っ込んだ。しかし、声は冷静に出した。
「公録のやつですよね。フロアって、すぐにできるんでしょうか」
「今まで中瀬さんが自分で全部やっとったんや。まあ、すぐ慣れるわ」
「はい」
中瀬プロデューサーというのは、年中「忙し忙し」と言うのが癖の、小柄で汗っかきの50代の男性だった。いつも襟が黄ばんだ白いシャツを着ていて、独身だとか、奥さんに逃げられたとか言う噂もあるが、とにかく席にじっとしていたためしがなく、誰も確認したことがなかった。
麻子が付き合っていた下谷のようなスタイリッシュな男とはまるで別の生き物かと思えるほど、違うタイプだった。
東田はスマホを手にして立ち上がると、小部屋の戸をあけて振り返り、眉をひそめた顔のままの麻子に言った。
「泣きなや。笑う門には福来る、やで」。
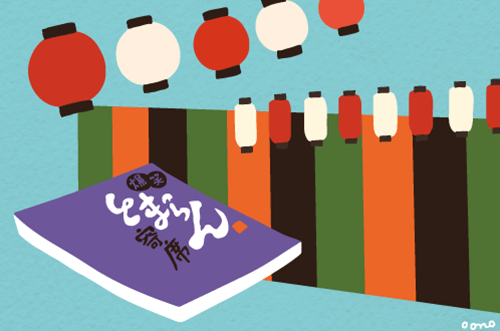
- <<前のページ
- 1/4
- 次のページ>>






