- HOME
- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」
- 第64回:林哲司さん(作曲家)

中森明菜さんが歌った『北ウィング』、上田正樹さんが歌った『悲しい色やね』、杏里さんが歌った『悲しみがとまらない』…。80年代に歌謡曲に洋楽テイストのポップな楽曲を発表した作曲家の林哲司さん。その楽曲は今も歌い継がれ、また新たな作品も次々と生み出されています。シンガーソングライターとしてのスタートから今日まで、ヒットメーカーの林さんの視点を追いました。
《1》アイドルの時代を塗り替えた、林哲司のニューミュージック
上質なブルーパープルのツィードのスーツで現れた林哲司さんは、ダンディでお洒落な佇まい。さすがに時代の最先端を走る曲を作り出してきた人という雰囲気です。
林さんの音楽人生は、1973年、シンガーソングライターとして始まりました。
「当時、まだヤマハが海外への楽器プロモーション戦略として『世界音楽祭』というのをやっていたのです。ポプコン以前の話ですね。‘72年にそのチリ大会に出場したのがプロへの道の入り口になりました」
その後、まず海外でその作曲センスが評価されることとなります。UKのポップロックグループ、ジグソーに提供した「If I have to go away」が全米チャート、UKチャートにのぼり、ヒットを記録したのです。
「たまたまそうなっただけで、その後、すぐに日本で活動するようになりました」
竹内まりやの『September』、杉山清貴とオメガトライブの『ふたりの夏物語』など全シングル、稲垣潤一の『思い出のビーチクラブ』。…林さんの曲はニューミュージックと呼ばれた当時のJ POPシーンを牽引するものとなっていったのでした。
やがて中森明菜さんが歌った『北ウィング』が大ヒット。その後、菊池桃子、原田知世らへの楽曲提供も始まります。林さんはアイドルの時代も塗り替えました。
「私は彼女たちにアイドルの曲を提供したという気持ちはないのです。洋楽と遜色ないポップス、ニューミュージックを提供したという感覚だった。それがそれまでの時代のいわゆる青春歌謡とは一線を画したのだと思います」
最近、林さん自らがプロデュースして歌ったりもするSONGFILEのライブで、それを再び実感すると言います。
「たとえば原田知世さんが歌っていた『天国に一番近い島』といった曲は、彼女のあどけない声がもちろんよかったのですが、その若さではないシンガーが歌っても、客観的に楽曲として成立しているなあと感じるのです」
2019年は作曲家活動45周年を迎え、SONGFILEライブを各地で開催しました。
「楽器運んでステージに立って。楽しかったですが疲れましたよ(笑)。一旦、ゼロに戻してこれからのことは考えます。皆さんが歌ってくださるヒット曲は私の作った楽曲のうちの1%です。つまり過去につくった大半の曲が、その時代で流れてしまったりしているので、もう1回、その1%とともに織り交ぜて聴いてもらえたらいいなあと思っています」
ヒットしたかどうかに関わらず、おそらく林さんにとっては1曲1曲が同じく息を吹き込んだ絵のようなものなのでしょう。

《2》朝を真新しく始めるためにも香りが必要
ものを作るのは考えることを積み重ねる大変な作業です。林さんは毎朝、自分を真新しい状態にできる香りをもっているそう。
「タオルミーナというシチリアのレモンの香りをスプレーで使っています。映画『ディープブルー』の舞台になった島でしか売っていないもので、とても爽やかな香りなのです。夜は、南仏のエクスプロバンスで買ってきたラベンダーのエッセンシャルオイルを、セラミックに垂らしています。北海道の富良野でも買ったことがありますが、同じラベンダーでも香りが違うのが興味深いですね」
ご自身でも20歳の頃に贈られたGIVERNCYの「ムッシュ・ドゥ・ジバンシィ」をずっと愛用しておられるそう。今は廃盤になり、gentlemanという名称のものが近いそうです。年を重ね、紳士になられた林さんにぴったりです。
「香りは気分を変えてくれる大事な要素です。考える仕事なので、イメージやモチベーションをリフレッシュするのはとても大切です。年齢を重ねると、いろいろ辛いこともあるので、自分で触発しないとね。朝を爽やかに始めることは日常のなかでとても重要ですね」。
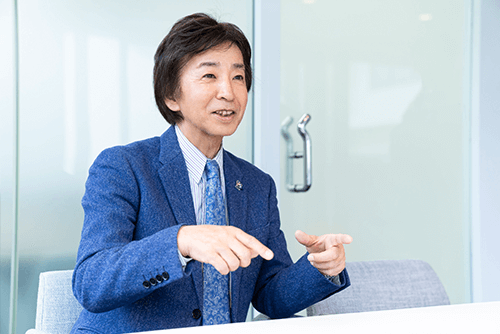
- <<前のページ
- 1/2
- 次のページ>>






