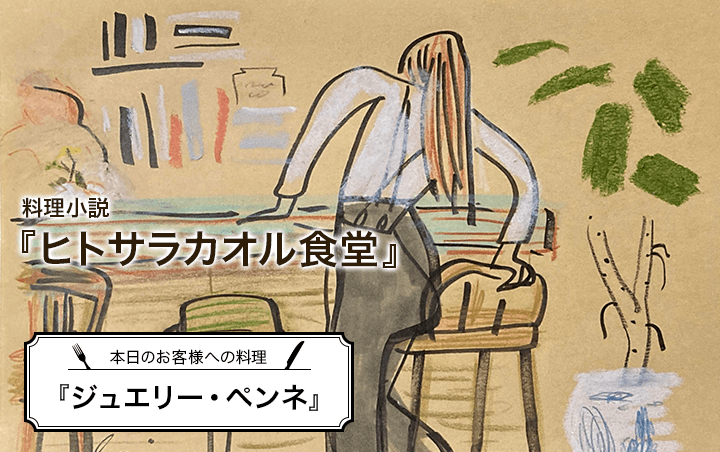
🥂1glass
褪せたデニムの色のようなブルーの夕暮は、輪郭がない。風に乗った汽笛が、ボーッとそれを音にして聴かせてくれた。
元町中華街の駅山手の方へと、続いている、一番なだらかな坂が代官坂だ。
地元の人はその坂を平坦だと言う。確かに脇道から山へとそそり立つような急な坂に、階段があったりするのだから、仕方あるまい。
その坂の入り口あたりに「ヒトサラカオル」と書かれた小さな看板がある。
古材の板切れに白いアクリル絵の具だろうか、あまり綺麗とは言えない字で書いてある。
入り口の脇は、ガラス窓になっていて、なかが伺えた。
手前に6人ほど座れるバーカウンターがあり、奥に2つだけ椅子のある少し低いカウンターがある。
どちらのカウンターも、古材に色を塗ってあるのか、薄いペパーミントグリーンのような色で、茶色の汚しワックスがかかっているようだった。
奥には簡単な厨房。カウンターの背後には、バーによくあるようにボトルが並んでいたりはせず、作り付けた小さな書棚に本と、紅茶の缶が並んでいた。
一見、カフェなのかバーなのか、わからない。はたまた窓からは、何か人の部屋を覗くような風情すらある。
立ち働くのは、40代終わりか、50代だろうか、女性がひとり。
肩に届くかどうかの髪はグレーのカシミアのカチューシャで束ね、この日はミルク色のニットに、チャコールグレーのゆったりしたパンツ。腰から下は白いギャルソンエプロンだ。
黒目がちの目が笑っているような泣いているような不思議な形で、こっちを見た。
「いらっしゃいませ」
1月1日午後5時を過ぎた頃。
その若い女性客は、扉を開けておいて、迷い込んだような顔をしていた。
「あの、ここバーですか」
「バーでもいいし、カフェでもいいし、おなかが空いていたら何か作りますし。メニューご覧になりますか」
若い女性客はちょっと迷った顔をしたが、はい、と答えて、白いダウンコートを脱いだ。それをフックにかけると、入り口に近いバーカウンターに座った。
白いタートルのニットに、サスペンダーのついた黒いパンツを履いている。紙袋に破魔矢が刺さっていて、どうやらどこかへ初詣に行ってきたようだ。
「あけましておめでとうございます。モリタと申します。よろしくお願いします」
オーナーの女性が両手をエプロンの前に重ねて、お辞儀した。
「おめでとうございます。…モリタさん…」
「はい、私は盛田幸と申します。モリママ、って呼ばれています」
そう言って、にっこり笑った。その感じが悪くなくて、なんとなく、若い女性も心ほどけた。育ちの良い性格なのだろうか。客は名乗らないことも多いが、素直にすぐに答えた。
「私、矢作凛花っていいます。このお店、最近ですよね。私、ちょっと坂の方に住んでいて。まあ、親の家なんですけど」
山手のお嬢様か、と盛田幸は察した。確かに品の良さはある。ただ自己主張の強さというか、
何かそういうお嬢様の一部の人にありがちな、ちょっと籠から出たい感がある人だなという気もした。伸ばした羽が籠に引っかかるのである。
客はメニューに目を落とした。
飲み物は。。。クラフトビール、カヴァ、シャンパン、グラスワイン、シードル、ウィスキー、ジン、紹興酒、自家製梅酒…コーヒー、紅茶、ジンジャエール、トマトジュース、レッドオレンジジュース、スパークリングウォーター。
食べ物は、酒の肴、野菜料理、肉料理、麺類、ご飯…おたずねください、と書いてあるだけだ。
「とりあえず、グラスワインの白をください」
「今日はお正月だから、一杯振る舞い酒をします。シャンパンです。モエのディフュージョンだけど。2杯目からは1000円ね」
「わ、ありがとうございます」
「乾杯」
幸は自分もグラスを手に取った。
客はごくり、と飲んだ。
「美味しい。冬って、意外と喉乾きますよね」
「そうね、冬に脱水症状になる人もいるそうだから」
「そうなんですか」
客はその話は聞いていないようだった。一瞬、笑顔になりかけたが、やはり心は違う場所にあるようで、どこか暗い面持ちだった。
どちらかといえば美人である。面倒見の良さそうなほっぺたと唇をしている。ほっぺたと唇がふくよかな女性は、大体面倒見が良いのだ。幸は長い客商売の経験で、顔相学の先生でもないのに、そんなことを思った。くりっと大きな目も、人懐っこい。
話しかけても良さそうだと思った。
「初詣ですか。どちらへ」
「赤坂まで行ってきたんです。氷川神社、ってわかります」
「私、コロナ前までは赤坂で店やってたんですよ」
「ええっ、そうなんですか」
「氷川神社、お参りしてました」
「えーっ」
こういう時、幸はちょっと神仏を信用する気持ちになる。何か、目に見えない縁というものを目に見えない神様が繋いでくれているんじゃないかと。
長いこと客商売をしてきて、いろいろあったけれど、なぜだか今、横浜にいるけれど、それもこれも、目に見えない神様の差配なのだと思えてくるのである。
凛花は、本当に不思議そうに、グラスの泡と幸の顔を見比べて言った。
「盛田さん… モリママ…。なんで横浜来ちゃったんですか。赤坂の方がお客さん、いそうなのに」
幸はうっすら微笑んで言った。
「もうたくさんのお客さんは、いらないんです。本当に会いたいと思って来てくださる方がいたらいいの」
「へえ。誰かを待ってるんですか」
「いや、そういうことじゃなくて」
幸はひとくちシャンパンを飲むと、ちょっと会釈して、奥へ行き、小皿をもって来た。
「これは、つきだし」
凛花は、小さなアンティークの緑の小皿の上の、薄いクッキーのようなものを口にした。
ひとくち食べると、塩味の効いた薄いバタークッキーにはトリュフの粒が弾ける香りが広がった。
「美味しい。シャンパンに合う」
思わず口にすると、凛花はこの店に来て初めて少し笑顔になった。またひと口、ふた口と、シャンパンも進む。
幸は嬉しくなった。美味しいものを美味しいとわかってくれる人が好きだ。そういうものに素直に反応できる人とは、仲良くなれそうな気がする。
思わず、なんとなく聞いてしまった。
「山手のお嬢さんが、なんで赤坂の神社へ? なんかご利益があるのかしら」
すると彼女は、もういいや、という風に話し始めた。
「あのね、本当はね、今日、初詣、彼氏と行くはずだったんですよ。でも、あの人、私の親友と付き合ってて。二股かけられてたんです。その友達も、言ってくれたらいいのに、何にも言わないんだもの」
そう言うと、残りのシャンパンをごくごくっと飲んでしまった。
幸は何も言わずに、そのグラスにまだ半分くらいシャンパンを注いだ。
「これは私のおごり。まあ今日は、飲みましょう」
そう言うと、自分のグラスにもシャンパンを注いだ。
新年早々、儲からない日になりそうだ。
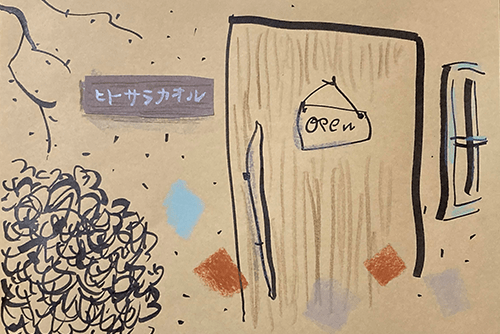
- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






