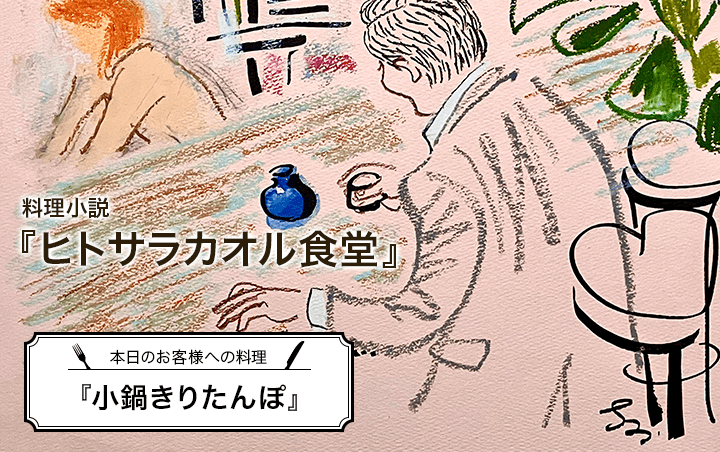
海はなぜ凍らないのだろう。冷たい風を全面に受けながら、それでもまだ鈍色の波が動いている。
盛田幸は海岸通りのマンションの6階に住んでいる。ここを借りるとき、自分と同じ50代と思しき不動産屋の女性が言った。何度か通ううちに津田典子、という名刺をもらっていた。津田さんは言った。
「海見えの物件、なかなか出ないんですよ。ま、ちょっと不思議な間取りなんだけど」
ちょうど5畳ほどのキッチンがあるほかは、26畳、スタジオのように何もない一部屋なのである。マスクをしたままの2人は、頭をくっつけるように見取り図を覗き込んだ。津田さんはトントン、と人差し指でそれを叩いた。
「なかなか、ここを借りたい人ってライフスタイルが見えないじゃないですか。2人で住むにしたって、あまりにもお互いプライベートがないでしょう」
「確かに、海が見たい一人暮らしで、ま、ちょっとお客さんが来たら喜ぶかも、みたいな」
幸はつぶやいた。もしも大阪から、店にいた女の子たちが来たら喜ぶかな。ま、いつ来るか知らんけど。
そうやって、決めたのが2年前の夏だった。そのときは、横浜ってあったかいんじゃないかと勝手に想像していた。
しかしどうだろう。今日のこの寒さは。
「さぶー」
二重カーテンの隙間から、硝子にぶち当たる風を見るともなく見る。そして、こういう時にはなぜか大阪弁が口をついた。
その時、スマホのInstagramにメッセージが届いた。
ー 明後日、父が行くと思います。なんか食べさせてやってください 凛花
この間の、傷心女子からか。しかし嬉しい話である。
ー お父さんは、何が好きかしら
ー 父は秋田出身なんです。歯医者やってるんですけど。
ー へーえ。
幸はちょっと驚いた。山手に秋田の人が住んでいるなんて。歯医者になって、大成功したんだろうか。
翌日、幸は有楽町の秋田物産館へ出かけて行った。
🥂1glass
あんまり寒いので、バーでは熱燗とホットワインも出すことにした。看板の隣に「熱燗、ホットワインあります」と、貼り紙をし、写真を撮ってInstagramに上げてみた。コメント欄には「今日のテーマは秋田です。秋田のもの、ちょっとあります」と、控えめに書いた。
凛花の父親らしき男は、8時半ごろ現れた。
上背があり、グレーのやや薄い髪をきちんと七三に分けている。グレーのスーツにライナーのついたステンカラーのコート、襟元には燕脂色のカシミアの襟巻きが覗いている。
「いらっしゃいませ。お飲み物はいかがなさいますか」
「ウィスキーのお湯割りでももらおうおかな」
「あんまりいろいろないんですが、シーバスかバランタインあたりで良いですか」
「じゃ、シーバスで」
グラスの横に、クリームチーズといぶりがっこの冷たいクッキーです、と、小さな皿を置いた。
紳士は小さなフォークでそれを口に運び、嬉しそうに笑った。
「凛花が、お世話になったそうで」
「あ、やっぱり、凛花ちゃんのお父さまでしたか」
「はい、矢作です」
幸は恐る恐る尋ねてみた。
「秋田のお生まれだと伺いました」
「まあ。もう40数年、こっちだからね。大学から東京で、医者になって、養子に入ったんですよ」
「へえ」
魔法にかかったように、何も訊ねていないのに、客が話し始める。いつからそんなふうになったのだろう。いやもともと、幸にはそういう素養があったのかもしれない。
紳士は訥々と語り始めた。
「まだ院生の時に結婚してね。この間の週末で40年だったんだ。ルビー婚とか言うらしい」
「おめでとうございます。じゃあ、ルビーを贈られたんですか」
「なんか勝手に買ってた。そこのフレンチで家族で祝ったよ」
「なんてお幸せな」
「凛花が彼氏を連れてくるとか言ってたんだけど、ダメだったらしいね」
矢作は我が事のように肩を落とした。
幸は伏せ目がちに言った。
「いいんですよ。凛花ちゃん美人だもの。まだいい人がいくらでもいますよ」
「でもあいつも35だからねえ」
「えっ、そんなに!? …あ、いえ、失礼しました。お若く見えたので」
矢作はクスッと笑って言った。
「ママ、正直な人だね」。
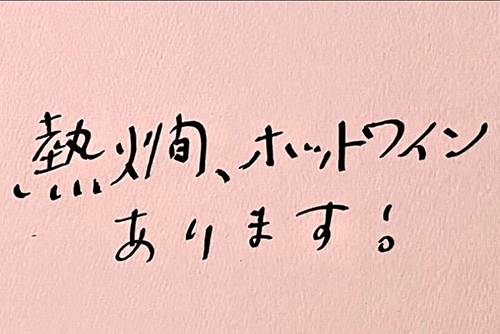
- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






