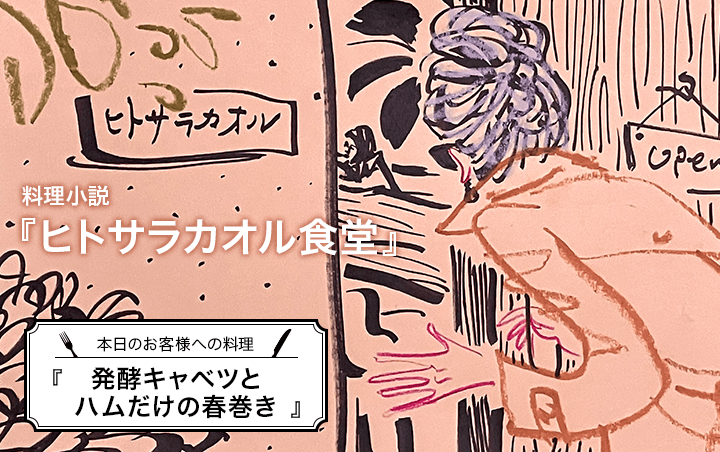
生暖かい空気が、屋上を覆っている。
地上5階という中途半端な場所からは、向かいのビルに縦についているネオンサインが間近に見えた。
「ミツコさん、ダメです。お願い。生きて」
伸ばした両手で細い手首を掴んでいる。手首は自分より冷たい。無理。もう無理。私も落ちてしまう。
そう思ったとき、誰かが自分の腰を後ろからぐいっと引き上げてくれた。幸はその細い手首を離さず、3人は屋上に反対側のドミノ倒しのようになって寝転がっていた。
ミツコの頭が自分の股の間にある。
「ああ、よかった」
そう思った途端、ミツコは消えてしまった。
「あれ、ミツコさん」
振り向くと、自分の腰を引き上げてくれたはずの男の影もない。
「あれ、パグ? ミツコさん?……」
ー そこでハッと、盛田幸は目を覚ました。ゆっくりと、体を起こす。喉が乾いている。両手を見る。自分の手を握りしめていたのだろう。手のひらの下の方に爪の跡がついていた。
何年かに一度、その夢を見る。自分にとっても、後の二人にとっても、おそらく命に関わる瞬間だった。ミツコもパグも、今もその時のことを夢に見るんだろうか。
あの時。
ミツコはいれあげた竹内という男に裏切られ、その男の妻と一緒に店に乗り込まれて恥をかかされ、衝動的にビルの屋上から飛び降りようとした。18歳の幸とボーイのパグが、彼女を助けたのだった。
その後、No.1ホステスだったミツコは店を辞め、しばらくしてまたスポンサーを得て「マダム・ミツコ」を開店した。
幸にとって、ミツコは絶対に自分にはなれない憧れの存在だった。細く長い首にまとわる金茶色の巻き髪、左手の中指と薬指の間に挟む細いミントの煙草。キュッとくびれた腰、長い脚に8センチのハイヒール。低く響く声。そして、居場所に鮮やかなほど残り香を残す、ミツコと同じ名前のあの香水の香り。
たとえ意地悪をされようが、嫌味を言われようが、前を歩くミツコという形を失うことは考えられなかった。
それからそれから。いろんなことがあった。
どんなことがあっても、幸はミツコのことをどこかで姉のように思っていた。
ベッドからゆっくり起き上がった幸は、食器棚から適当なグラスを出し、常温のミネラルウォーターを注いで、ひと口飲んだ。
落ち着くと、小さな独り言が溢れた。
「ミツコさん、今、どないしてはるんかなあ」
最後に会ったのは、幸が大阪の北新地の店を人に任せた頃のことだった。
ということは、20年は会っていない事になる。
「20年か」
呟いた途端、港の方から、ぼおー、っという汽笛が聞こえた。
ここは横浜だった。
🥂Glass 1
翌朝、幸は大きな瓶を抱えて、家を出た。
瓶のなかには、井澤由美子という人の本で読んだ「乳酸キャベツ」が入っていた。キャペツを塩ときび糖で発酵させたものだ。
ジッパーのある袋で一度発酵させてから、冷蔵庫に入れる前に唐辛子と昆布を少し入れるのが幸の好みだった。
すっかり暖かくなった海風に押されるように歩く。商店街も緑や黄色やターコイズブルーといった明るい色の服やバッグが並んでいる。
通り過ぎる人たちの中には「この人、何を抱えているんだろう」と、幸の胸元を覗き込む人もいた。
幸はまるで赤ちゃんのように、大事に瓶を抱えて歩いた。なぜかその姿勢は安心できた。赤ちゃんを産んだことはないけれど、きっと何かを抱いて歩くのは、自分も癒やされるのかもしれない。
店に入ると、瓶を冷蔵庫に入れた。今日はブルーのハリのあるシャツに、けし粒パールのネックレスをしている。白いエプロンの紐を前で締めると、小さな気合が入った。
少し拭き掃除をして、簡単な仕込みをする。今日は「乳酸キャベツ」があるから、そのバリエーションで行こう。お酒を飲む人のアテには、肉の大木のソーセージやコンビーフも買ってある。
5時を過ぎた頃、近所に住む凛花がぴょこん、と顔を出した。しっかり化粧をしてきたばかりという感じだ。
「もりママ、こんにちは」
「あら、おめかしして、これからお出かけかな」
「今からコンサートなんです。また帰りに寄るかも。今日、なんかあります?」
「一応、食堂、って書いちゃってるからね」
幸はくすくす笑った。
「ですよねえ! じゃ後で!」
元気に出かけていった。凛花は元気になったし、前よりも化粧が上手くなって、大人っぽくなったような気がする。
「いってらっしゃい。楽しんでね」
凛花を送り出すと、なんだか気持ちに春が吹き込んだような気がした。若い女性にはそんな力がある。
入れ違いに、こちらを覗き込むような老女が現れた。
シルバーの髪を無造作に高く結い上げ、トレンチコートと白シャツの襟を立てている。胸元には大粒のブラックパールが上品に鈍く輝いていた。
サングラスを取ると、赤いルージュがにっこりと笑った。
「幸ちゃん、元気そうね」
「えーっ」
幸は心臓が止まりそうになった。その笑顔は紛れもなくミツコだった。
誇り高い空気感。洒落た着こなし。しかし、違うのは、髪の色、やつれた首筋、足元のスニーカー。そして、あのミツコの香りがしなかった。
「ミツコさん。よく来てくださいました。大阪から?」
ミツコのトレンチコートを預かりながら、嬉しくてドキドキしている自分に、幸は驚いていた。
今朝方の夢はこの来訪を知らせてくれたのだろうか。
「私、今ね、熱海にいるんよ」
「えっ、熱海」
「うん。憶えてるかな。大パパにな、熱海のリゾートマンションをもろてね」
大パパ。誰だっけ。幸は思い巡らした。そういえば竹内と別れて、彼女はニューヨークにいったりしていた。
「ニューヨークに一緒に行かはった方ですか」
「ううん。その次の次」
「さすがミツコさん」
「せやろ」
二人は顔を見合わせて「あはは」と笑った。
「乾杯」
「かんぱーい」
二人はシャンパングラスを傾けた。このシャンパンは、やはり奢るべきだろうと幸は思った。
ボーモン・デ・クレイエール。薔薇の花のアイコンがあるこのシャンパンは、最近よく使う一本だ。
「ああ。後味がスッキリして美味しい。でも私、もうあんまり飲まれへんねん」
ミツコはそう言って、俯き加減に微笑んだ。
- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






