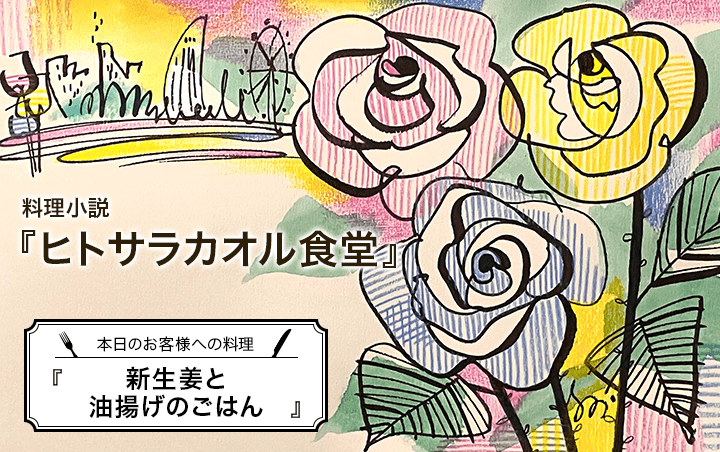
5月になっても、寒かったり、急に暑くなったりと寒暖差の激しい年だ。
それでも新緑は生き生きと輝き、コロナ禍が収束してマスク不要となった人間たちに微笑みを投げかけていた。
横浜元町は、あちこちにいろんな薔薇も咲く。顔を近づけなければわからないけれど、その香りは空気のどこかにひそんでいて、街に華やぎをくれていた。
連休が明け、もりママこと盛田幸には一つ待ち遠しいことがあった。
北新地で店をしていたときの店の女の子… いや、年齢は彼女たちの方がやや年上で今や「アラカン」のはずだが… ケイとヒトミが、揃って横浜へやって来るというのだ。
小柄で地味な顔立ちだが思慮深かったケイはその後、昼間に習っていたフラワーアレンジメントの先生になり、独身のまま、花屋もしながら教えていた。北新地で出会った社長さんたちの名前がリストにあり、イベント毎に花を出すなど、うまくいっているようだ。
大柄で目と目の間が少し離れたおおらかな性格のヒトミは、その後介護士の資格を取り、特別養護老人ホームを経営する社長と結婚して、裕福ながらも忙しく経営に携わっていた。
二人は新幹線の二人がけに並んで座り、水了軒の八角弁当を食べながら横浜へ向かっていた。
「もりママ、今、どんな感じになってるやろな。ものすごいべっぴんさん、って言うほどやないけど、色気っていうか、若うても迫力あったよな」
ヒトミが真ん中のだし巻きをつつきながら言うと、ケイは端っこのにんじんから静かに口に入れて言った。
「うん、目力あったしな。私らより3つくらい歳下やし、あの頃、まだ23ぐらいやで。真奈美ママが亡くなって、そのとき同時ぐらいにあの男の裏切りが発覚して、東京から大阪へまた戻ってきて。めそめそしてたらあかん、ママの代わりになって店をちゃんとしてかなあかん、と、もう必死やったんやろうな。… いろいろあったな」
ヒトミは「いろいろ」のなかに自分の話も出てきては困ると、話を遮った。
「それはそうと…。今晩は中華街やろ。もりママ、店は休んでくれたんかな」
「月曜定休やて。言うてたやん」
「せやった。どんなところなんやろなあ。名古屋から先は海外みたいな気ぃするわ」
「私も」
「だいたい関東弁なんかな」
「〜じゃん、て言うらしいで」
「そうじゃん。いけてるじゃん、みたいな」
「わかってるじゃん」
ふたりは「〜じゃん」を、富士山が見えるまでにはほぼマスターしていた。
🥂Glass 1
元町中華街駅の元町側で、3人は10数年ぶりに再会した。
「もりママ〜」
大阪人の再会は、大げさである。3人は肩を叩き合い、ヒトミは幸を抱きしめた。
「あんまり変わってへんわ。めっちゃ嬉しい」
幸は身長172センチで、さらに肉付きも良くなっているヒトミに抱きつかれて、クラクラした。
「ヒトミちゃん、久しぶり〜。ケイちゃんも、元気そう。いつぶりかな、赤坂には来てくれたことあったよね」
「ほんまほんま。なんで横浜なん?ゆっくり聞かな」
夕食までに、少し時間があった。3人は一旦、幸の店に荷物を置き、中華街より港の側にある「スリーマティーニ」というバーで、アペリティフを飲むことにした。
スリーマティーニは、広々として、琥珀色の時間が流れていた。誰もが想像する「横浜のオーセンティックで居心地の良いバー」を叶えるような店だった。分厚い木のカウンターの向こうの片隅に、レコードが積まれ、客に合わせて恰幅の良いマスターが懐かしい曲を選んでいた。
「ええ感じ」
ケイが目を細めた。
幸はマスターにそっと尋ねた。
「私たち、久しぶりに会ってうるさいかもしれないから、テーブルに行きましょうか」
マスターはにっこり微笑んで言った。
「まだこの時間はお客さんが少ないですから、どうぞカウンターへ」
「ありがとうございます」
カウンターに3人が並ぶと、そこだけぽっと明るくなるようだった。ヒトミはピンク、ケイは黄色のワンピースで、それぞれ白とベージュのカーディガンを羽織っている。幸はベビーブルーのシャツに白いデニム。もともとはこの3人がメインの店をしていたのだから、歳を重ねても何か衰えない華やかさがあった。
ヒトミがマスターに声をかけた。
「マティーニ、って言いたいとこやけど、酔っ払うから、ジンソーダ、薄めで」
「ジンは何になさいますか」
「タンカレー。ああ、いいやつがありますね、それで」
「かしこまりました」
受け応えが、常連客とのそれのようで、マスターも楽しげだ。
「乾杯」
「ようこそ横浜へ」
3人はグラスを合わせ、口々に「美味しい」と呟いた。
行きの新幹線での話。富士山の話。その店の話。…
店を出る頃、ケイがふと言った。
「なんか、ちょっとだけわかった気がする」
幸は「え」とケイの顔を覗き込んだ。
「いや、なんでもりママ、横浜に店出したんか、聞こうと思ってたんやけど、なんか、この店で、こうやって話してたら、わかった気がして。こういう雰囲気でしょう。こういうふうに、お店やりたい、っていう気持ちになったんでしょ」
うんうん、と幸は頷いた。
「どういうこと? ようわからへんわ。なんで」
ヒトミは2人の顔を見比べて、きょとんとした。

- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






