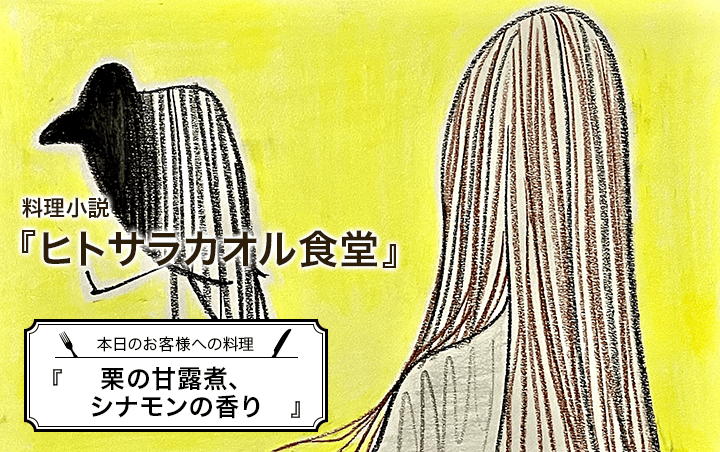
「栗を収穫しました。3日乾燥させてあります」
福岡の嘉麻市というところに住んでいる、ヤスコさんから、栗が届いた。
栗のほかに、生の落花生、激辛というシールが貼られた唐辛子と、手作りの柚子胡椒も入っていた。
「ありがたいなあ…」
幸は目を見開いて一つずつを見た。どれも発光しているように見えた。丹精して作られたものだけが発する、目には見えにくい光である。
ヤスコさんというのは、上京してきて、一緒に料理を習っていた少し年下の女性であった。高級ブランドのジュエリーの店で忙しく働いていて、休みの日にはまたゴルフと料理を習っているような人だった。ずっと自分を磨き続けていて、どんどん高みを目指しているようで、いったいどこまで行くんだろうと思っていたら、ある時、突然、地元で農業をやると言い出したのだった。
幸はその栗の輝きを、ヤスコさんの瞳を思い出すように見つめた。
せっかくの栗を美味しく生かさねばならない。
ええっと、どこかにあったな、と、引き出しの奥から栗むき鋏を取り出した。
水に1時間以上漬けた栗を剥く。これがなかなかな作業だった。
1キロほど剥いても大した量にはならない。
水に浸して灰汁を抜き、潰したクチナシの実と一緒に20分弱ほど煮る。お湯にクチナシの黄色がすぐに広がり、栗の実を染めていく。なかなかいい光景だ。
色づいた栗は冷ましておき、別鍋で砂糖と水でシロップを作る。
このシロップに、シナモンをひと枝割って入れ、また10分ほど静かに煮る。栗に染みたクチナシの黄色がシロップに移っていく。これがまたなんとも透明で綺麗な色だ。
ひと粒食べてみると、白ワインが飲みたくなった。
…成功だ。
🥂Glass 1
土曜は早朝から、ブランチの仕込みである。
母親が「こんなところで働くのはやめなさい」とやってきた事件から、凛花は2週間ほどやって来なかったが、また来るようになっていた。母親をどう説得したのか、それとも納得されていないままに来ているのか、幸はもう凛花に聞かなかった。
いかんせん、彼女はもう35歳なのである。自分のことは自分で決めるだろう。
その日の凛花は息せきって飛び込んできた。青ざめて両手をこめかみの上に当てている。
「幸さーん。今、今ああ、私の頭にカラスが載ったんですぅ〜」
幸は吹き出しそうになりながら、凛花の頭を見た。そんなにヘアスタイルが乱れてもいない。
「大丈夫?ケガはしなかった?」
「傷とかないんですけど」
自分の発したその言葉に安心したように、凛花は手を下ろした。
幸は凛花の頭を覗き込み、除菌ペーパーで頭皮を拭いてやった。
「大丈夫そうね。傷もないし、赤くもなってないわ。どんな感じで載ったの?威嚇されたのかしら」
「威嚇って感じじゃなくて、なんかもっと遠くへ飛ぶためにステップの着地点が欲しかったというか。…ふわっと乗ってすぐいなくなったんです。全体重をかけたわけじゃない感じ」
自分の説明に今度は可笑しくなったらしく、凛花はふっと笑った。
「たまたまその場所に凛花ちゃんの頭があった、ってことだったのね」
幸もその偶然に笑った。しかし、ちょっとネガティブになりがちな凛花はまたこんな妄想をした。
「でもなんだか、不吉じゃないですか。カラスが頭に乗るなんて」
「日本神話では八咫烏って神様のお使いよ。いい方に考えましょう。さあ、お茶でも飲んで、手伝って」
幸はポットのレモングラスティーをカップに注いだ。

- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






