
春は急ぎ足でやってきたかと思うと、足踏みして冬と手をつなぎ、やがてまた急にやってくるらしかった。
代官坂に紅白の木瓜の花が咲く屋敷がある。今年はそれも早かった。桜は咲こうとしたが凍りつき、息をひそめた。
幸は花屋で見つけた啓翁櫻を、カウンターに飾った。一人分、お客が減りそうな大きさだったが。
急ぎ足でやってきた春は、桜の香りとともに、ヒトサラカオル食堂にもやってきた。
「ご報告がありまして」
神妙な面持ちで、二人は奥のカウンターに座った。
大城と凛花だった。
凛花はすっかり服装の好みもメイクも変わった。少し額を出して、艶やかな髪を肩のあたりでふわりとさせている。リップのグロスが多目は変わらないが、メイクは色数を抑えている。シンプルで質の良さそうな白いニットのワンピースに覆われたボディも少し引き締まったようだった。
大城は、土曜日の夕方でもジャケット姿だ。この人に合わせると、彼女はどこかで決めたのだろう。二人は少し、居ずまいを正し、背筋を伸ばして、お辞儀した。
「僕たち、結婚することになりました」
幸はグラスを磨きながら、え、とも、へ、ともつかない声をあげた。そうなればいいなあと思ってはいたが、過度な期待は彼女にも自分にも良くないと思っていた。失恋した日に初めてここへやってきた凛花のイメージも大きくて、幸は時々、ネガティブなことを考えてしまっていた。
思えば、彼女の「自分を変えよう」と思うひたむきさはすごかった。30代も半ばになれば、なかなか自分を変えるのも大変なことだ。それを彼女は1年で、やってのけた。それこそが愛なのかもしれない。幸はそんなことを3秒ほどで思い巡らして、胸が熱くなった。
そしてその思いを込めて、ゆっくりと手にしたグラスを置き、二人の顔を見つめて言った。
「本当におめでとうございます」
「ああ、なんか、これでホッとした。… 実は今日、昼間に凛花さんの家にもご挨拶に行ってきたんです」
大城は白い歯を見せた。
凛花は涙ぐんでいた。そういえば、格好は大人っぽくなっても、どこか心はそうなりきれないところがある人だった。幸は頷きながら、聞いた。
「で、式はいつかしら」
凛花が泣き笑いで答えた。
「6月の最後の日曜日に。教会で式をして、ベーリックホールでパーティーを。ジューンブライドが夢だったんです。幸さんも絶対来てくださいね」
「素敵ねえ。絶対行くわよ!」
幸の声が裏返った。
🥂Glass 1
大城と凛花の幸せに弾むような背中を見送ると、店は一瞬、ぽっかりと穴の空いたような景色になった。
二人が「今日はお茶だけで」と飲んでいたカップを片付けながら、幸は凛花の両親のことを思い出していた。
どうやら、今日の大城のご挨拶のために、凛花の母親は2日準備をして料理を振る舞ったらしい。
凛花が苦笑いしていた。
「で、2日かかってこれだけ、って感じだったんですけど。… ビーフシチューと、サラダとマッシュポテトと、コンソメスープ。私も手伝おうかって言ったんですけど、自分の実力を見せたい、って。相変わらずでしょう。大好きなんですよね、ママは、大城さんのこと。最初は医者でないとダメだとか言ってたくせに」
大城が咳払いして言った。
「僕はおとうさんが好きです。優しくて、渋いんだよなあ。ちょっと憧れるじゃないですか、医者って学者って感じだし。リスペクトっすよ」
なるほど、親と仲良くなったことで、話は急速に進んだのかもしれない。あの母親は確かに凛花の年齢のことなど気にしていただろうから。
まあしかし、あの母親はこの店や自分のことをあんなに毛嫌いしていた。そこで出会った大城と娘の結婚を、あっという間に受け入れたのも、不思議な気もした。
土曜日のランチが賑わうと、夜は比較的静かなことが多い。
幸は一人で乾杯しようと、白ワインを1本抜くことにした。
「何がいいかなあ。お祝いだけど、一人だからなあ」
最近、すっかり値上がりしているフランスのサンセールを手にした。幸が白ワインのなかで一番好きなワインだ。モンラッシェなんていうのはもう高嶺の花になってしまった。サンセールは牡蠣に合うと言われていて、シャブリより爽やかで、香りが良い気がする。
「凛花ちゃんと、大城さんに乾杯」
ほのかな酸味と葡萄の香りが、舌の奥で広がった。
その時、店の前に人影を感じた。
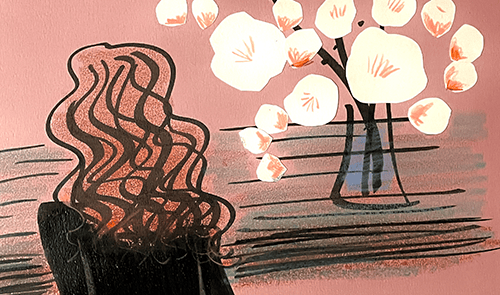
- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






