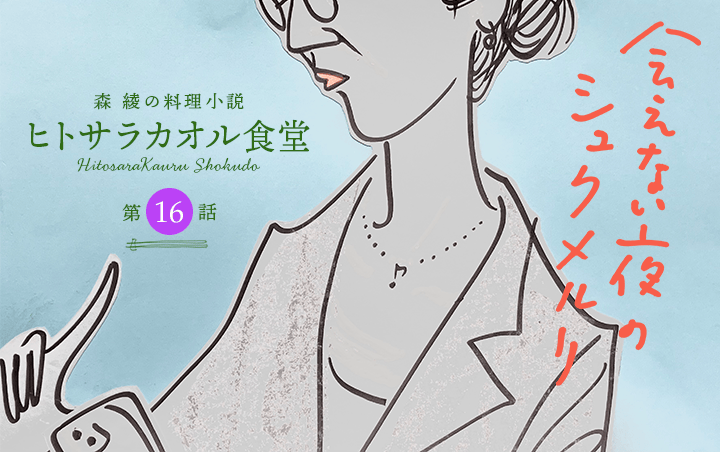
佐伯洸が弾くチェロを聴いてから、矢作夫人はたびたびヒトサラカオル食堂を訪れるようになった。あんなに毛嫌いしていたのに。
いい男といい音楽の効果は、あっという間に頑なな人の心を溶かしてしまったのだった。
その日は17時の開店そうそうやってきた。
「幸さんのお料理は本当に美味しいもん」
そんなおべんちゃらまで言った。
「矢作も付き合いが多いし、凛花も結婚式の準備やら何やらで忙しいし、私、ひとりでしょう。お漬物でチャチャっととか。いい加減なものしか食べてなくて」
「それはカラダに良くないですねえ」
幸はいきなりには彼女のことが理解できず、お客さんとして丁寧に接するほかなかった。どこかどぎまぎしていたとき、見慣れないひとりの女性がドアを開けた。
「あの、ひとりなんですが、いいでしょうか」
「いらっしゃいませ。どうぞ好きなところへおかけください」
幸は小さく会釈しながら言った。
風貌を見るに、40代後半だろうか。地味ないでたちだが、スッと首筋が伸びて姿勢が良かった。
女性はその首をスッと伸ばし、天井から床から、取り調べするように見渡した。そして、矢作夫人と離れたバーカウンター側の場所に座り、隣の席に角の丸くなった黒い表革のバッグを置いた。
🥂Glass 1
幸はその女性客をファッションチェックした。服好きのせいでついつい、そんなことをしてしまう。テーラーカラーのグレーのスーツ。黒髪は後ろでまとめてシニョンにしている。茶色い細いフレームの眼鏡。首元の細い金のネックレスのチャームは、小さな音符だった。少し前に出た四角い額が、隠しきれない美人の骨格を現していた。
ハンドバッグからスマホを出すと、大袈裟に人差し指を下から上へスライドして中身をチェックし、テーブルにかたり、と置いた。
誰だろう、この人は。探偵なんだろうか。それにしてはいやに堂々としている。もし探偵だとしたら、いったい誰について調べてるんだろう。あ、待てよ、国税庁の人とか? いやいや、ちゃんと税金払ってるし。そんな儲かってないし。…幸はあれこれ考えながら、注文を取ることにした。
「こんにちは。何になさいますか」
「飲めないので…何か、ノンアルコールのものはありますか」
幸は手書きのノンアルコールのメニューを見せた。
コーヒー
紅茶
ジンジャエール
バタフライピーソーダ
「あの、このバタフライピーソーダ、ってなんですか」
女は眼鏡をちょっと上げて聞いた。幸は気づいてくれたことが嬉しくて笑顔になった。
「あ、これね。バタフライピーっていう青い色素のハーブがあって、そのシロップを使ったものなんです。天然のブルーですよ」
「へえ。じゃあ、それをお願いします」
幸はシロップをソーダ水で薄め、昔懐かしい缶詰の赤いチェリーをのせた。
しゅわしゅわと波立つブルーの海の上に、赤いブイがのっているような、可愛い飲み物だった。それはグレーのストイックなムードの女性とは、不思議なギャップがあった。
「どうぞ」
女はストローでひと口のみ、なんの感動もなく、またスマホを見始めた。
矢作夫人は、チラチラと彼女を見ながら、幸の耳元に顔を近づけ、ひそひそ話にならないハリのある声で言った。
「誰かしら」
幸は人差し指を口に当てて、しーっという顔をして、彼女をおさめた。

- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






