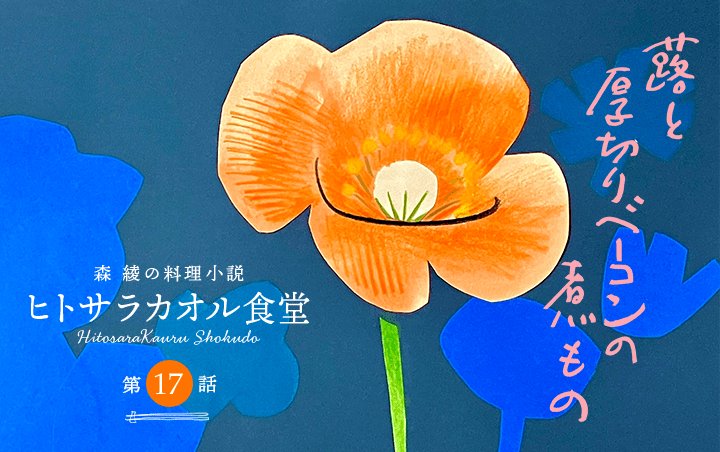
ヒトサラカオル食堂のある代官坂は、ジブリの映画『コクリコ坂から』の舞台になった場所だそうだ。
コクリコは、漢字では雛罌粟。ひなげしのことで、朱赤に近いオレンジの花が咲く。去年までは坂のあちこちに咲いていたけれど、今年はいつまでも寒い春だったせいか、坂にはほとんど咲いていなかった。
あっという間に、歩いているだけで汗ばむほどの日差しになった。
結婚式を控えた凛花だけが、落ち着かない季節のなかで、ぽっと一輪、明るく咲いているようだった。
マリッジ・ブルーになることもなく、彼女は嬉々として準備に勤しんでいた。さらに嬉々としていたのは、彼女の母親だったが。
なぜ結婚を控えた女性はこんなに綺麗になるのだろう。幸は本物の花を見るように、この頃の彼女を見つめていた。
🥂Glass 1
午後六時少し前。扉が開いて、凛花が入ってきた。
今日は、少し小さな声で挨拶した。
「こんばんは」
「あら、凛花ちゃん、こんばんは。随分、日が長くなったわね」
「…」
今度は拗ねたように、凛花はバーカウンターの一番手前の席に座った。奥の席では、セルジュが紺と白の太いストライプのシャツの襟を立てて、ビールを飲んでいた。凛花を見ると、右手を挙げた。
「やあ、マドモアゼル。こんばんは」
凛花は小さく会釈して応じたが、ふーっと、大きなため息をついた。
きたか、マリッジブルー? と、幸は伺うように彼女に声をかけた。
「どうしたの。最近の中では、一番浮かない顔だけど」
「…いろいろ大変ですね。二人で住むって」
「楽しそうだけど。何か、問題でも」
幸は彼女とセルジュの顔を見比べて言った。
凛花はうーんと両手で頭を抱えた。
「今、インテリア問題です」
「インテリア問題?」
凛花は極めて冷静に話し始めた。
「つまりね、大城くんは今まで、シンプルすぎるほどシンプルに住んでたんです。部屋には何もなくて、機能的なウォークインクロゼットをつくっていて。ご飯を食べるテーブルもなかったんです。でも、うちの家は割と祖父母の代からの木の家具がドシっとあって。まあそれはそれで私は落ち着いて育ってきたんですよね。でも、二人の居心地の良さを一つにするのがめちゃくちゃ大変なんですよ。なんかもう、最初からぶつかっちゃって」
「ほほう」
セルジュがグラスをもったまま、面白そうに体ごと彼女の方を向き、頬杖をついた。
「大城は今まで通りにしたいと言ってるんだ」
「そうなんです。私は今までと全くおんなじでなくてもいいんです。でも、なんというか、彼の居場所にそのまま入る、っていうのも違うと思うんですよね」
「ほほう。なるほど」
セルジュは、うん、うんと二度頷いて、語りモードに入ろうとした。
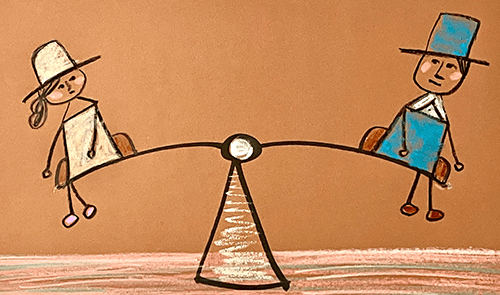
- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






