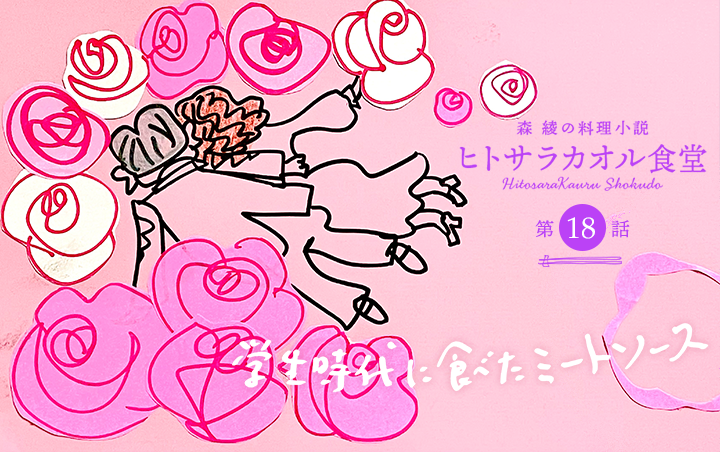
元町・中華街駅の5番出口のエレベーターを屋上まで登ると、アメリカ山公園の薔薇が出迎えてくれる。緩やかな坂を上ると、港の見える丘公園があり、そのなかにまた薔薇があふれるイングリッシュローズの庭がある。その庭だけでも約150種800株もあるそうだ。
海の香りをかき消すほどの、恍惚とする薔薇の香りに、盛田幸は店を開ける前のつかのま、彷徨っていた。
名前と花を見比べながら歩く。結局、覚えられないのだけれど。
バターの色に咲く大輪はバタースコッチ。赤いビロードのようなレッド・ドリフト。
ブルゴーニュのワインのようなピンク転びの紅色が美しい、アイスバーグ。
品のあるピンクの中輪が頬を寄せるように咲くピエール・ド・ロンサール。
ウェディングドレスと燕尾服の若い二人も、頬を寄せ合っている。
「はーい、もっと見つめ合ってくださーい」
「ご新郎はご新婦の肩に手をー」
公園中のどのバラよりも晴れやかな笑顔は、凛花と大城だった。
幸が見ていることに気づかず、二人は見つめ合ったり、背中合わせになったり、映画のポスターのようなポーズをとり続けていた。
フォトグラファー、ヘアメイクだろうか、スタッフは女性4人がかりだ。ドレスの裾をもつだけの人もいた。
大城が、幸の姿に気づいた。
「あ、幸さーん!」
「え。あ、さちさーん」
肩の出たマーメイドラインのドレスを着た凛花が大きく手を振る。ヘッドドレスは、小さなサテンのトーク帽に長めのチュールがついたもので、すらりとしてややおとなの花嫁に、よく似合っていた。
大城は正統派の黒い燕尾服で、サテンの白い蝶ネクタイをしていて、新婦のトーク帽とよくリンクしていた。
「前撮りね。二人とも素敵よ〜」
少し近寄って声をかけ、小さく手を振って通り過ぎようとした。凛花が叫んだ。
「後で行きます〜」
「いいのいいの、頑張って〜」
若いっていいわね、とひとりごちると、少し離れた場所に、50〜60歳と思しきカップルを見つけた。
「あれ、吉田さん?」
セルジュたち常連3人組のひとり、真面目で薄い印象の吉田だった。幸は我ながらよく気づいたと思った。
若いカップルと同じように、頬を寄せたり、おでこをくっつけて向かい合ったり、見ている幸は照れくさいのを超えて、ちょっと罪悪感を感じるほどだった。
そそくさと立ち去ろうとすると、びっくりしたような声で吉田が叫んだ。
「ああっ、ママ。ヒトサラカオル食堂の…」
立ち止まって振り向くと、新郎新婦は恥ずかしそうに顔を赤らめていた。
「おめでとうございます。前撮りですか」
幸はあわてて言った。すると、吉田は言い訳のように言った。
「あの、僕ら、事情があって結婚式をしなかったもので、いや、数十年前にね。それで、妻が最近、こういうのがあるからって。こっそり撮っとこう、って」
ファンデーションがややよれてきていた花嫁が、さらに顔を皺くちゃにして言った。
「… だからあの、後撮りです」。
🥂Glass 1
幸は今日もお香を一本たいてから、店を開く。
煙がくゆる間に、心がすーっと落ち着いていく。たとえざわざわしていようと、たとえ沈んでいようと、たとえ浮き足立っていようと。お香をたく時間は、彼女の心の海を凪にしてくれるのだ。
今日は薔薇を見てきたので、薔薇の香りのお香をたいた。
二組のカップルの笑顔を思い出すと、なんとなく悪くない日になりそうな気がしてきた。
開店と同時に、白シャツにグレーのズボンを履いたメガネの男が立っていた。
日本の電車の各車両に必ず何人かはいそうな、普通の人。
「こんばんは。お久しぶりです。佐伯と待ち合わせです」
「あ、お久しぶりです。ええと、…岡部さん」
客商売ができるかどうかの最大ポイントは、顔を名前を一致させて一度会ったら忘れないことだ。おそらく何万人という客の顔が、幸にはインプットされている。
岡部は静かに腰掛け、店の香りに気づいた。
「薔薇の香りがしますね」
「鼻がいいんですね。気づいてもらって嬉しいです」
そこはかとないその場の香りには、気づかない男性も多い。岡部良介のその繊細さは、やはりもともと音楽をやっていたような感性に裏打ちされているのかもしれない。心根の優しい人なんだろうと、幸は想像した。
「先にお飲みになっていますか。待たれますか」
「じゃ、暑かったので、水だけもらえますか」
「はい」
グラスがテーブルにつく頃に、佐伯洸が現れた。こちらは黒い麻のシャツを着ている。
「久しぶり」
「おう」
二人は白ワインを頼んだ。
「冷たいやつね」
「はい」
幸は冷蔵庫から、ニュージーランドのソーヴィニヨンブランを取り出した。
「ホークスベイのシレーニです。もともと教会だったところらしいです。…行ったことないんですけどね」
「そういうとき、大阪の人は、知らんけど、って言うんじゃないの」
そう言って佐伯がふっと笑った。
幸もふふっと笑って、アクセントを直した。
「しらんけど↓じゃなくて、知らんけど↑」。
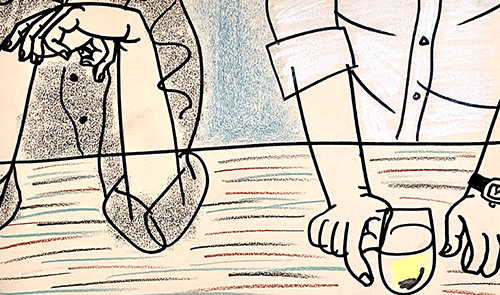
- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






