- HOME
- 連載長編小説『4 LOVE NOTES』
- 第5話 『多美子の出会い《前編》』
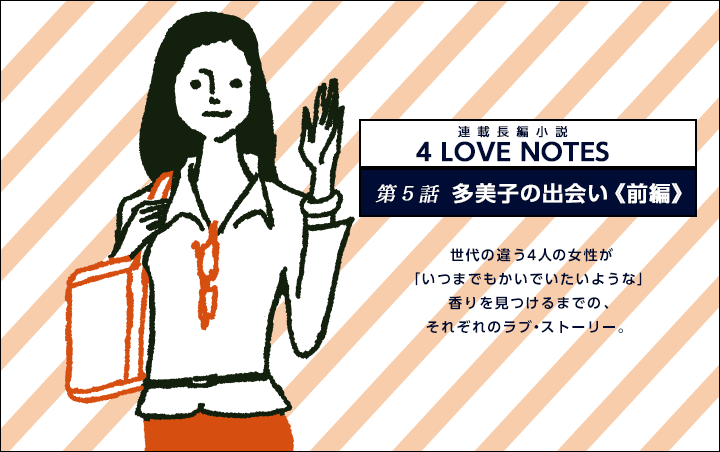
【ここまでのあらすじ】
暗闇でご飯を食べるイベントで偶然知り合った女性誌編集長の鍵崎多美子(50代)、フラワーアーティストの内畠麻貴(40代)、カフェでパティシエをする野添有紗(30代)、旅行代理店勤務の殿村未知(20代)。
4人はそれぞれにちょっと傷つきながら、楽しみながら生きている。有紗の店での女子会を終え、世代を超えて、何か通じ合うものを感じ始めていた。
《1》
女性誌の編集長は会社のなかでも外でも忙しい。
社内では編集部内だけではなく、編集長会議、役員も入る大きな会議などいくつも会議がある。社外では、ファッション、コスメ、アクセサリーと、季節ごとにレセプションや展示会がある。そこでの外交も、新製品の一早い掲載や、果ては広告営業にもつながる大事な仕事だ。
外資のファッション誌は、編集長代理を置き、これを分業しているところもある。しかし、多美子のいる版元は老舗の日本の会社なので、そういう配慮がまだなかった。
ハイブランドの夜のレセプションでは、外交担当に専任した外資ファッション誌の編集長が、華やかなソワレでやってくる。黒とはいえ、肌見せやスパンコールなど、昼間の編集部ではとても着ていられない衣装だ。
多美子はそういうとき、いつもトイレで着替えて出かけるはめになる。
「ああっ、タミーさん、変身~! いってらっしゃーい」
今日も女子トイレから出てきたところを副編集長の海上敏夫に冷かされ、多美子は肩から羽織った薄いコートの襟を立て、モデルのようにポーズを作って、目力を発揮した。
「いってきます!」
「き、今日もいけてます…」
海上は眩しそうにまばたきし、鼻の上でずりおちそうなメガネを人差し指で押し上げた。
彼はもう20年以上女性誌編集部にいる。その前は芸能誌にいたため、女優やタレントのブッキングには長けていた。自分ではファッショナブルなつもりでパンツの裾を折上げて足首を見せているが、多美子はそれが気になって仕方がない。良い意味ではなく悪い意味で。
多美子の黒いワンピースは、いつだったか、ドルチェ&ガッバーナのプレスセールで80%オフで買ったものだ。胸元がぐっと開いていて、かなり腰がくびれている。これをアラフィフで着られるだけでも大したものだが、ジュエリーのないデコルテは、もうやつれてどこかみすぼらしくなってきたと多美子は薄々、自覚していた。
外へ出ると、少しひんやりしていた。タクシーを拾い、乗り込んで、癖のようにスマホを見る。
ほんの少しスマホを見ないうちに、着信があった。
- <<前のページ
- 1/4
- 次のページ>>






