- HOME
- 連載長編小説『4 LOVE NOTES』
- 第9話 『未知のお見合い』
-
- 特集
-
連載長編小説『4 LOVE NOTES』
第9話 『未知のお見合い』
《3》
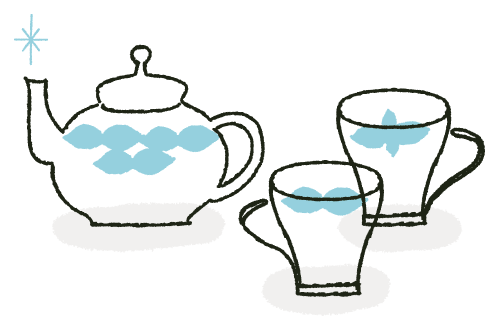
要するに、お見合いであった。
未知は成り行き上、会うと言ってしまった。言ってしまったが、その事の重たさはすぐに胃にのしかかってきた。
再来週の土曜、キャピタル東急のオリガミというラウンジカフェに、15時。
もし断ったら、地方に異動になるのだろうか。それとももっとつらい部署だろうか。
相手は自分をどう思うのだろう。父親が気に入ったからと言って、息子が気に入るとは限らない。むしろその逆のパターンの方が多いのではないか。だいたい、高井専務はなぜ自分のことを気に入ったのだろうか。あのとき何を話していたというのだろう。奥入瀬の話だったか、それとも湖北鉄道の話だったか。
花粉症より、胃痛が先に立つようになった。しくしく痛む。
だいたい、お見合いって、何を着ていったらいいのだろう。
お見合いらしい格好ってどうしたらいいのか。そうだ、ファッション雑誌にいる多美子に相談しようとメールをしてみた。
「多美子さん、今度、お見合いをすることになりました」。そう書いて、消した。
「多美子さん、今度、紹介されて人に会うのですが、そういうとき、どういうものを着たらよいのでしょう。よかったら、教えてください」
多美子からはすぐ返信がきた。
「やったー❤ お見合い?」
なぜこの人は他人のことでいきなり盛り上がれるのか、未知には不思議だった。
「そんなような感じです」 そう返信すると、また矢のように返ってきた。
「ワンピースがいいわね。未知さんにはクリーム色とか、アイボリーが似合いそう。ブルーは顔が暗くなるかも。襟元は開きすぎないようにね」
「ありがとうございます」
未知は多美子に言われた通り、白っぽいワンピースを買った。こんなにすぐに汚れてしまいそうな色の服は今まで買ったことがなかった。デパートの店員は「お似合いです」と言ったが、あまり心がこもっていなかった。
家へ帰って着てみると、鏡のなかによそゆきの自分がいた。
「私、やる気あんのかな」
明らかに着るものについていけていない自分を感じた。






