- HOME
- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』
- 第4回『きんもくせい』
-
- 特集
連載読み切り短編小説『香りの記憶』
第4話『きんもくせい』
《2》
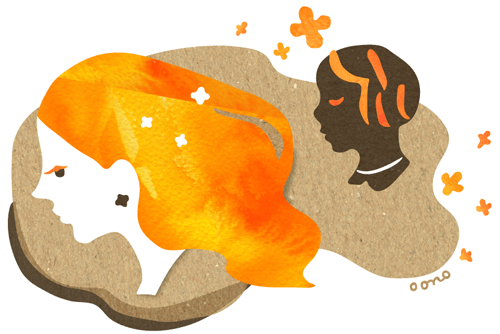
佳子は、子ども時代を両親と神戸で過ごした。
その住宅地は幾本も山に向かって坂道が走っていた。
急な坂道を登ったところに、ピアノの先生の家はあった。
こぐまのアップリケをしたレッスンバッグに2冊の教則本と、横に長い五線紙の黄色いノートが入っている。4歳の佳子はそのバッグを自分でずっと持ちたいのだが、気がつくといつも母親がもっていた。
「こんにちは、佳子ちゃん」
先生はまだ音大の3年生で、この家の長女だ。
「こんにちは、先生」
「よろしくお願いします」
母親は入り口に近い小さな部屋で待つことになっていた。小さなアンティークのカフェテーブルの上には、銀の一輪挿しにいつも何かしら季節の花がささっていた。
佳子は先生の部屋にあるグランドピアノの前に座る。
肩までの髪をカチューシャでまとめておでこを出した先生は、ぱっちりした目の美人だった。いつも丸襟の白いブラウスで、寒くなるとスイス風のかちっとした毛糸のブルーのカーディガンを羽織っていた。
先生が少し変わったのは、佳子が通い始めて数か月経った夏頃のことだった。
窓を開けると蝉時雨がうるさいほどだったが、高台のその部屋にはクーラーがなく、アメリカ製の薄緑の扇風機がうなりながら回っていた。先生は佳子にメルローズという教則本のなかの1曲を弾かせたまま、そわそわして、窓の外を見ていた。
佳子が弾き終わっても、先生は窓際で背中を向けていた。
「…先生」
「あ、ごめんなさい」
駆け寄って佳子の隣の椅子に座った先生は、嬉しそうに時計ばかり見ていた。
それからしばらくすると、またこんな日もあった。
その日の先生はとても不機嫌だった。あまり練習をしてこなかった佳子がつっかえつっかえ弾いていると、突然、教則本をパタン、と閉めて、佳子の手をぴしゃっと叩いた。
親にも叩かれたことのない佳子は身を硬くして、鍵盤を見つめた。
声も涙も出なかったが、小刻みに震えた。それを見た先生ははっと我に返ったように佳子の肩を抱いた。
「ごめんなさい。…ごめんなさい。先生どうかしてた。ピアノを嫌いにならないでね。それから、あの、練習はしてきてね」
佳子はただただ怖かった。
先生は何か病気なんだろうか。おかあさんに言ったほうがいいんだろうか。






