- HOME
- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』
- 第5回『白トリュフとウォッカのスパゲッティ』
-
- 小説
連載読み切り短編小説『香りの記憶』
第5回『白トリュフとウォッカのスパゲッティ』
《2》
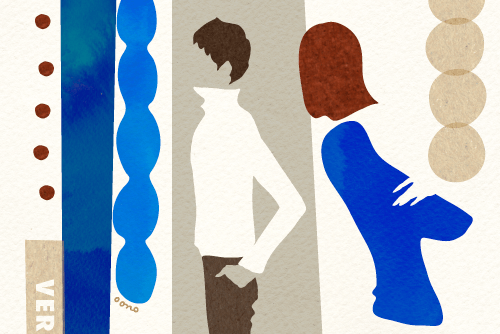
二人はベルリンの街のカフェでランチを食べようと、メニューを開いていた。
ベルリンは霧の下にあった。フランクフルトはもっとかすんでいたが。
「ねえねえ、フランクフルト、怖かったわねえ。あれどのくらい旋回してたのかしら。あのまま空港に降りられなくてさ、途中で落っこちて、私、死ぬかと思ったわ、まさかのあんたと」
「それだけは勘弁」
「私だって。まだベンちゃんに会えてないのに!」
「元カレ、ベンて言うの」
「ベンヤミンなんだけど、ベンちゃんって呼んでたの」
「はあ。えんちゃんとベンちゃんかい」
エリコは鼻で嗤い、メニューのなかを指差した。
「私、これ。白トリュフとウォッカのスパゲッティ。あとはなんて書いてあるのか、意味わからん」
「あたしはシュニッツェルにするわ」
「アーンド、白ワイン?」
「YEAH」
二人の前に、注文したものが運ばれてきた。シュニッツェルは大きな薄いトンカツのような様相だった。えんちゃんがレモンを絞ると、まだジュッと言いそうなほど出来立てだ。
エリコの頼んだ白トリュフとウォッカのスパゲッティは、着くなり濃厚な香りを醸した。トリュフは上にどっさり盛られているだけでなく、麺のなかにも見え隠れする。あたりの空気が変わりそうなほどの香りだ。そして一見、クリームで和えられたスパゲッティからは酔いそうなほどまたウォッカの香りもした。
フォークに絡めて口に入れると、トリュフとウォッカの香りが激しく抱き合っていた。それをなんとかつなぐこくのある生クリームと相まって、絶妙な味だ。
「危険。これは危険」
エリコは思わず口走った。
「ひと口ちょうだいっ」
その香りにひかれたえんちゃんはもうシュニッツェルのことがどうでもよくなったように懇願する。
「ダメダメ。これ止めたら死ぬ… 酔う… 」
「きゃー、そんなこと言われたらよけい欲しい」
「…欲しいか」
「欲しい」
エリコはしょうがなくお皿を差し出した。
えんちゃんはひと口食べると「おおっ」と、男らしい声を出した。
「これはやばいわ。確かに食べたことがない味。止めたら死ぬわ」
えんちゃんは結局、残りを食べてしまった。
エリコはしかたなく、シュニッツェルも食べて、白ワインをごくごく飲んだ。






