- HOME
- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』
- 第5回『白トリュフとウォッカのスパゲッティ』
-
- 小説
連載読み切り短編小説『香りの記憶』
第5回『白トリュフとウォッカのスパゲッティ』
《3》
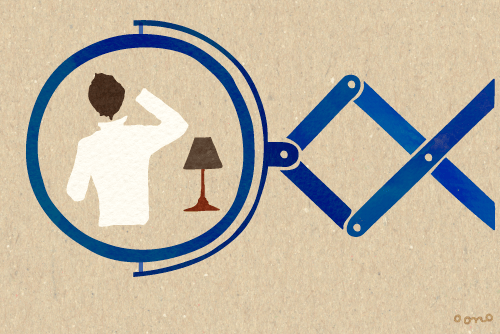
翌日、二人はポツダムに向かった。そこで、えんちゃんは元カレのベンちゃんと会うことになっていたからだ。
「なんでそんなところまで行かなきゃいけないわけ?で、なんで私がつきそうの」
エリコはその日はえんちゃんとは別行動で、美術館を巡ろうと思っていた。
「だって、ベンちゃんにはきっとここで恋人がいると思うし。その人と一緒に来たりしてたら、私、泣いちゃうし」
「ダメだねえ…。人のことは言いたいように言ってたくせに」
エリコはえんちゃんが泣くところも面白いと思ってついていくことにした。
なんだろう。それは意地悪なことだけれど、それすら許されるような間柄って。恋愛でもなく、普通の友情でもなく。二人は何かを超えた間柄なのかもしれない。
えんちゃんは前の晩に鼻歌をうたいながらパックをしていた。朝から髪や眉を整え、新しいブルーのシャツの上に、これまた新しい柔らかいグレーのカシミヤのセーターを着た。
「気合入ってるねえ」
「あんた、女心がわかんないわね。ユーミンの『Distiny』っていう歌、知らないの」
エリコはその歌を思い出した。
「今日に限って 安いサンダルを履いてた〜、ってやつね…」
エリコが歌い出すと、えんちゃんも一緒になって歌った。振られた相手にはいい女になって、かっこよくなって見返したい。えんちゃんの気持ちは、エリコにはなんだかくすぐったいようで、懐かしかった。






