- HOME
- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』
- 第7回『赤い実のなる木』
-
- 小説
-
連載読み切り短編小説『香りの記憶』
第7回『赤い実のなる木』
《2》
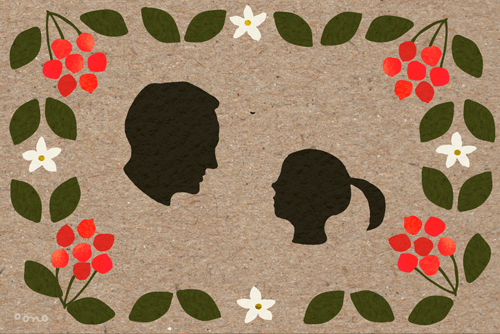
葉奈が思い出す父親は、いつも庭にいる。
子どもの頃から、いつも休みの日の父親は庭にいたからだ。
父親は地元で警察官として定年を迎え、去年、63歳で警備会社も辞めた。
今は好きな庭いじり三昧だ。田舎だから、庭は広くて手がかかる。
ゲッツキの垣根、ハナミズキ、梅。手洗い所のそばのいちじく。おもとに、シダ。夏には朝顔、秋には菊。
種類はバラバラで、ガーデニングと言えるほど洒落た木はない。
いつだったか、クリスマスに買ったもみの木も、もう誰もが見上げるほどの高さに成長している。
なかでも、葉奈はゲッツキが好きだった。夏に白い小さな花が咲き、ジャスミンのようなやさしいいい匂いがする。
だからかどうか、いまだにジャスミンの香りを手にとることが多い。オーデコロンも、部屋のディフューザーに使うアロマオイルも。
「お父さん、なんでこの木は白い花が咲くのに、赤い実がなるんやろな」
ある年の冬、まだ小学校低学年だった葉奈が、父親にそう尋ねたことがあった。
日焼けした顔に白目のところだけ白い父親は、赤い実をひとつつまんでセーターの下のシャツでこすり、ちょっとかじって言った。
「木は花を咲かせるのに一生懸命や。その後、何色の実がなるんかまでは、知らんやろ」
葉奈は「そんなさびしいこと」と、子ども心に思った。が、その気持ちをどう言葉にしていいかわからず、黙っていた。
「かじるか」
父親は赤い実を葉奈に差し出した。葉奈は頷いてそれをかじった。
「甘…ううん、苦い」
顔をしかめた葉奈を見て、父親は顔をくしゃくしゃにして笑った。






