- HOME
- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』
- 第8回『砂糖菓子のリボン』
-
- 小説
-
連載読み切り短編小説『香りの記憶』
第8回『砂糖菓子のリボン』
《3》
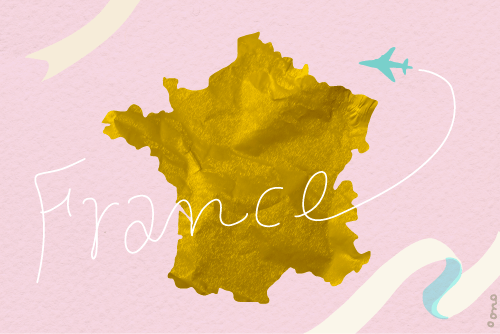
パリに着くまでに、二人は以前からの知り合いのように話をした。映画を見て、機内食を食べた。
「砂糖菓子ってさ、つやっとした飴みたいなのでリボンを作ったり、風船みたいなのを作ったり、鳥の巣みたいなのを作ったりするんでしょ」
「そうそう、よく知ってるじゃん」
「それを勉強してどうするの。ホテルのパティシエになるの。それとも、お店とかやりたいの」
「うーん。いいね、店とか。いつか出せたらいいな」
「駒澤大学のあたりとか、いいんじゃない。あとはそうだなあ、桜新町とか」
「高そうなところだね」
「きっと出せるよー」
根拠もなく言う香苗に、彼は根負けしたように笑って言った。
「出せるといいね」
飛行機は着陸の案内を始めた。
「ああ、もうすぐ着くね」
「あなたのおかげで楽しかったわ。だいじょぶ? トランジットできる?」
「ちょっと不安だなあ」
「うちの婚約者が迎えにきてくれてるから、聞いてあげるよ」
「…うん」
無事に着陸し、シートベルト着用のランプが消えると、彼は立ち上がって棚からまず香苗の茶色いエルベシャプリエを降ろした。
「あの、もう一個あるの、お土産の袋が」
「ちぇっ、人使いが荒いなあ」
彼は笑って紙袋も降ろした。
二人は一緒にシャルドゴール空港に降りた。
香苗の婚約者は出口の間際まで来ていた。
「あ、ありがとう。あのね、トランジットをしたい人がいて…」
「どこに」
振り向くと、あんなに大きな彼は、影も形なかった。
香苗は名前を聞くのも忘れた、と思った。






