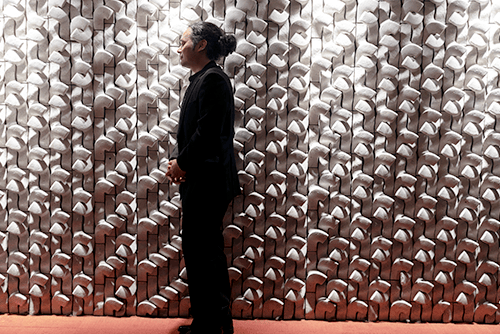- HOME
- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」
- 第204回:富名哲也さん(映画監督)
《2》大竹しのぶさんの圧が大きくてまともに話ができなかった
主演の二人の脇を固めた役者さんも、ちょっとやそっとでは動じない芸達者揃い。大竹しのぶさん、片岡千之助さん、石橋静河さん、森山開次さん、田中泯さん…。画面に現れる数は少なくても、しっかりとその姿が胸に焼きついて消えないような演技です。能楽師の辰巳万次郎さんも出演されています
「大竹しのぶさんはよく出てくださったなあと思います。なんというか、存在の圧が大きくて、まともに話ができなかった。話をしない方がいいのかなとも思いました。僕は説明してそのように演技してもらうのも嫌なんですね。ここはこういうシーンなんで、こうしてください、と説明すると冷めてしまう。お互いに何を考えているんだろうと思いながら、つかみどころがない方がいいんじゃないかと。時間がくれば始まりますし、何かをつかむような感じで撮影できたらよくて。」
彷徨い続ける男を演じた森山開次さん、あの世の入り口にいる人たちを束ねる長のような役割をする田中泯さん。身体表現の国宝のようなお二人は、歩く、座るといった普通の動作を見ているだけで、そこに一人の人間の人生を感じるような凄みがあります。
「脚本では、たとえば開次さんのところには『脚を引きずっている男』としか書いていない。たとえばもっと贅沢に予算と時間があれば、もう少しストーリーを作ったかも知れません」
削ぎ落とした結果なのかも知れませんが、ひとりひとりの俳優の姿がとても印象的で美しい。この映画は、俳優たち自身にとっても、忘れられない作品になっていることでしょう。
《3》「無宿人」たちを描いたわけではないけれど、そこが始まりだった
舞台に選ばれた佐渡島は、最初から決めていた場所ではなかったそうです。
「前作「ブルー・ウインド・ブローズ」は、映画祭の助成金をもらって物語は書いていたのですが、東京近郊では合わないなとは思いました。それで、当初は僕の先祖がある石川県の能登で撮ろうと漠然と思っていたんです。そうしたら、畠中が前作を撮った佐渡にちょっと寄ろうと。なんとなく歴史的には暗いイメージがあったんで、なんで、と思ったんですが、行ってみたら自然は豊かだし、島の人なのであったかいし、ご飯も美味しかったですし。惹かれるものがありました。後々、能登の人たちも昔から北前船という船で佐渡に出入りしている人が多かったらしいと聞いて、ある種の縁なのかなと思いました。もしかしたら、僕の先祖の人たちも佐渡に来てたこともあるんじゃないかって」
今回の『わたくしどもは。』は、成仏する前の世界を彷徨っている人たちが主に描かれていますが、佐渡の金山の廃墟という景色が、またぴたりとそぐうのです。
「昔、佐渡に金山があったという話はなんとなくは聞いていたんですが、最初は関心は向かなかったんです。前作の撮影が終わった後だったか、畠中と二人で坂道を歩いていて、金山の割れた頂上が遠くから見えて、おお、と思ったんですね。なんか鉱脈があるからなのか、磁場なのか、霊的な話ではなくて、本当に磁石のように引っ張られる感じがあって、ずっとそこを目指して坂道を歩いていったんです」
富名さんと畠中さんのお二人も、磁石で結びついているように思えるほど、公私共に一緒にいる夫婦。今回も、畠中さんのプロデュースとキャスティングが冴え渡っています。二人でいるから引き寄せるパワーのようなものがあるのかもしれません。
この二人が歩きながら出会ったのは「無宿人の墓」という小さな看板でした。
「無宿人の墓、という言葉に完全に関心が向いてしまったんです。なんだろう、これ、って。それでその日は終わってしまって。その後、調べました。無宿人というのは、なんらかの理由で国籍を奪われた人たちが、内地から結構連れて来られて、水替人足という、水を外に出さなきゃいけないという、かなり過酷な労働を強いられていたようなんです。あまりに仕事が過酷で、2~3年で亡くなってしまった」
虚しく亡くなっていった人たちの想いが、富名さんの胸に沁みてきました。
「それがここで撮ろうと思うきっかけになりました。だからと言って、無宿人の人たちを描く映画ではないですが、そこはなんとなく始まりだったんです」。