

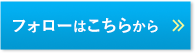

マンションのベランダは海側を向いている。
今日も風が強い。春の嵐は辛すぎる、という歌詞があったような気がするが、はて、誰の歌だったろうか。
盛田幸は、鼻歌をうたいながら、プランターの植物に時々声をかけていた。
「頑張ってね。ここは地中海ではないけどね」
南風が吹き始める季節は、塩害がすごい。
ベランダのハーブはそれを見越して、盛田幸はオリーブとローズマリーとラベンダーにした。
「オリーブさん、実がなったら、少しくださいね」
もちろん、オリーブの木は返事をしない。調べると、実がなるにはどうやら3年ぐらいかかるらしい。
「おばあちゃんにならないうちに、お願いしますね。あら、もうおばあちゃんだって?」
独り言を言い出したら立派な年寄りである。そう思い至って、幸は黙った。
また大きな客船が停まっているのが見える。あの船はどこから来て、どこへ行くのだろう。
そろそろ、海外からのお客さんも増えてきたようだ。
幸は旅の思い出を振り返った。
パリ、ニューヨーク、ベルリン、香港島、台北、ソウル。
思えば街中ばかりを訪ねてきた気がする。そして買い物ばかりしていた。パリには5回は行ったな。両手に紙袋を下げて歩いたサントノーレを、もう一度歩きたいな。
ふとベランダの下を見下ろすと、あのフランス語を口走る常連の男がゆったりと歩いていた。タックの入ったズボンのポケットに片手を入れ、もう片方の手にはパイプを持っている。今日はベレー帽でなく、髪を撫でつけている。しかし派手なパーブルと白のストライプのシャツのボタンを3つ外しているのはこの辺でこの人しかいない。
「セルジュさんだ」
彼がセルジュさんと呼ばれていることは、最近知った。そういえば、フランスの名優、セルジュ・ゲンスブールの風情がある。
その時、ポケットからスマホを取り出し、何やら話し始めた。
ウロウロと、行ったり来たりしている。あまり楽しそうな顔ではない。
しばらく話して、セルジュは電話を切り、肩で大きくため息をついた。
🥂Glass 1
店を開ける前に、幸は一本、お香をたく。
だいたい、アンバーかトンカのような甘い香りだ。その日の気候に応じて、お茶の香りやレモングラスのようなすっきりした香りを選ぶこともある。
香りは空間を作るスィッチのようなものだ。そして、幸の背中をポンと叩いてくれるような存在でもあった。
「よーし、今日も開けよう」
このところ「ヒトサラカオル食堂」は少し営業業態を変えた。
メニューの書き方を変えたのである。
肉料理とか魚料理とかパスタとか書いていたが、そんなにたいそうなものを作れるわけでもない。それで、今日ある材料を羅列することにしたのであった。
そして、奥のカウンターの前に、野菜をかごに入れて置いてみることにした。
今日は、なんと言っても太いアスパラガス。
空豆。
プチトマト。
小さな、新じゃが。
さすがの生命力。春野菜は、並べてみると、花にも負けない存在感がある。
「オッケー」
腰に手を当て、悦に入っていると、エプロンの中のスマホが震えた。
「はい、ヒトサラカオル食堂でございます」
「ああ。もりママ。セルジュですけどね、ちょっと若いのを連れて、後で行きます。少しつまんで呑む感じだな。20時かな」
「ありがとうございます。わかりました。お席、ご用意しておきます」
「はい、お願いします」
若いの、って男かしら、女かしら。女性なら、そんなふうには呼ばないか。
セルジュは20時過ぎに、若い男性を連れて現れた。
白Tシャツにイタリアものらしいサマーウールの紺のジャケット。タイトなシルエットがジムに行っていそうな背中に沿っている。
今時の清潔感の漂うおしゃれさんだ。
「クラフトビール二つ」
「いや、僕、もう飲めないんで」
「ええ〜。今朝の電話で俺を呼び出しといて、それはないだろ」
セルジュは顔を顰め、両手を欧米人のようにちょっと挙げた。
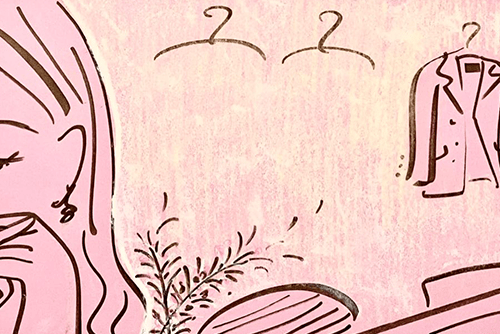
- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






