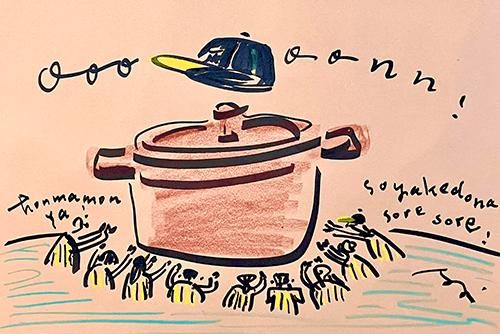🥂Glass 2
男は語り出した。
「いや、初めはね、しゃべってたんですよ、大阪弁。でも嫌な顔しはるお客さんがいてね。訛ってますね、とか。東北の人も九州の人もみんな方言を直すのに、大阪の人だけ直さないのはなぜですか、とか言われて。なぜですか、って知るかー。そのうちね『大阪の人はすぐ値切るんでしょう?じゃあうちも値切ろうかな』とかね。ほんま腹立つ!」
放っておいても一人で喋っていた。体の中に溜めていた大阪弁があふれ出てくるようだった。
「優勝かあ。18年前なあ。2005年かあ。マダムはなにしてました?」
幸は2005年を振り返った。もう上京していた。赤坂に店を出していた頃だった。
「赤坂でね、バーやってました。焼きそばも出すバー。焼きそバー、言うてね」
「ええな。行きたかったな。オレは大阪にいてました。95年入社やから10年目か。上の子が幼稚園入った頃かな。お受験するとかせえへんとかいうてね。うちは私学行かすような給料でもないのに。向こうのおかんがうるそうて。嫁はんと二個一やからね。まあ、そやから多少援助してもろとるんやけども」
大阪にはありがちな、妻が実家とまだ密接で、時々、夫は肩身が狭い思いがするというパターンなのだろう。確かに経済的援助もあるだろうけれど、夫は「一番の家族はこっちではないのか」と思うこともある。
幸はシャンパンをひと口飲んで、頷いた。
「割り切りはったらよろしいやん。そやけど、あっちもこっちも、気ぃつかいますねえ」
男の目が嬉しそうにカモメの形になった。
「そやねん!割り切って、おおきに、ありがとうございます、って言うてたらええねんけど。貰いっぱなしもいかんし。気ぃつかうんですわ」
そして今度は、大袈裟に肩を落とした。
「ほんで単身赴任で楽になるわ〜と思ったら、大阪弁いじめやろ」
幸は男の感情の上げ下げに笑いながら、言った。
「奥さん、きれいな人でしょ。ね、おしゃれで。お客さん、シャツ、おしゃれやもん」 ちょっとおだててみた。すると、男はまた大袈裟に手を振った。
「いやいやもう、ブサイクブサイク」
それは関西人独特の謙遜だった。大事な人を他人にけなされたくないとき、先に予防線を張るのであった。