
代官坂を抜ける風が、めっきり冷たくなった。
麓に佇む巨木の金木犀の香りが季節を告げている。
からりとした秋晴れは心の湿気まで持っていってくれるようだ。
盛田幸はチョコレート色の薄いニットの上に赤いトレンチコートを羽織って、元町ショッピングストリートを横切ろうとした。
そこへ、凛花とその母親の矢作夫人、大城の三人とばったり出くわした。
いや、正確には4人だった。大城は空っぽのベビーカーを走らせていたが、矢作夫人の腕の中には、生成りのカシミアに埋もれるように小さな赤ちゃんがいた。凛花と大城の子だ。
「さちさーん!」
「凛花ちゃん!」
「ごめんなさい、ご無沙汰しちゃってー」
「いえいえ、こちらこそ。お祝いしなくちゃと思いながら。…いつ産まれたの」
「7月21日です。今日、100日祝いで、実家でお食い初めをしようと」
「それはおめでとうございます」
幸は丁寧に頭を下げ、矢作夫人の腕の中の赤ちゃんを覗き込んだ。
気候が良いことは、こんなに小さな命も朗らかにするらしい。眩しそうにしながらも、口元はにこにこと笑っている。
大城に似た鼻筋と、凛花に似たクリっとした目元が愛らしい。
真っ白なロンパースには小さな襟がついていて、そこに小さな蝶ネクタイがついている。
「紳士ね… 男の子なのね」
「はい。彗仁、けいと、です」
幸は恐る恐る、小さく握られた手に触れてみた。彗仁は、その手で幸の人差し指をしっかり握った。
「けいと、わかるんだ。この人がね、パパとママのキューピッドなのよ」
凛花はそう言って矢作夫人から、自分の腕に彗仁を譲り受けた。
幸はそう言われると何か報われたような気がして、微笑んだ。
そばにいる大城も、矢作夫人も、もうすっかり一つの家族になっている、穏やかな表情だった。
「幸さん、また落ち着いたら伺いますね」
大城は幸にそう言って、軽くヒトサラカオル食堂の方を指差した。
🥂Glass 1
赤ちゃんは光のようだ。すべての人に向けて愛を発している。
幸はすっかり心があたたまったまま、店にたどり着いた。
このあったかい心持ちのままでいたい。今日のお香はESTEBANのイリスカシミヤにしよう。
マンダリンからローズやアプリコットへ、最後にはカシミアウッドとトンカビーンズの甘さが残る。すぐには料理の香りとはぶつかるだろうが、今日は平日、開店は5時間後だ。
香りの中で、幸はふと「本当に竹内はこの店に来るだろうか」と考えた。
来たとしても、その日にどこまで話すべきなのか。
竹内の元愛人だったミツコが亡くなったこと。ミツコに子どもがいたこと。その息子は竹内の子であること。
そんなことを一気に言っても、にわかに信じてはもらえないだろう。
そして、ミツコの墓にその日に誘うわけにもいかない。竹内はそのためにもう一度横浜へやって来るだろうか。そこまでミツコのことを想っていただろうか。
思い巡らすほどに、それはもう40年以上もの昔話である、と幸は自分に言い聞かせた。
…当時25歳だったミツコは客だった竹内に真剣に惚れ込み、竹内も一時は別居中の妻と別れて、ミツコと結婚しようとしたのだった。
彼はミツコにダイヤモンドの婚約指輪を贈った。
しかし、竹内の妻が彼を引きずって来て店に乗り込み「妻と別れることはない」と言わせた。皆の前で恥をかかされたミツコは、指輪を竹内の妻の腿に投げつけ、そのまま屋上へ駆け上がって、飛び降りようとした。
それを助けたのが幸で、一緒に落ちそうになった二人をいっぺんに引き上げて助けたのがパグだった。
あのとき、肩を落とし、ミツコの目を見られなかった竹内の歪んだ表情。
竹内の妻の高らかな嗤い声。
血相を変えて屋上へと上がっていったベージュのドレスのミツコの背中。
あのあと、ミツコは店を辞め、2年ほど姿を消した。そして再び、誰かの援助で自らの店「マダムミツコ」を立ち上げた。…
昔話のすべてがお香の煙にあぶり出されるようだった。
薄く細くたなびく煙の行方が、ミツコの細い指の間にはさんだバージニアスリムの煙の残像と重なった。
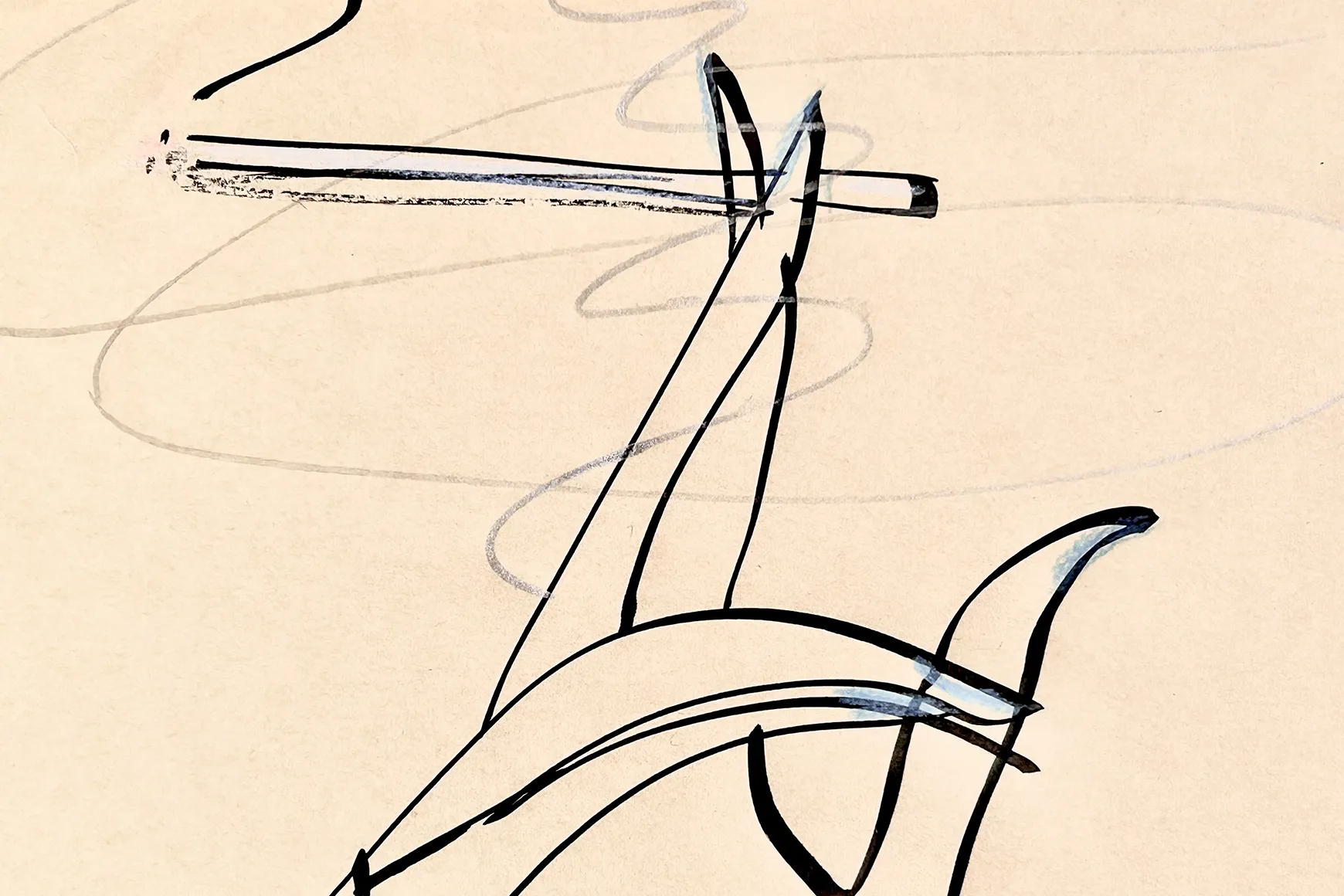
- <<前のページ
- 1/3
- 次のページ>>






