- HOME
- 連載長編小説『4 LOVE NOTES』
- 第2話 『有紗の事情』
-
- 特集
連載長編小説『4 LOVE NOTES』
第2話 『有紗の事情』
《3》
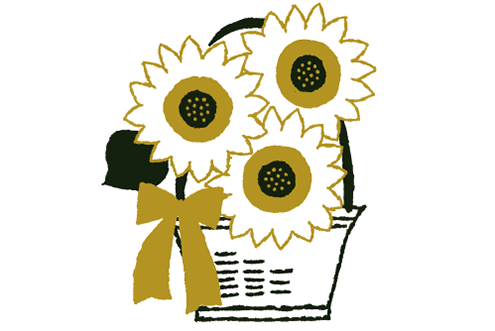
あれから3年ぐらい、いわゆる不倫状態だった。そのうち、勝瀬は友人から東京に店を出さないかという話を持ちかけられ、有紗と一緒に上京することを決めた。
二人は世田谷区の三軒茶屋で同棲しながら、池尻でビストロをやることになったのだった。
店は2人席が2つと窓際の4人席がひとつ。あとはカウンターに6席。2人でやるには十分忙しいが、人を雇うほどでもなかった。
オープン当初は裏道でもあり、なかなか大変だったが、神戸の老舗フレンチ仕込みという勝瀬の料理は、やがて少しずつ客を集め、5年近く経った今では、このあたりの人気店として定着している。
19時を2〜3分過ぎたところで、殿村未知と内畠麻貴がやってきた。
「こんばんは~」
「わー、可愛い店ですね」
未知はブルーのポロシャツっぽいトップスに、ネイビーの細いパンツ。コーチのモノグラムのバッグを肩にかけ、さらに紙袋をもっていた。麻貴はくすんだミントグリーンのトップスに白いスカートといういでたちで、茶色い紙袋から籠につくったひまわりの花を取り出した。
「これ、作ってきました」
「わ、うれしい。すごいきれい」
有紗はぱっと顔を輝かせ、うやうやしく籠を手に取ると、カウンターの真ん中に置いた。未知は「あ、私、手ぶらですみません」と、もじもじした。
「いいんですよ、うちは店だから… 座って座って」
黄色いクロスの敷かれたテーブルに二人が座ると、有紗もエプロンをはずして、カウンターの隅に置き、歌うように言った。
「あとは、タミーさんね」
未知はまだ店のなかを珍しそうに見渡しながら言った。
「あの人、編集長なんですよね。忙しそうですね」
「忙しいと思う。時々、店に雑誌の人が来るけど、みんな忙しそうだもん」
「どんな仕事なんでしょうね」
「ねえ。聞いてみよう」
ところが、鍵崎多美子は20分経っても現れなかった。
「あ、LINEが来てる。半ぐらいになるみたい。飲んでてください、って」
麻貴が言うと、有紗は用意してあったシャンパングラスを運んできた。






