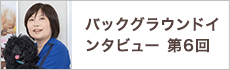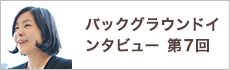- HOME
- バックグラウンド・インタビュー「香を紡ぐ」
- 第9回:塩原紗綾さん(音楽療法士、心理療法士)
-
- 特集
-
香りを紡ぐ人びと
第9回 塩原紗綾さん
(音楽療法士、心理療法士)
一科目ずつ受からないと前に進めない。難関を乗り越えて

東京芸術大学の3年生たちが練習室を取るのにしのぎを削るなか、塩原さんはひたすら図書館へ。そこでふと開いた本にびっくりするものを見つけます。
「ウィーンで声楽を勉強した方のエッセイを広げていたら、偶然、ウィーン国立音楽大学の音楽療法科の入試問題が、日本語で書かれていたのです。」
やはりウィーンで学べということだったのでしょうか。しかし調べると、その入試にはたくさんの課題があり、しかも1科目ずつ受からないと次へ進めないという超難関でした。
「これは厳しいなと思い、1年目は入試を受けてみて感じをつかもうと思いました。東京芸術大学を卒業してウィーンに行き、3~6月まで入試準備。そうしたら1年目で合格してしまい、2001年10月にはウィーン国立音楽大学の音楽療法科で学んでいました。その後、音楽療法士となり、様々なクライアントを診るなかで、心理療法士の資格の必要性も感じ、こちらも学びました。」
「音楽療法」と一言に言っても、様々な形があります。例えば、受動的、能動的の両方があり、その音がどう響いたのか、その時の感情はどうだったのか、意味を考えたり、言語化することもその一つです。
塩原さんは、あえて産休代理などの期限付きの職場を選び、ホスピスと乳幼児以外の様々なクライアントを経験できるようにしたそうです。
自分の中心に戻り、ルーツを感じ取れる香りの必要性

セラピストとして、頭を切り替えるために、香りは欠かせないそう。
「自殺願望、DV被害。現在進行形の人もいます。一人ひとり背景も違い、重い話が多いですから、まずワンセッションが終わる毎に、窓を開けてアロマのルームスプレーを噴霧します。空気と香りで場面を変えるのです。頭に靄がかかってきそうなときは、香りで切り替えます。」
大事なことは、自分がブレないこと。
「人間としてもセラピストとしてもブレちゃいけない。私が不安定になってはいけません。でも自信を持ちすぎてもいけないし、もたなさすぎてもいけない。柳のようにしなりながら、幹と根は相当しっかりと、折れてはいけないのです。」
そのために、塩原さんにはルーツのような香りがあるのです。
「日本では、母も祖母もお香が好きでよくたいていました。伽羅、白檀、沈香といった伝統的な香りがリビングに漂っていた。だから、自分の中心に戻りたいときは、ルーツを感じられるそんな香をたくようにしています。ピシッとするし、落ち着きます。」
ウィーンで、日本人の特性を考える
ウィーンで16年を過ごす塩原さん。海外にいるからこそ、日本人ならではの部分が見えてくると言います。
「日本人は親切できっちりしているのが基本で、他人の言葉の行間を読むという美徳があります。だから私はクライアントが『こう言っているけど、本心はそうじゃないよね』というところが自然に見えたりする。それは日本人でよかったな、と思えるところです。反対に、ウィーンでは、非常によく議論をします。ひとりのクライアントにカウンセラー、作業療法士か看護士、医者の3人がコミュニケーションをとりながら応じる。経過報告をもとに、1時間半以上の会議を週に2度はします。日本人にも時にはそういった議論が必要かもしれないですね。」
塩原さんの言葉はとても丁寧で、あたたかさがありました。日本の香に通じるそこはかとない落ち着き。それは、人と人が向き合うときに何より必要なものなのでしょう。
- <<前のページ
- 2/2
- 次のページ>>
取材・文 森 綾
https://moriaya.jimdo.com/
大阪府生まれ。神戸女学院大学卒業。
スポニチ大阪文化部記者、FM802編成部を経てライターに。92年以来、音楽誌、女性誌、新聞、ウエブなど幅広く著述、著名人のべ2000人以上のインタビュー歴をもつ。
著書などはこちら。
撮影 ヒダキトモコ
https://hidaki.weebly.com