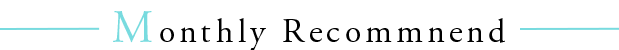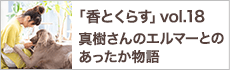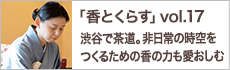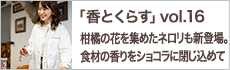1964年、京都で初めてきもの学院を作ったのが、服部有樹子さんのお母様、和子さん。昨夏、和子さんが亡くなり、有樹子さんはその”服部和子きもの学院”の院長を継承しました。和子さんの追い求めたきもの美学を今の時代にさらに発展させ、有樹子さんの新たな美学が始まっています。
モデル業を経てきもの学院を創設した眩しい母親の存在
紫のつけさげを優美に着こなして、笑顔で出迎えてくださった服部有樹子さん。元モデルだったお母様の和子さんの大輪の薔薇のような存在感とは違う、凛と咲いて香りたつ百合のような存在感があります。
「そうですねえ。母のきものは帯も合わせて500点ぐらい遺っています。母は人前に立つことが多く昭和のTVや舞台に映える色鮮やかなものを別染していました。タンスを開けると眩しくて。私はメディアのスタイリストもしていますので、令和のTVや広告などの衣装として母の着物を活かしています」
お母様の和子さんは元モデル。ミスきもの、ミスコットン、ミス西陣に選ばれたそうです。そのパッと明るい美貌で人気になり、多忙を極めた末に、身体を壊してしまったそう。そこで「これからは人の役に立つことをしたい」と、1964年、27歳の時に『服部和子きもの学院』を創設しました。
「お教室はミセスきものに選ばれた方と一緒に始めたそうですが、看板を出すか、トイレ掃除をするのかをじゃんけんで決めていたんだと笑っていました。私たちの父と結婚してからもとても忙しく、ほとんど不在で、時代も良かったんでしょうが、兄(西洋占星術研究家の鏡リュウジさん)と私、それぞれを担当してくれる住み込みのお手伝いさんに来てもらっていました。」
可愛らしい有樹子さんも、3歳ごろからモデルの仕事に借り出されるようになりました。
「七五三に行こうね、ときれいにしてもらって、連れて行かれた先には、知らない男の子もいて。手を繋いでくれと言われて大泣きしてしまい、絶対に繋がなかった。証拠写真もあります(笑)」きもの学院のテキストには、泣きながらしっかりと帯から手を離さない、3歳の有樹子さんが写っていました。
絵を立体にできるきもの世界
やがて有樹子さんは美術に興味をもち始めます。大学は兵庫県西宮市の関西学院大学へ。
「京都の大学だと”和子さんの娘”が常につきまとうような気がして。美術を見ることはとても好きだったし、文学部の美学科へ進みました。大学時代は、テニスをして真っ黒になっていましたが」
就職活動でも京都の銀行を受けると、やはりお母様の話になり「何年でやめるのですか」と聞かれる始末。
「母の光が強すぎて、眩しいばかりで。それに家族に就職している人がいなかったし、その時点では勤めるという意味がわかっていなかったのかもしれません。学芸員の資格ももっていたので、博物館の話もありましたが『虫を消毒する』仕事があると聞いて、虫嫌いなので尻込みしてしまったり。あるとき、きものもアートだということに気がついたんです。それにせっかくの環境は使った方がいいなと素直に思えて。それで京都で人間国宝の方や作家もののきものを扱う企業に就職しました。絵はキャンバス1枚だけれど、きものの反物は長い巻物です。白生地から手描き友禅で染め上げられてきたものを検品する仕事は楽しかったですね。この梅の花一つ、金を括り忘れてます、とか。振袖や訪問着などは、模様が1枚の絵のように描かれ、広げるときは本当に幸せな気持ちで。そのうち、これはどこの機屋さん、どこの染屋さんのものと見分けることもできるようになりました」
入社1年目には『京都きものの女王』にも選ばれ、休日は京都の公の行事にも呼ばれる日々。
「振袖を着て、式典や表彰式の介添え、祇園祭花傘巡行、時代祭。台湾の旅行博、ワシントンD.C.への表敬訪問と桜まつりのパレードなどもあり、海外でも1人で振袖を着られるように練習しました。公私共に振袖は100回位は着ましたね(笑)
会社は2年9ヶ月で退社しましたが、この時期に得たきものの知識と経験、温かな人達との出会いが、私を服部和子きもの学院に導いてくれました」
和子さんは「華やかさで人に負けたらあかん」というきもの選び。でも、有樹子さんはそこで自分の考えを持ち始めます。
「平面のきものを立体にして着るのが面白いと思うようになったんです。着付け方で、描かれた絵をシャープに見せたり丸みを出したり。
もともと現代アートやインスタレーションのようなものが好きでしたから。私の名前の漢字は、樹が有る子と書くので、きものを着る私を樹だと思うようになったんです。例えば、蕾から花が咲いていく様子が描かれた訪問着を娘の入学式に着る。気持ちをきもので表現したらいいんだと」。

きものは体験型アートで、ひとり美術館のようなもの
生徒を教えるだけでなく、俳優やモデルに着付ける、きもののスタイリストとしての仕事も舞い込んできました。
「俳優さんの着付けをして、学んだこともたくさんあります。例えば肩の下あたりに皺が出ないように綿を入れたりしたら、ある俳優さんが『こんなことしたら愛する人の前で脱げる?』と言われたんです。確かにそうだなあと。その人の体の素のラインのままがいい。どう美しい自然なドレープを作るか。何を『美しい』とするか、はその時々で変わる。その頃から、きものが面白くなってきて、広告の仕事もできるようになりました」
自然な身体。自然に美しくどう見せるか。表現の面白さに気づいた有樹子さんに、面白い仕事がどんどん舞い込んできました。
「『番長皿屋敷』のお菊さんや座敷わらしの着付けとか(笑)。美術館関連の仕事も来ました。モネの奥さんが打ち掛けを着て後ろ向きの絵があるのですが、その絵をショーで再現したい、とか。前は何を着ていたかわからない。多分、洋服だったんじゃないかと。でもきものにしましょうと。それで、モネの絵のようなぼかした色合いのきものを着せたりしましたね。竹久夢二の絵を再現した着物のショーでは女神のきものをS字ラインを意識して着付けをしたり」
有樹子さんがやりたかったアートが、まさに今、きものの世界で繰り広げられるようになったということです。もともと美術を勉強していたこともあり、京都芸術大学で教鞭をとることにもなりました。
「私がこんなふうにしたら面白いんじゃないかな、と考えていたことは、現代アートと呼ばれたものがもはや現代ではなくなってきたあたりから、わかってくれる人が増えてきたようです。私にとってきものは、体験型アートであり、ひとり美術館なんですよね」。

香りも全体のしつらいとの兼ね合いが気になる
和子さんから受け継いだものをさらに次の美学へ。
「母から教えてもらったことももちろんたくさんあります。例えば香り。母はお香の香りをきものにしのばせていました。伽羅が好きでしたね」
有樹子さん自身は、香りも全体のしつらいとの兼ね合いが気になるそうです。
「香りはしつらいと合っているのが心地良いと思います。お寺のお香の香りは大好きですが、洋風のリビングに同じものがあっても違うように思うんです。全体の調和と世界観を大切にしたいですね。」
例えば、きものの胸元に、春霞に舞う花びらの柄があれば、帯あげの色で、晴れた空のイメージにするか夕焼けの空のイメージにするかを変えられると言います。
「お茶の世界とも通じますね。きもので四季をまとい、自然のものに包まれることもできる。市中の山居を叶えることもできます」
お母様のきもののなかで一番好きだという小溝一夫さん作の訪問着を見せてくださいました。
色とりどりの花が咲き、風そよぐ光溢れる世界。
一枚のきものから想いを馳せる。
有樹子さんの美学はきものを通し、まだまだ新しい扉を開いていくことでしょう。
photo by Yumi Saito
http://www.yumisaitophoto.com/
Text by Aya Mori