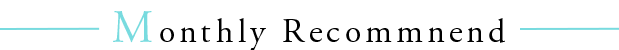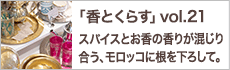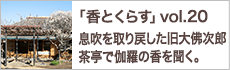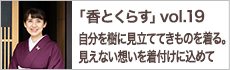帽子デザイナーとなって25年。現在は文京区小日向にアトリエを構え、自らのブランド「SEPT BLEUS」(セット・ブルー)で、ハンドメイドの帽子を作り続ける松信七重さん。自分発ブランドの先駆けとなってきた彼女の暮らしには、その折々に素敵な香りとの出会いがありました。
帽子が実のようになる木
文京区小日向。閑静な住宅街のなかの木の壁の一軒家には、地下に降りる階段が。白い看板には「SEPT BLEUS」の描き文字。地下にも関わらず、明るい光に満ちている空間が、松信七重さんのアトリエです。
出迎えてくれたのは、帽子がまるでりんごの実のように成っている木のディスプレイ。
「ずっとこの木と一緒にいるんです。もうすぐ秋冬の展示会なのですが、今日は春夏の帽子を飾っています」
生成りや青、緑の麻に、羽の形を生地で作ったブローチ。涼しげな麻にくすんだピンクのブレード。どの帽子も、軽くてかぶりやすい形。かぶる人の表情を邪魔しない優しさに満ちています。
高島屋など大きなデパートでコーナーをもつSEPT BLEUSは、長年の顧客や、初めてのお客さんがその帽子を手に取ります。
「『帽子は似合わないの』とおっしゃっていたお客様が、かぶってみて『あら、似合うかしら』と顔を輝かせ、かぶり出してくださるのが嬉しいですね。頭の形は千差万別なので、選び方次第で、似合う形が必ず見つかります。セミオーダーしていただければ、さらにぴったり合うものをおつくりできます」
暑い夏には、洗うことができる帽子もあるのも良いところ。今夏の透けた麻の生地は、なんと彼女のお祖父様のもっていたデッドストックだったとか。
「祖父は生地屋でした。それでこの生地も、祖母が大切に保管してくれていて残っていたものを、何度も手洗いをして、丈夫で涼しげなので帽子にしました」
デッドストックの生地だけではなく、帽子のつばの部分に使うブレードは岡山県にある工場にてオリジナルで製作しています。彼女は古き良きものや素材を見抜く目が確かなのです。

ひとつひとつの小さな仕事がパーツになって、大きな仕事の世界に
そもそも、帽子作りには興味があったという松信さん。でも若い頃はスタイリストの仕事に憧れ、女子美短大を出てから再び専門学校へ。
「洋服を選んでコーディネートするというよりは、自分でつくるコスチューム・アーティストになりたかったんです。専門学校時代、ときどき、ひびのこづえさんのアトリエでお手伝いもさせてもらいました。こづえさんは絵を描いて、生地を選んで、それをお針子さんが作ります。それを見ながら、技術がないと、一生下働きだなあと思いました。そこで週に1回は帽子作家の平田暁夫さんの教室にも通いながら、文化服装学院に立体裁断を勉強しに行ったりしていました」
平田暁夫さんは、日本を代表するオートクチュールの帽子作家で、皇室のプリンセスの帽子を手がけていることでも有名でした。
「その頃は地球儀の形や土星の形の帽子とか変わった帽子ばかりつくっていたのでアトリエに残ってくださいとは言われませんでした(笑)」
専門学校も卒業し、出版社の編集のアルバイトをしながら、時々はひびのこづえさんのアトリエも手伝う日々。
「編集のアルバイトのおかげで、フォトショップやイラストレーター、エクセルの使い方も覚えました。そこからだんだんと、人のご縁も広がっていったんです。知り合いの洋服屋さんで友人と私の帽子のイベントをやれることになったり。雑誌でアーティストの方の帽子を作ったり」
その後、彼女は表参道のスパイラルで展示販売をできるようになりますが、それにはこんなご縁がありました。
「1995年ごろ、表参道のスパイラルでひびのこづえさんの大きなイベントがあり、ボランティアを募集していたんです。そこで気がつくとボランティアのリーダーみたいになっていました。そのときは後にスパイラルで展示販売をできる事になるなんて思ってもいませんでした」
ひとつひとつ、バラバラにやっているように見えたことがひとつひとつのパーツになっていて、今の松信さんの帽子デザイナーとしての世界をつくることになったのです。
「時期も良かったんですね。ちょうどアッシュペーフランスがroomsという、クリエイターを集めるイベントも立ち上げた頃で、そこにも参加しました。roomsは大きなムーブメントをつくったと思います」。

生まれて初めて感じた絶望感。でも今ならパリに住めると思った
松信さんが帽子作りを始めた頃は、デパートの帽子売り場にはまだチューリップハットやキャップのような帽子しかなかった時代でした。「SEPT BLEUS」は東京銀座の松屋や大阪のうめだ阪急から声がかかり、フェアをやれることに。
「楽しいからどんどん帽子をつくっていました。突然、コムデギャルソンから電話がかかってきて、JUNYA WATANABEのコレクションでコラボレーションを依頼されたり。28歳で独立して初めて一人暮らしをしました。お金も入ってきたけど、無駄遣いもしていました。インプットしてあったものをわーっと全部出し切ってしまった感じでした。だんだんと、楽しく無くなってきたんです」
その頃、roomsで仲良くなった人たちと行ったパリで、彼女はこんな経験をしました。
「蚤の市へ行って山のように買い物をして、バスティーユのあたりでホテルがどこかわからなくなってしまったんです。クタクタに疲れてカフェに入っても、オーダーも取りに来てくれなくて、そのまままた外へ出ました。生まれて初めて感じるような絶望感が湧いてきて。でも、そのときなぜか、今なら憧れのパリに住めるかも、と思ったんです」
30歳。当時はワーキングホリデーがぎりぎり申請できたと言います。
「ぎりぎり、ワーキングホリデーで滞在できることになりました。メールが電話回線でやり取りされていた頃です。語学学校にも行きながら、パリの展示会に出てみたら、日本人のバイヤーさんが来てくれたり。日本のroomsにも出るのでたまに帰国しながら、まる3年はいました」。

マレの屋根裏部屋に漂った、ヒヤシンスの香り
住んでいたのは、3区と4区の境目、マレ地区のアールゼメチエール駅付近。
「映画に出てくる様な暖炉があって2〜3部屋あるようなところに住みたかったけど、それは夢物語。小綺麗だけど屋根裏部屋で、100段の階段を上る必要のある部屋でした。あるとき、水栽培のヒヤシンスを買ってきたら、咲き出すとものすごくいい香りで部屋が満たされて。幸せな気持ちになれましたね」
パリの人たちに倣って、香水も楽しみました。
「頬に挨拶のキスをする習慣がありますよね。そのとき、良い香りがするのが素敵だなあと、私も香水を選びに行き、いくつかをその日の気分でつけるのを楽しんでいました」
香りを楽しむ習慣はそこから今も続いています。
「日常的に好きなアロマをブレンドしたスプレーや、ロールオンにして使っています。製作の途中でハーブティーで香りを楽しんだりもします。最近は和の香りもいい香りだなあと思えるようになりました。木や草の香り。楠、松、いぐさなど」
彼女が帽子のために選ぶ生地やブレードも、どこか自然の風合いが感じられるものが多いようです。
香りもそうですが、パリが彼女に与えてくれたものは、目には見えない豊かさ。
「競争の激しい時代もありました。他人のことが気になりすぎることもあった。少しテングになっていたこともあったと思います。でも、フランスで暮らしたことで、仕事にしろ、生活にしろ、私のペースが出来上がったのだと思います。パリの郊外のボタン屋さんで倉庫でボタンを見ている間に、そこのおじさまがランチをつくって振舞って下さる。そういう余裕がいいなと思いました。だから、そういう心の余裕を感じられるうちに、私は日本に帰ろうと。厳しい現実も見ましたから、パリに執着はせずに、また日本で続けていこうと」
今は夫と子どもの3人暮らし。生活を味わいつつ、ますます創作にも意欲が湧いています。帽子の実のなる木は、今年も美味しそうで、良い香りがします。
photo by Yumi Saito
http://www.yumisaitophoto.com/
Text by Aya Mori