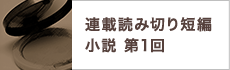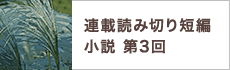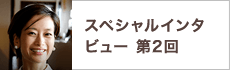- HOME
- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』
- 第2回『LOTUS PLACE』
-
- 特集
連載読み切り短編小説『香りの記憶』
第2話『LOTUS PLACE』
《4》

無事にデザイナーの取材が終わり、最終日になった。
友里江とエリカは、ガウリが手配してくれた車で、街を回ることになった。
「今日は、ホテルの運転手さんが一緒に行ってくれます。私は行きません。どうぞ二人でデリーの街を楽しんでください。夕暮れにおすすめの場所、伝えておきました。LOTUS PLACE。素晴らしいところです」
ガウリは満面の笑みで二人を見送った。黒い大きな車の運転席には、警官のような帽子をかぶってイギリス風のジャケットを着たガタイのいい男がいた。
友里江が英語で話しかけると、彼は肩をすくめた。わかりません、ということだろう。
朝は気温が低かったが、11時頃になると急に日が照り、暑くなった。運転手は時々誰かに電話したり、ネクタイをはずして襟元を緩めたりし始めた。
「もう帰ろう。暑すぎる」
どうやらインドの言葉でそう言って、親指を後ろに向ける。引き返そうと言うのだ。
友里江とエリカは猛然と日本語で怒った。
「バカいってんじゃないわよ!」
「写真撮らなきゃいけないのよっ」
彼はしぶしぶ車を走らせたが、オールドデリーの街並みのほかに、中途半端に都会化されたニューデリーにはあまりフォトジェニックな景色はなかった。
「困ったわねえ。景色でメインになるような写真がないわ」
日が傾き始めると、二人は焦った。すると、男が言った。
「Lotus Place?」
ロータスプレイス?
「ガウリが言ってたところですね」
エリカが言った。二人は頷いて、車は夕日に向かって走り始めた。
やがて見えてきた白い大きな建物は、まさに蓮の花の形だった。
車はそこに止まり、運転手は待っているとジェスチャーで言った。
建物は見たこともないほどに大きく白く、花だった。そして石畳も、天国へ続いているかのように白かった。
ターコイズブルー、ルビー、トパーズ。まるで石のような原色のサリーをまとって身をやつした女たちがそぞろに歩く。その色がかすみがかかったような空気のなかで、夕日に浮き上がって輝くようだ。
ある場所で履物を預け、裸足で建物のなかへ入っていく。
「はいりますか」
「もちろん」
不思議なことにこの国にきてからのいくつもの警戒心が、夢だったように消えていた。
靴を預け、黙って歩く。
建物に入ると、まず、あまりにもかすかでこの世のものとは思えない、いい香りがした。蓮の花の匂いだろうか。その静謐な気に包まれていると、天女に冷たい手で頬を抱かれたようだった。てっぺんまで吹き抜けた天井が、本物の天とつながっていた。
物音ひとつしないのに、そこにはただそこにいる人々があふれていた。
手を合わせているわけでもないのに、皆が思い思いに祈っていた。
それは自分のためにではなく、誰かのために。
友里江とエリカは10メートルほど離れて歩いていた。
やがて建物がから出たとき、二人は顔を見合わせていった。
「私たち、なんで泣いてるんだろう」
二人とも、清々しい顔をしていた。
「ここに来られてよかったね」
「はい。よかった。生きてきて、よかったですよ。たぶん、迷ってもブレてもいいんですよね」
「うん。それが生きてるってことなのかもね」
二人はまた靴を履いて、車に戻った。
友里江はオレンジの夕日を見上げて、その光がまだ待っていてくれたことに感謝した。
エリカはその大きな白い建物を振り返ると、ゆっくりとカメラを構えた。
終
- <<前のページ
- 4/4
- 次のページ>>
作者プロフィール
森 綾
https://moriaya.jimdo.com/
エッセイスト、ライター。
最新刊『Ladystandard』(マイナビ出版)、『一流の女が私だけに教えてくれたこと』(マガジンハウス)など著書多数。
大阪生まれ。神戸女学院大学文学部卒。新聞記者、放送局編成部を経て92年上京してフリーランスに。Web小説では映画『ハンティングパーティー』のノベライズ、映画化された『音楽人』原作などを手がけている。
https://www.amazon.co.jp/%E6%A3%AE-%E7%B6%BE/e/B004LP4KI8