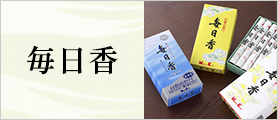- HOME
- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」
- 第251回:浅野祥さん(津軽三味線演奏家)
-
- 特集
-
スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」
第251回:浅野祥さん(津軽三味線演奏家)
《4》震災後、仮設住宅を回った。民謡を弾くと、塞ぎ込んでいた人も踊り出した
津軽三味線と民謡への想いを強くさせたものに、2011年、浅野さんの地元も被害を受けた東北大震災があった。
「自分の地元がヤバい、大変なことになったということで、自分の活動を一旦は減速して、県内の仮設住宅を100箇所ぐらい、三味線をもって回りました。そのときに、そこにいる100人ぐらいのおじいちゃん、おばあちゃんたちが『じゃあ、次はこの曲いこう』と言って弾き出したら、大合唱できるんですよ。そういう音楽ってあったっけ、と。みんなどうして歌詞を知ってるんだろう。…しかも塞ぎ込んでひと言も喋らなかったおばあちゃんが、歌が始まったら踊り出したんですよ。震災って本当に大変なことだったのに、家を無くしたりしているのに、そうなるまで心を動かす音楽ってすごいな、と思ったんです。ああ、もう民謡ばかりだと飽きられるんじゃないかなんて、つまらないことを考えてたらダメだ。この誇りをもって、高らかに歌っていこうと。そのときにお会いした人たちの縁は大きかったし、僕にとっては遺伝子レベルですごいものなんだと知ったプラスの体験でした。あの光景は忘れられません」
浅野さん自身のお祖父様は、彼が12歳のとき、亡くなりました。
「お線香の香りをかぐと、三味線を教えてくれた祖父との最後の1日を思い出すんです。自宅で亡くなったんですが、床の間に寝ていた、最後の時間を、ふと思い出すんです。祖父の口癖は『芸は身を助けるから。嫌になるときがあってもいいけど、絶対に三味線を手放さない方がいいんじゃないか』と、ずっと言っていたんですよ」
「芸は身を助く」。その言葉を、浅野さんはずっと考えていたと言います。
「芸は身を助けるって、どういう意味だろう。子どもの頃は、お金を稼ぐとかそういうことなのかなと思っていました。でもそんなことじゃないと今はわかります。三味線を弾いていなかったら経験できなかったこと、出会えたなかった人がたくさんいる。その震災のときのように、見られなかった光景もあるんです。だから本当に芸は人生の糧になっているんです。お線香の香りに包まれると、亡くなる前の祖父のそばで一心に考えていた、自分を思い出すんです」
津軽三味線と民謡は、浅野さんにとって家族の愛とともにあるものなのだろう。まっすぐで純粋で濃やかな音色は、さらにまた年月とともに育ち、想像もできない場所へと広がっていくに違いない。

- <<前のページ
- 3/3
- 次のページ>>
●公式サイト
http://sho-asano.com/
取材・文 森 綾
フレグラボ編集長。雑誌、新聞、webと媒体を問わず、またインタビュー歴2200人以上、コラム、エッセイ、小説とジャンルを問わずに書く。
近刊は短編小説集『白トリュフとウォッカのスパゲッティ』(スター出版)。小説には映画『音楽人』の原作となった『音楽人1988』など。
エッセイは『一流の女が私だけに教えてくれたこと』(マガジンハウス)など多数。
http://moriaya.jp
https://www.facebook.com/aya.mori1
撮影 萩庭桂太
1966年東京都生まれ。
広告、雑誌のカバーを中心にポートレートを得意とする。
写真集に浜崎あゆみの『URA AYU』(ワニブックス)、北乃きい『Free』(講談社)など。
公式ホームページ
https://keitahaginiwa.com