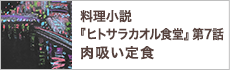🥂Glass 3
「とりあえず、キッシュ、仕上げましょう」
幸は静かに微笑んで、続きの作業をした。
淡々と作業をすることは、心を整える。
グリュイエールとエメンタール、2種類のチーズのシュレッドを敷き、火を入れた野菜とベーコン、生地を注ぐ。紫のオクラとプチトマトをバランスよく飾った。
「さあ、これであとはオーブンが焼いてくれるから。180度で25分くらい焼いてみて、あとは少し温度を上げてちょっといい色にしましょうね」
キッシュが焼ける間にと、幸は冷えたシードルを一本取り出した。
「おつかれさま」
グラスに注ぐと、黄金色が流れでる。繊細な泡が立ち昇った。
「乾杯」
ひと口飲むと、凛花の顔がぱあっと明るくなった。
「キュッとして美味しい!」
「シードルの頂点ね。HEROUTというブランドで、ノルマンディーで古くから作られているそうよ。天然酵母なんだって。他のシードルにはない、気品があるのよね」
「幸さんのそういう知識のある、素敵なところ。ここに来たら、いろんな人と出会えて、いろんな美味しいものとも出会えて、… そういうこと、母はわかってないと思うんです。本当に。さっきは、ごめんなさい」
萎れてしまった花のような表情で、凛花は肩を丸めていた。
幸はさっき彼女の母親が何度も言った「許さない」という言葉を思い出していた。
「おかあさんは自分の価値観に自信があるのね」
幸は言葉を選んだ。その価値観で、娘を縛っていることを、あの女性はわかっているのだろうか。ひょっとしたら凛花は、その価値観からそろそろ抜け出したいと思っているのかもしれない。いや、きっと抜け出さないと、彼女の人生の先が見えない。
凛花はしばらく黙っていたが、きっぱりと言った。
「私は、ここに来たいです」
幸はそれには答えずに、立ち上がって、オーブンを覗いた。
「あと3分、少し温度を上げて焼こうかな」
凛花のグラスが空いていた。
そこに半分だけ、幸はシードルを注いだ。

🥂Glass 4
オーブンからは、クリームと卵とパイのバターがとろけて焼けて香った。
「美味しそうな香りがしてきたわ」
「はい! 香りだけで、まだシードルが飲めそう」
美味しそうな香りは、人の心を上向きにする。
幸は出来上がったパイを網の上に載せて粗熱を取り、そのままホールタルト用の白いボックスに入れた。
そしてそれを、凛花が座っているカウンターの右端に置いた。
「これ、おかあさんに持って帰ってあげて。あなたが初めて焼いたキッシュだから」
「えーっ」
凛花は驚いて、声のトーンが上がった。
「あんな言われ方したのに。いいんですか」
「いいのいいの」
幸は頷いて言った。
「あんな言われ方したから、安心してもらわないと」
「本当に、ごめんなさい」
「あなたが謝ることはないわよ。焼き立てはね、スフレみたいで美味しいのよ」
凛花は、白い箱をじっと見つめて、言った。
「でも私、初めて焼いたキッシュは、大城さんに食べてもらいたかったな」
「あらま」
二人は顔を見合わせて笑った。
幸は凛花の顔を覗き込んだ。
「それはもうちょっと上手くなってからね」
「そう…かもですね」
凛花は卵の失敗を思い出して苦笑いした。
真夏の日は、なかなか暮れようとしなかった。
アイスクーラーから取り出された辛口のシードルの最後の一杯は、心まで二人を涼やかにした。

筆者 森 綾
フレグラボ編集長。雑誌、新聞、webと媒体を問わず、またインタビュー歴2200人以上、コラム、エッセイ、小説とジャンルを問わずに書く。
近刊は短編小説集『白トリュフとウォッカのスパゲッティ』(スター出版)。小説には映画『音楽人』の原作となった『音楽人1988』など。
エッセイは『一流の女が私だけに教えてくれたこと』(マガジンハウス)など多数。
http://moriaya.jp
https://www.facebook.com/aya.mori1
イラスト サイトウマサミツ
イラストレーター。雑誌、パッケージ、室内装飾画、ホスピタルアートなど、手描きでシンプルな線で描く絵は、街の至る所を彩っている。
手描き制作は愛知医大新病院、帝京医大溝の口病院の小児科フロアなど。
絵本に『はだしになっちゃえ』『くりくりくりひろい』(福音館書店)など多数。
書籍イラストレーションに『ラジオ深夜便〜珠玉のことば〜100のメッセージ』など。
https://www.instagram.com/masamitsusaitou/?hl=ja
- <<前のページ
- 3/3
- 次のページ>>