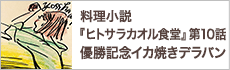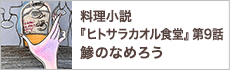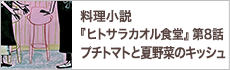🥂Glass 3
そのうちに、2組、3組とお客がやって来て、店は程よく満杯になった。凛花はサービスに忙しくなりながら、大城と彼女のそばを通るときは耳をひくっとそば立てた。
「これ、忘れないうちに、ちゃんと持って帰ってね」
「ああ」
モデル風情の彼女は大城に伊勢丹の紙袋を渡していた。
デザートは、幸が苦労して剥いた栗の甘露煮に、バニラアイスクリームを添えたものだった。
「この栗、手作りね。ほんのりシナモンの香りがして、美味しいわ」
「うん。ここのママ、ちょっとひと味違うものを作るんだよ。… 君もこれから、料理とかするのかなあ」
「単発でいろいろ習いに行ってるんだけど。まあ、基礎からやんないとね。結婚したら、日々の料理って、普通のものだものね」
「うん」
「あなたとは随分、美味しいレストランに行ったけど」
大城はその言葉に、うん、と頷いて無理に笑った。
「まあなんか、俺たち、現実味がなかったのかな」
「楽しかったからいいよ」
やがて、紙ナプキンで少し口元を押さえて、モデル風情の彼女が立ち上がった。
「じゃね。先に行くね」
「うん。気をつけて」
彼女はゆっくりと腰から体を回し、脚を揃えて立ち上がった。その優雅な姿は、そばの席の男性客もしばし目を奪われるほどだった。
「ありがと」
「ああ。ありがとう」
彼女は先に店を出て行ってしまった。大城は背筋を伸ばすように、深呼吸して肩を落とした。
そして、厨房に声をかけた。
「すみません。白ワインを1杯もらえますか」。
🥂Glass 4
1杯目の白ワインはすぐに飲み干され、大城の食後のワインは2杯目になっていた。
彼の目の縁が少し赤くなっていた。
お客はほぼ引けたので、幸はその2杯目のワインにちょっぴり注ぎ足しをした。
カリフォルニアのシャルドネは薄い蜜色のようで、ナッツの香りがゆったりと口中に広がり、余韻が長い。
「すみません。昼間から酔っ払って」
大城は両腕をテーブルに任せたまま、謝った。
幸は微笑んで、静かに言った。
「いいんですよ。彼女、先に帰っちゃったんですね。けんかでもしたんですか」
「いえ、元カノなんです。来週、彼女、結婚式で。僕が貸してたカシミアのカーディガンを、返したいって言うから。なんか二人で会うのが怖くて、この店にしちゃいました」
二人の話を背中で聴きながら、凛花はさっきの落胆がすーっと消えていくのを感じていた。しかし、大城は彼女のことを今も好きなのだとも思った。あんな美しい彼女の代わりに、自分がなれるのか。…無理なんじゃないかな。
さっきの人生最大級の緊張が緩み、頭のなかがグニャグニャだった。
幸は凛花の方を振り向かず、大城の前にいた。
「来てくださってありがとう。いつでもいらしてください。そうだ、クリスマスパーティーしましょうか。ここで」
「ああ。いいですねえ」
数杯のワインで寝ぼけ眼のようになった目で、大城は幸を見上げて、笑った。
大城が帰った後、全部背中で聴き終わった凛花は、洗った皿を拭きながら幸に呟いた。
「あのカラスを八咫烏にするのか、普通のカラスにするのかは、私にかかってますね」
幸はその決意を、応援しなくてはと思った。が、言葉は甘くはしなかった。
「そうね。栗剥きより大変そうだけど」
どのみち、クリスマスは楽しいほうがいい。
幸の頭のなかには、すでにとりどりのメニューが浮かび上がっていた。

筆者 森 綾
フレグラボ編集長。雑誌、新聞、webと媒体を問わず、またインタビュー歴2200人以上、コラム、エッセイ、小説とジャンルを問わずに書く。
近刊は短編小説集『白トリュフとウォッカのスパゲッティ』(スター出版)。小説には映画『音楽人』の原作となった『音楽人1988』など。
エッセイは『一流の女が私だけに教えてくれたこと』(マガジンハウス)など多数。
http://moriaya.jp
https://www.facebook.com/aya.mori1
イラスト サイトウマサミツ
イラストレーター。雑誌、パッケージ、室内装飾画、ホスピタルアートなど、手描きでシンプルな線で描く絵は、街の至る所を彩っている。
手描き制作は愛知医大新病院、帝京医大溝の口病院の小児科フロアなど。
絵本に『はだしになっちゃえ』『くりくりくりひろい』(福音館書店)など多数。
書籍イラストレーションに『ラジオ深夜便〜珠玉のことば〜110のメッセージ』など。
https://www.instagram.com/masamitsusaitou/?hl=ja
- <<前のページ
- 3/3
- 次のページ>>