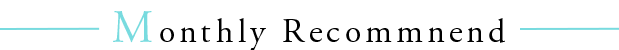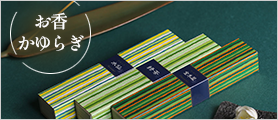天ぷら、担々麺、たたききゅうり。… 胡麻油があるからこそ美味しい料理はたくさんあります。焙煎した胡麻のいい香りは、真夏でも食欲をかき立ててくれます。
そこで、厳選した材料で丁寧に作られている胡麻油を求め、横浜にある岩井の胡麻油の工場を訪ねました。創業168年という歴史ある胡麻油は多く料理人から支持を得て老舗和食や高級中華で使用されています。その本物の香りは、丁寧に丁寧につくられているのです。
プチッと音がするところが、焙煎完了の合図
横浜駅から車で10分。そこにはいくつもの建物が。オフィス棟の入り口には、岩井竜太社長が自らプランターで育てている胡麻がありました。
「これはもちろん商品にはしませんが、どんなふうに胡麻が育つのか、見てみたくてね」
成育し、乾かした胡麻の穂も飾られています。
「胡麻はある程度の段階で刈り取って、乾かし、脱穀します。そのまま放っておくと、弾けてしまうんです」

あまり見ることのない胡麻の穂。ここから胡麻を取り出し、どうやって油にするのでしょう。
まずはお米のように大きな袋に入った胡麻が積み上げられている場所へ。
「この胡麻をまず、ふるいにかけます。殻や砂を取り除くのです。多い時は3%もの石や砂が入っていることもあるのです。しっかりと数度にわたってふるいをかけます」
純粋に胡麻だけになったところでゆっくり焙煎されていきます。
「低めの温度でゆっくり焙煎するのか、高めの温度で早めに焙煎するのか。それによって胡麻油の色や香りが変わっていきます。また焙煎することによって、酸化を止めるという効果もあります。最終的には耳元でつぶしたとき、プチッと音がするくらいまで。職人さんが手作業でチェックしています」
実際に、プチッという音を聴かせてもらいました。人の感覚による作業が続きます。
「さらに蒸してから、すり潰します。特に弊社は基本2番油までしか絞らないので歩留まりの割合で言うと75~85%までしか絞りません。ということは、しぼりかすにも栄養素がかなり残っている。それは卵メーカーさんが鶏の飼料に買ってくださっています。うちはそういう贅沢な絞り方ですが、メーカーによっては溶剤を使って98%まで絞るところもあります」
焙煎して絞った胡麻油は、抗酸化酸力が非常に高いのです。
「先日、30年前にしぼった胡麻油の缶が未開封で出てきたのですが、ほとんど劣化していなかったんです」。

時間も手もかかる匠の胡麻ラー油
焙煎の工場に入ると、一気に熱気が高まります。夏場はサウナ状態。階段を登ると一番てっぺんには、胡麻ラー油をつくる場所もありました。
暑さマックス。釜を覗き込むと、その赤い色と香りが鼻腔にきます。
「焙煎した油に唐辛子を加えていくんですが、色の変化をチェックし、熱を加えては休ませる。それを3〜4日にかけてやります。だからうちの胡麻ラー油は、まず胡麻油の風味を感じて、その後じわじわと辛さが長続きします。熱いスープに入れるとよくわかりますが、夏は冷たい麺に垂らしても美味しいですよ」
少し舐めてみると、確かに柔らかい胡麻油の味から辛味の余韻が追いかけてきてとどまります。
それにしてもこんなに手のかかる工程でつくられているとは驚きです。

最後は分厚いコットンで3回濾過。日本ならではの繊細な仕上げ
胡麻油はしぼっただけでは、まだ製品にはなりません。さらにタンクから濾過していきます。
「コットンで、3回濾過します。雑味、苦味、えぐみを取り除くのです」
濾過するコットンは、デニムのように分厚い白いもの。それで3回も濾過するのですから、とても澄んだ油になります。
「コットンは定期的に、専門の業者に洗ってもらいます。濾過して出た最後の油かすは、馬の蹄の油になるんですよ」
濾過された油も、まだまだ最終的な工程があります。
「最後のタンクに入れて、2週間熟成させるのです。澱を沈殿させ、上澄みのみを製品にします」
この最後の工程を大事にするのは、日本ならではの繊細な仕上げの製法だそうです。
創業は江戸時代末期。石臼玉締めから今のエクスペラーへ
そもそも岩井の胡麻油が創業したのは、1857年。江戸時代の安政の時期です。安政といえば、ペリーの黒船が来航し、開国を迫られた頃。そんな時期から胡麻油がからつくられていたのです。
「その当時の作業の様子はもはや絵でしか残っていませんが、本当に手作業だったようです。昭和に入ってから、平釜式になり、焙煎してつぶして蒸し、ゆっくりプレスする玉締め製法になりました。180キロの重さで2時間くらいかけてプレスし、和紙で漉していました。今はエクスペラー式になり、エクスペラーという機械でプレスしています」
機械化されつつも、随所に人の感覚が生かされている工程に、良質の胡麻油をつくることへの想いがこもっていました。

業務用から家庭の食卓へ
岩井の胡麻油はもともと高級レストラン、天ぷらの店に業務提供をすることが多かったようですが、最近は高級スーパーにも。活性炭で濾過して色と匂いを外した白口も需要が高まっています。
「業務用にしても、なるべく目の届く範囲の店で使ってもらっています。使っている方の顔が見えるので、一緒にブランドを考えたりするのです。例えば、天ぷらだけをやっているところと、うどん屋をやっているところの天ぷらとでは違う香りの方がいいでしょう」
香りへのこだわりはそういうところにも見て取れます。岩井社長は、胡麻油の健康への影響もエビデンスをとって探究しています。
「油って誤解されることが多くて、それ自体ではダイエットに悪いものではありません。油と糖質が結びつくことで太る原因になるんですよね。胡麻油はオレイン酸とリノール酸が半々で、アルコールの分解酵素ももっています。なるべく熱をかけないでつくっていますので、体に良いものだと思いますよ」
暑さで食欲が減退する夏こそ、胡麻油の香りが漂う料理がぴったり。油の質と健康との関係性が見直される今、日常に最高品質の油を使うのは、もはや単なる贅沢ではなさそうです。

岩井の胡麻油 公式サイト
https://www.iwainogomaabura.co.jp/
photo by Yumi Saito
http://www.yumisaitophoto.com/
Text by Aya Mori