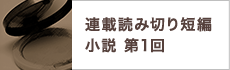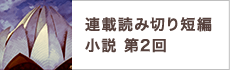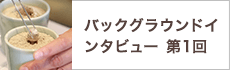- HOME
- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』
- 第3回『仙石原の月』
-
- 特集
連載読み切り短編小説『香りの記憶』
第3話『仙石原の月』
《4》

秋の日はつるべ落としというが、6時から7時の間に、日は一気に落ちた。
宿からバスに乗って、ふたりは仙石原にやってきた。
「ああ」
「これが4万本のすすきか」
ふたりはしばらく立ち尽くした。
月は群青の空にまるく輝き、それを助けるかのように、すすきの道を灯篭が照らしていた。
すすきの野原は月へと続くように広がっている。右に手向ける穂もあれば、左に手向ける穂もあり、上を向いて放心する穂もある。
すべてが風の気のままに右へ左へ、その体を傾ける。まるでゆらめく黄金の大海原のようだ。
1本1本は枯れている。でも、月に照らされ、また命をもらったかのように、いや、残り少ない命を生き切るかのようにうごめいている。
宏之と絵津子はしばらく立ちすくんで眺めていたが、その道をゆっくり歩き始めた。
また立ち止まる。宏之は目を閉じてひとつ深い息をし、言った。
「なあ、絵津子。今、どんな匂いだ」
「… 匂いはしませんよ。すすきですもの」
「そんなことはないだろう。どんな匂いだ。なあ、説明してくれ」
「またそんなことを…」
絵津子はそんな言葉をもたない。匂いの説明などしたことがないのだ。いい匂いか、悪い匂いかくらいしか、気づいたことがない。
それでも目を閉じたまま立ち止まっている宏之に何か言わざるを得なかった。
「昨日、雨が降ったでしょう。だから、風が吹くと、すすきの穂についた雨の匂いが少しします。とっても、いい匂い」
「そうか」
宏之はメガネの奥の目を開いて、にっこり笑った。
「ありがとう」
それは、もう何十年も、ついぞ聞いたことのない言葉だった。
絵津子はたまらなくなって横を向くと、宏之の二の腕のあたりをぽんぽん、と叩いた。
そのとき、絵津子の携帯電話が鳴った。梨沙子からだった。
「どう? きれいでしょ。ケンカしてない?」
「きれいよ。梨沙子も来ればよかったのに」
「いいわよ、私は、彼氏と行くから」
「え」
電話を切ると、宏之が尋ねた。
「梨沙子か。なんだって」
絵津子は月を見上げて微笑んだ。
「後で話します」
吸い込まれそうなほどの月の鏡に照らされて、すすきの海原はやっぱり風を教えてくれていた。
終
- <<前のページ
- 4/4
- 次のページ>>
作者プロフィール
森 綾
https://moriaya.jimdo.com/
エッセイスト、ライター。
最新刊『Ladystandard』(マイナビ出版)、『一流の女が私だけに教えてくれたこと』(マガジンハウス)など著書多数。
大阪生まれ。神戸女学院大学文学部卒。新聞記者、放送局編成部を経て92年上京してフリーランスに。Web小説では映画『ハンティングパーティー』のノベライズ、映画化された『音楽人』原作などを手がけている。
https://www.amazon.co.jp/%E6%A3%AE-%E7%B6%BE/e/B004LP4KI8