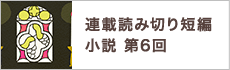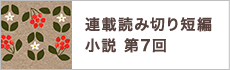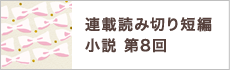- HOME
- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』
- 第9回『桜坂降りるまで』
-
- 小説
-
連載読み切り短編小説『香りの記憶』
第9回『桜坂降りるまで』
《4》
「ごめんなさい、日本人のように触らないで、黙って好きでいるのだった」
アデルはそう言って笑った。亜未はそうされても嫌ではない自分に驚いた。
彼はまるで横断歩道で青信号が点滅しているのを走るときにみたいに、自分のことを話した。学生時代はパーカッション奏者だったこと、日本映画が好きなこと、来月家族が来たら住む場所をこの週末には探しにいくこと。
気づくと亜未も、一生懸命頭のなかで英語の単語を組み立てながら、自分の夢を語っていた。夏までにはニューヨークに行くこと。そこでもう一度、人生を考え直すこと。
やがて二人は、連れ立って外へ出た。
亜未の頭のなかに、名前のないバラードが流れてきた。
「桜を見に行きましょう」
「sakura?」
「そう、あなたは日本に来て、桜を見られてとても幸運よ」
そう言って、歩いた。六本木からまたアークヒルズまで歩いて、スペイン大使館へと続くあの坂道をあがり始めた。
ゆったりと、たゆとうように蛇行する上り坂だ。
24時前ともなれば、さすがに他に人影もない。
ライトアップされ、輝きと赤みを濃くした桜は、亜未の予想以上に美しかった。
花のひとつひとつが、その下を歩く人を微笑んで見守るかのようだ。拒んでも拒んでも終わることがないかのように見える。
二人はひたすら上を向いて歩いた。
時折、アデルは立ち止まり、目を閉じて、眉と眉の間で息をするように香りを吸い込んだ。
「なんていい匂いだ」
亜未も彼の真似をしてみた。強い香りではない。そこらあたりに漂っている優しい香りを、ひとつに撚り合わせて吸い込むようにするのだった。
坂は途中で緩やかに下りになった。
アデルは歩きながら、亜未に尋ねた。
「なぜ、君は僕のことを理解したの」
亜未は小学4年生の頃、いじめられたことがあった。ピアノに通い、ソルフェージュに通い、塾に通っていて、球技大会の練習に出なかったのがきっかけだった。やがて次の学年でクラス替えになって、そんなこともなくなったが。
あのときのずっとひとりぼっちかもしれない感じを、あなたが味わっていたらどうしようと、さっき思ったのよ…。
そんなことを説明しようとして「球技大会」とか「塾」という英単語が出てこないことに気づき、一人で苦笑いした。そして言った。
「亜未は、あなたの友達だから」
アデルは、亜未の手をぎゅっと握った。そして、あっ、と、振り払った。
「日本人のように、触らないで、黙って好きでいるのだった」
亜未は自分でそう言うと、アデルの手を握りなおして、それを大きく前後に振った。
「いいのよ、何人でも。友達なら」
アデルは微笑んで、亜未にはわからない、アラビア語の歌を歌った。そして亜未にも歌わせた。
子どものように、二人は歩いた。
坂道の桜並木は、あと少しでおしまいだった。
終
- <<前のページ
- 4/4
- 次のページ>>
作者プロフィール
森 綾 Aya mori
https://moriaya.jimdo.com/
大阪府生まれ。神戸女学院大学卒業。
スポニチ大阪文化部記者、FM802編成部を経てライターに。
92年以来、音楽誌、女性誌、新聞、ウエブなど幅広く著述、著名人のべ2000人以上のインタビュー歴をもつ。
著書などはこちら。
挿絵プロフィール
オオノ・マユミ mayumi oono
https://o-ono.jp
1975年東京都生まれ、セツ・モードセミナー卒業。
出版社を経て、フリーランスのイラストレーターに。
主な仕事に『マルイチ』(森綾著 マガジンハウス)、『「そこそこ」でいきましょう』(岸本葉子著 中央公論新社)、『PIECE OF CAKE CARD』(かみの工作所)ほか
書籍を中心に活動中。