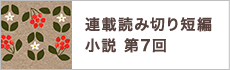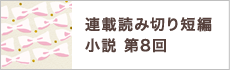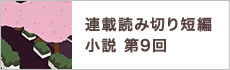- HOME
- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』
- 第10回『雨音演奏会』
-
- 小説
-
連載読み切り短編小説『香りの記憶』
第10回『雨音演奏会』
《3》

表に出ると、またしとしとと雨が降っていた。
ショートヘアの女性はさっさと会計をすませると出てゆき、品川方向へ飛ぶように歩いていった。
木崎と老夫婦は、ゆっくりと傘をさして白金高輪駅までの長い坂道を下ることになった。
「やっぱり、最後はあの曲なのね」
老夫人は前を向いたままそう言った。
「…」
老紳士は黙っていた。木崎は聞いていいものかと逡巡しながら「なぜなんですか」とおそるおそる口にした。
老婦人は語り始めた。
「あのね、あのご主人、10年前にまだ11歳だったお嬢さんを亡くしたの。ヴァイオリンが上手でね、雨の日も風の日も、あの店の奥からヴァイオリンの音が聴こえていたの。ご主人はその音が流れていると、いつもうれしそうでね。『あの娘がいるからがんばらないと』って。あの協奏曲第4番は、お嬢さんが亡くなる前に練習していた曲だった。ご主人はモーツァルトが大好きだったから。雨が降ると、まるでさっきあの蓄音機から聴こえてきたように聴こえたものよ」
やっぱりあれは雑音ではなかったのだ、と木崎は思った。
彼にとって、あれは、雨音だったのだ。
「事故か何かですか」
「交通事故でね、奥さんともどもよ」
「…」
木崎は返す言葉をなくした。50数年も生きていれば、自分のつらさも人のつらさもいくつも見てきた。でも、初夏へと向かうはなやいだ季節のなかで、珈琲の香りと雨の匂いとその話だけは、ここに取り残されそうだった。
だいたい。
人の人生は比べるものではない。誰かの不幸を聞いて、自分のほうが幸せだという考え方ができるほど、木崎はもう若くはなかった。
けれども、木崎にはひとつだけ、気づいたことがあった。
自分は人生のなかで、まだ何も失っていないのだ、と。だからもうちょっと頑張れるのではないかと。
きゅっと唇をひきしめた木崎の表情も見ず、老婦人は前を向いたまま、問わず語りに話し続けた。
「あの人の蓄音機には、あの小さな箱のなかには、きっとお嬢さんがいるのね」
「…」
雨の坂道を3人は下り続けた。木崎はそれ以上その話を聞いているのが苦しくなって、老夫婦のことに話をそらした。
「お二人は、幸せそうですね」
「あら」
老夫人は笑い始めた。ころころとメゾピアノでソプラノのような声だった。老紳士は半分だけ眉を下げて「おい、幸せじゃないのか」と小さい声で言った。
老婦人はうんうん、と頷いてまだ笑顔が残る口元で言った。
「いろいろあったんですよ。いろいろ」
木崎はもうそのいろいろの中身を問わなかった。
3人はまた黙って歩き始めた。
雨音のなかを、それぞれの脳裏にヴァイオリンの音が流れている。
木崎はうちに帰ったら、今夜こそ、珈琲をいれて妻と話そう、と思った。
終
- <<前のページ
- 3/3
- 次のページ>>
作者プロフィール
森 綾 Aya mori
https://moriaya.jimdo.com/
大阪府生まれ。神戸女学院大学卒業。
スポニチ大阪文化部記者、FM802編成部を経てライターに。
92年以来、音楽誌、女性誌、新聞、ウエブなど幅広く著述、著名人のべ2000人以上のインタビュー歴をもつ。
著書などはこちら。
挿絵プロフィール
オオノ・マユミ mayumi oono
https://o-ono.jp
1975年東京都生まれ、セツ・モードセミナー卒業。
出版社を経て、フリーランスのイラストレーターに。
主な仕事に『マルイチ』(森綾著 マガジンハウス)、『「そこそこ」でいきましょう』(岸本葉子著 中央公論新社)、『PIECE OF CAKE CARD』(かみの工作所)ほか
書籍を中心に活動中。
取材協力
大江正雄(蓄音機の会)