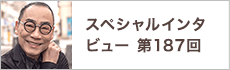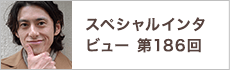- HOME
- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」
- 第189回:三島有紀子さん(映画監督)
-
- 特集
-
スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」
第189回:三島有紀子さん(映画監督)
《3》白で始まって黒で終わる人生。黒でいいんだ
三島監督は脚本も書かれていますが、彼女の映画を何本か見て感じるのは、重要なシーンで、演じる役者の独白が多いこと。
「そうですね。舞台では割と多いですけど、映画では珍しいかもしれませんね。『IMPERIAL…』でも、佐藤浩市さんが一人で喋りながら走っています。実はあれは、コロナ禍のときに、自分が今死んだらどんな人生だったんだろう、と思って自分の人生の年表を口に出してみたのがモチーフになっています。1969年4月22日、大阪・堂島に生まれる…、というふうに」
彼女は笑いながら話してくれましたが、そういう切実なときに自然と出てきたものこそが、真の表現になるという例なのかもしれません。
振り返れば、幼い彼女が被害者となった後、夢中になったのが映画でした。
「事件があったとき、世の中が全部モノクロームになった。でも映画の中だけはカラーだったんです。もちろん、実際にはモノクロの映画もありました。でも花にも建物にも色が付いているように見えるんです。10歳のとき『風と共に去りぬ』を観たのですが、最初のほう、少女時代のスカーレット・オハラが純白のドレスでグリーンの芝生を駆けてくる。最後のシーンは、レット・バトラーにさられた彼女が黒い服を着ている。白から始まって黒で終わるのが人生だな、と思ったんです。幼い私は性被害を受けて自分の体が汚れてしまった、と思っていた。でもいろんな色が混ざって真っ黒になるのが人生。黒でいいんだ。THE ENDを見た瞬間、ああ私は、映画を作る人になろう、と思いました。それまでのぼやけた世界が終わって、パッとピントが合ったんです」
ハッピーエンドの映画。ハッピーエンドではない映画。さまざまな映画が彼女に生きる力をくれたのです。
「本当につらい時には、リアリティのあるものは観たくないものです。だから私はこんな人がいてほしいと思うような人が出てくる美しい映像の映画をつくってきました。でもコロナがあって、劇映画が延期になったり中止になったりするなかで、自分を見つめることができました。もがきながら一生懸命生きるというのは、カッコ悪いけど美しいんですよ。生命存在の美しさは誰もがもっていて、それは誰がどうしたって、穢すことはできないんです」
『一月の声に歓びを刻め』で、れいこがふと、今、映画監督となった三島監督の10歳のときの想いを代弁するセリフがあります。
それはぜひ、映画館で、確かめてください。

- <<前のページ
- 3/3
- 次のページ>>

『一月の声に歓びを刻め』
2月9日(金)テアトル新宿ほか全国公開
© bouquet garni films
出演:前田敦子、カルーセル麻紀、哀川翔
坂東龍汰、片岡礼子、宇野祥平
原田龍二、松本妃代、とよた真帆
脚本・監督:三島有紀子
取材・文 森 綾
フレグラボ編集長。雑誌、新聞、webと媒体を問わず、またインタビュー歴2200人以上、コラム、エッセイ、小説とジャンルを問わずに書く。
近刊は短編小説集『白トリュフとウォッカのスパゲッティ』(スター出版)。小説には映画『音楽人』の原作となった『音楽人1988』など。
エッセイは『一流の女が私だけに教えてくれたこと』(マガジンハウス)など多数。
http://moriaya.jp
https://www.facebook.com/aya.mori1
撮影 萩庭桂太
1966年東京都生まれ。
広告、雑誌のカバーを中心にポートレートを得意とする。
写真集に浜崎あゆみの『URA AYU』(ワニブックス)、北乃きい『Free』(講談社)など。
公式ホームページ
https://keitahaginiwa.com