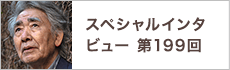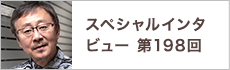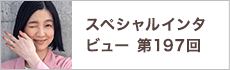- HOME
- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」
- 第200回:林家たい平さん(落語家)
-
- 特集
-
スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」
第200回:林家たい平さん(落語家)
《4》前世はイヌだった!? 人一倍、鼻が利く
さて、たい平さんは、嗅覚に関して、人一倍「鼻が利く」のだそう。
「他の人に『こういう匂いがしません?』と訊いても『しませんよ』と言われてしまうことが多いんです。僕は前世、イヌだったのかもしれません。いや、小学校のとき、イヌを飼いたいと言ったら、ダメ!と言われて『じゃ、俺がイヌになってやる!』と、お皿にミルクを入れてペロペロ舐めていたからかもしれませんが」
青春真っ盛り、高校時代にはこんなことがありました。
「シャワーコロン、って流行ったんですよね。それを彼女がつけていたんです。ところが、その彼女がそばにいなくても、通学路とは違う、ある路地の土蔵と土蔵の間に入って土壁を嗅ぐと、そのシャワーコロンの香りがするんです。あれはなぜだったんだろう。僕はその路地で、よく深呼吸したものです。今でもその香りを嗅ぐと、若かったあの時の気持ちに戻れます!」
それはかなりのこだわり。今でいうところの、匂いフェチという人かもしれません。落語界に入ってからも、こんなことがありました。
「前座時代のことです。僕は志ん朝師匠が大好きでね。もちろん、落語家としての尊敬の念です。当時、汗で濡れた肌じゅばんを楽屋で乾かしてあって、乾いたものを風呂敷に戻すのが前座の仕事だったんです。師匠はおそらくオーデコロンをつけていらっしゃったようです。僕は一番に楽屋に行って『落語が上手くなりますように』と願いながら、その香りを嗅ぎました。なんか、その香りを吸い込めば、名人になれそうな気がして。これはもう、男女を超えて、人として、芸としての憧れですよね」
意図せず、全くありえない場所で、まさかの香りを嗅ぎとることもあるようです。あるときは、あまり行くことのない駅のホームで。
「新富士駅のホームに行くと、父親の頭の匂いがしたんです。誰か、同じポマードをつけた人がいたのかな。思わず『お父さんの香り、しない?』と家族に言いましたが『嗅いだことないからわかんない』と言われましたね」
嗅覚が研ぎ澄まされているたい平さん。とにかく、嗅ぐことを大事にしています。
「鼻が大切。嗅覚が五感のなかで一番大切だと思います。それなのに、ふだんはあまり使っていませんよね。眼で見ることが8〜9割じゃないかな。モノの触感も、スマホのようにつるつるしたものばかり触っていますよね。香りですよ、いま一度、香り。大学3年になるうちの息子も部屋でお香をたいていたりして。心が落ち着くのかな。僕に似ている感じがして嬉しいです」。

《5》ドローンのようにどんどん上に向かって翔んでいきたい。
今年12月、たい平さんは還暦を迎えます。落語家として、60代は体力と気力と実力のバランスが取れる円熟のとき。
「僕はずっと高校時代で止まっている感じでね。60代になったら、余計に青春プレイバックしてやろうと思っています。ドローンのようにどんどん上に向かって翔んでいきたい。危なくないように地面スレスレを飛んでいたって何も見えないですから。高いところに上がれば、見たことのない景色が見えるでしょう。体も動くので、これからが青春です」
今、年齢が若い人たちのことも冷静に見つめます。
「今の若い人は落語が上手なんですよ、本当に。だけどね、若々しさと元気さでは僕は勝てると思う。型にはまることなく、バカだねえ、まだこんなことやってるんだ、と言われ続ける芸人でありたいです」
真面目に語るときのたい平さんの目力の強さと、沈んだ空気も破くことができるようなおおらかな笑顔と。場の空気をつくることができる演者としての底力が、ひしひしと伝わってきました。
確かに「若々しさ」は「若さ」とは別物なのです。

- <<前のページ
- 3/3
- 次のページ>>
取材・文 森 綾
フレグラボ編集長。雑誌、新聞、webと媒体を問わず、またインタビュー歴2200人以上、コラム、エッセイ、小説とジャンルを問わずに書く。
近刊は短編小説集『白トリュフとウォッカのスパゲッティ』(スター出版)。小説には映画『音楽人』の原作となった『音楽人1988』など。
エッセイは『一流の女が私だけに教えてくれたこと』(マガジンハウス)など多数。
http://moriaya.jp
https://www.facebook.com/aya.mori1
撮影 萩庭桂太
1966年東京都生まれ。
広告、雑誌のカバーを中心にポートレートを得意とする。
写真集に浜崎あゆみの『URA AYU』(ワニブックス)、北乃きい『Free』(講談社)など。
公式ホームページ
https://keitahaginiwa.com