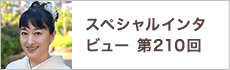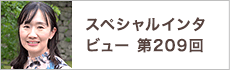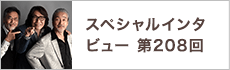- HOME
- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」
- 第211回:春風亭一之輔さん(落語家)
-
- 特集
-
スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」
第211回:春風亭一之輔さん(落語家)
《4》保育園で落語会も。子どもたちは音で笑う
今やラジオ、テレビ、配信、エッセイの執筆と、八面六臂の活躍。「いつもと同じ」感じでいられるのは、あたたかい家族の支えもあってのことでしょう。『笑点』では家族ネタもちらほら。
「まあ、仲は良い方でしょうね。本当に仲が悪かったら、私に冷たいというようなネタは、喧嘩売ってるのか、ってなりますよね。(笑)多少盛らないとね。これと言って、私に仕事のことをなんか言ってくることはないですが、案外楽しく見てるんじゃないかな。前向きには見てないけど、時間があれば録画して見ていたりします」
子どもたちが幼い頃は、保育園への送り迎えもしていたという一之輔パパ。
「ちょうど二つ目の頃かな。僕の場合、3年2ヶ月で二つ目になったんですが、それが一番下で、一番上の二つ目はキャリア15年ぐらいな訳です。そうしたら、二つ目を使うなら、上の方を使いますからね。そこでご祝儀仕事の後は、ぱたっと仕事がなくなりまして。子供をベビーカーに乗せて、公園で稽古したりしていました。オムツとか洗ってましたよ。で、保育園に入れなくてね。かみさんは働いていたけど、書類に父親・無職とか書いたら絶対入れない。週に2回、居酒屋で落語やっています、と書いたら、じゃあそれ以外は子育てしろよとなる。それで、稽古も仕事のうちですから、朝6時に起きて夜9時まで稽古しています、とか書いて。無理やり保育園に入れられました。1番下の娘が保育園を卒業するまでは、送り迎えもしていました」
頼まれて、保育園で落語をしたこともあったそうです。
「子どもたちは結構一生懸命聴いてくれるんですよ。反応はいいです。あと、音で笑いますね。たぬきが出てくる噺とか」
今や地方へ行くと、子どものお客さんも多いそう。音で楽しませる落語。保育園でやったことのある経験も生きているのかもしれません。

《5》出来立ての扇子、手ぬぐいの染めの香りに嬉しさがこもる
一之輔さんの思い出の香りは、真打になったときにつくった、扇子の香り。
「真打のお披露目で、自分の名前が入った扇子をつくるんですね。挨拶で配るんです。扇子には香が染み込ませてあるのか、その新しい高座扇の香りはいい香りですよ。嬉しい気持ちも一緒に、覚えています。いっぱい届いたとき、嬉しかったな。東京の噺家は、平骨の扇子を使います。大阪は一門によって違うようですね。米朝一門はこれだったり、笑福亭は舞扇を使うとか」
そういうお話の一端にも、一之輔さんの落語への深い造詣が伝わってきます。
「手拭いを染めたりもしますね。昨今、どんどん少なくなっているようですが、染め屋さんの香りというのもありますね。私がお世話になっている染め屋さんは江戸川区にあるのですが、毎年1回、色を変えるのに相談に行くんです。そこの作業場の匂いは、なんともいいですね」
毎年、手ぬぐいの色を変えるという一之輔さん。そういう落語家としての慣わしも、とても愛おしげに語られます。ひとつひとつの仕事を大事にされているのでしょう。が、ラジオなどで語られる雰囲気にはあまり熱い感じがしないのも独特の魅力。
「装わないようにしてるんです。やる気がないわけじゃないんですよ。やる気はある、やる気の種はあるけれど、エンジンがかかるのに時間がかかるんです。(笑)無理やり火をつけて、エンジンかけて」
すべて「流れ」のままだと苦笑いします。
「巡り合わせ。流れ、ですね。あんまり計画的に、ビジョンを立てたりはしていません。弟子にはビジョンを持て、と言いますが。自分がしないくせにね。今の状況を良しとするなら、運がいいんでしょう」
5人いるというお弟子さんたちは、一之輔師匠から学んで、また自分の道を見つけていくような気がします。
唯一無二の春風亭一之輔から学んで、また唯一無二の落語家になっていく。
一之輔さんに出会えたお弟子さんたちの幸せは、また優しくて厳しいものなのでしょう。

- <<前のページ
- 3/3
- 次のページ>>
取材・文 森 綾
フレグラボ編集長。雑誌、新聞、webと媒体を問わず、またインタビュー歴2200人以上、コラム、エッセイ、小説とジャンルを問わずに書く。
近刊は短編小説集『白トリュフとウォッカのスパゲッティ』(スター出版)。小説には映画『音楽人』の原作となった『音楽人1988』など。
エッセイは『一流の女が私だけに教えてくれたこと』(マガジンハウス)など多数。
http://moriaya.jp
https://www.facebook.com/aya.mori1
撮影 萩庭桂太
1966年東京都生まれ。
広告、雑誌のカバーを中心にポートレートを得意とする。
写真集に浜崎あゆみの『URA AYU』(ワニブックス)、北乃きい『Free』(講談社)など。
公式ホームページ
https://keitahaginiwa.com