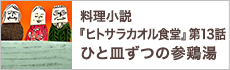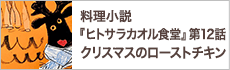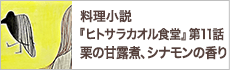🥂Glass 3
「何か召し上がりますか」
幸が訊ねると、佐伯は頬杖をついたまま、目を閉じた。
「この間の参鶏湯は美味しかったなあ。そうだなあ。さっき、ソーセージって聞いたら、ナポリタンが食べたくなった」
「ナポリタン。かしこまりました。おとなっぽく、しますね」
大分産の小さなパプリカを黄色と赤。玉ねぎは6分の1ほど。そして粗挽きソーセージを薄くそぎ切りにする。
にんにくと唐辛子、ソーセージをオリーブオイルで炒める。途中、にんにくと唐辛子は香りがうつったら取り出してしまう。パプリカと玉ねぎも入れてひとつまみの塩で炒める。
そこにトマトペーストとケチャップ、中濃ソースを加えて炒めておく。
太めのスパゲッティを表示時間通りにしっかり茹で、フライパンに移す。そこでマヨネーズを絡める。最後はすべてをしっかりと焼き付ける。少し焦げるくらいに。
そして、セージの葉っぱをちぎって散らし、黒胡椒をガリガリとしっかり振る。
仕上げにパルミジャーノ・レッジャーノを削った。
「はい、おとなナポリタンです」
「おとな。。。どこが、かな」
佐伯はいただきます、とフォークを持ったまま手を合わせ、食べ始めた。
「ん〜」
早い早い。水もワインも手をつけずに一心に食べた。
そして半分ほど食べて、嘆息とともにようやく言った。
「うまい!」
幸は微笑んで、ありがとうございます、とつぶやいた。
佐伯はナポリタンを食べ終えると、さっと紙ナプキンで唇をぬぐい、感想を述べ出した。
「柔らかすぎない太麺も、ちょっと辛めなのもよかった。ソーセージを香ばしく焼き付けてあるのも。それにセージの香りがこんなに合うとは。喫茶店のナポリタンではないけれど、ちゃんとナポリタンだった。また食べたいです」
幸は微笑んで、両手をエプロンの前に合わせて、ちょっとお辞儀をした。
🥂Glass 4
「何か召し上がりますか」
お腹がほどよく満たされた佐伯は、また少し恭仁子のことを話した。
「恭仁子とは、1年生の春から3年の半ばまで付き合ったんです。彼女は結婚したい人で、僕はまだそんなことは考えられなかった。入った大学も、違うと思っていて、音大に入りなおそおうとしていたしね。自分のことしか考えられなかたし。それに僕は…」
佐伯は少し言い淀んでから言った。
「… 今、ここにいる人より、いない人が気になってしまうタチでね」
「… だから、今の彼女の話はなさらないんですね」
「ああ。それはまたちょっと別だけど。あの人はビジネスパートナーという感じだから
幸は他人の恋愛ばかり見てきたから、その状況はちょっとわかる気がした。きっとその今の彼女は、彼のために必死に働いていて、それはまた、彼をビジネスとしていかに売るか、でもあるのだ。
おそらく佐伯はそれに感謝しつつも、恋愛という気持ちを抱きづらいのかもしれない。
しかし「ここにいない人」を思ってしまう男は厄介だ。世間一般には、それを浮気心というのである。
ともかく、彼はここにいない恭仁子のことを、今は愛しているようだった。少なくとも、過去というものは、美化され、温存されている。
「恭仁子さんはあなたにも愛され、ご主人にも愛されているんですね」
佐伯は唇を歪めて微笑んだ。
「良介はいいヤツですよ。あいつは本当に性格がいい。まっすぐに彼女を愛してきた。最初から、ずっと。今も。…彼女も幸せでしょう。僕はこれで良かったと思っていますよ」
「嘘つきですね、佐伯さん」
幸は軽く嫉妬を覚えて、そんなふうに口走ってしまった。
「あ、…ごめんなさい」
佐伯は首を振った。そして静かに言った。
「嘘つきですよ。おとなだから」
二人は顔を見合わせて、仕方なく笑った。途方もなく、おとなになってしまったことを、笑うしかなかったのだった。

筆者 森 綾
フレグラボ編集長。雑誌、新聞、webと媒体を問わず、またインタビュー歴2200人以上、コラム、エッセイ、小説とジャンルを問わずに書く。
近刊は短編小説集『白トリュフとウォッカのスパゲッティ』(スター出版)。小説には映画『音楽人』の原作となった『音楽人1988』など。
エッセイは『一流の女が私だけに教えてくれたこと』(マガジンハウス)など多数。
http://moriaya.jp
https://www.facebook.com/aya.mori1
イラスト サイトウマサミツ
イラストレーター。雑誌、パッケージ、室内装飾画、ホスピタルアートなど、手描きでシンプルな線で描く絵は、街の至る所を彩っている。
手描き制作は愛知医大新病院、帝京医大溝の口病院の小児科フロアなど。
絵本に『はだしになっちゃえ』『くりくりくりひろい』(福音館書店)など多数。
書籍イラストレーションに『ラジオ深夜便〜珠玉のことば〜130のメッセージ』など。
https://www.instagram.com/masamitsusaitou/?hl=ja
- <<前のページ
- 3/3
- 次のページ>>